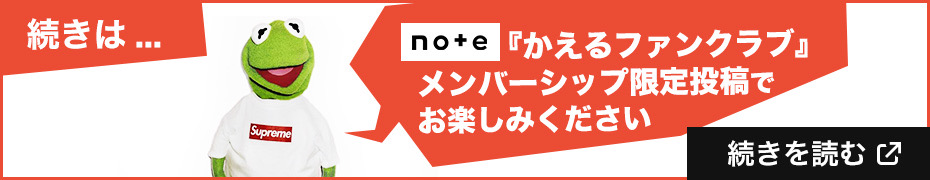外国人持ち株比率の裏事情
株式情報 投資戦略 2024.06.19
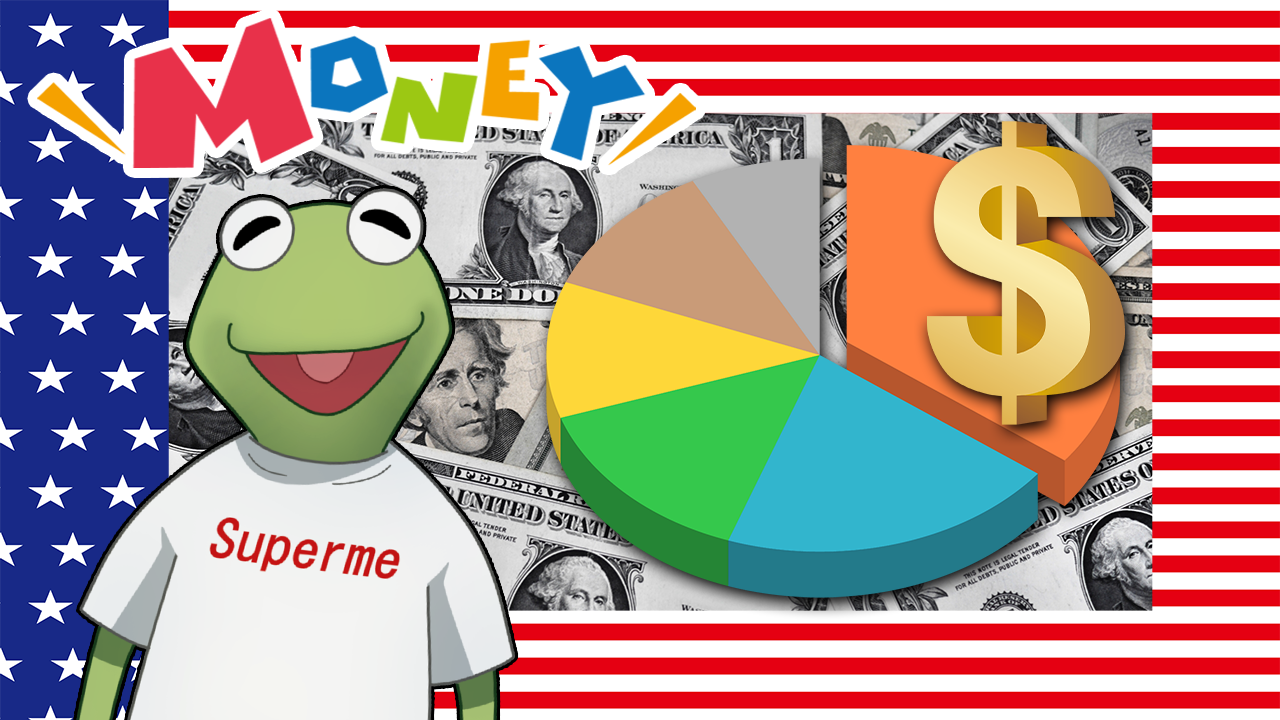
目次
四季報の公開
あーあ、またやってきました..四季報の時期…
四季報は
読むものでなく
投げるもの
株クラ川柳があれば確実に入賞するような(しない)名文句を発表した僕ですが、実は・・・
外国人持ち株比率
は見たりするのです。(四季報ではなく四季報のデータを他の媒体で見る感じ)
何故なら・・?
『外国人持ち株比率が少ない銘柄は、上がらないからです!』
(少ない銘柄は人気低か仕手化、つまり個人のおもちゃにされるしか生きる道はありません)
一方でとあるXの投稿を見て、少し皆様と現状認識を共有したいと思い!
この外国人持ち株比率に関する記事を書こうと思いました。
いわゆるプロの機関投資家相手の証券ビジネス(株式関連業務)って当然のことながら、僕が業界に入った1992年から大きく変わっているのです。
ただ所謂個人投資家の方々の認識はあまり変わっていないのではないかと思いました。
そのギャップを少しだけ埋めたいなと思います。
証券会社マーケット部門
この証券ビジネスについて書くときに一つ明確にしておきたいのが!
証券会社には株式関連業務として・・
マーケット部門
投資銀行部門
引受部門
調査部門
が存在していて、所謂、株式売買に関連する部門はマーケット部門と調査部門であり、今回はそこにフォーカスします。
主人公の一つである証券会社は、マーケット部門および調査部門。
一方投資家サイドは株式をファンドに組み入れられるファンド全般でアクティブファンドとパッシブファンドを含みます。
が..!今回はどちらかというとアクティブファンドの話です。
まず、証券会社のマーケット部門の基本的なビジネスモデルは・・
委託注文から得る手数料収入
自己売買部門での売買損益
によって成り立っています。
 証券会社ビジネスイメージ(かつて)
証券会社ビジネスイメージ(かつて)
委託注文、つまり顧客から注文をいただいたその手数料収入ビジネスの場合、かつては証券会社のアナリストがレポートを書き、そのレポートをセールスが投資家に伝えることによる対価が手数料の主な源泉でした。
証券会社のアナリストは、担当企業の分析をするために会社訪問や同業他社訪問、業界分析などなどをするコストを払ってレポートを書いています。
セールスはそのアナリストとのミーティングを投資家とセッティングするためにコンタクトをして訪問するのですが、当然給料以外に交通費がかかります。
アナリストやセールスのエリアはコンテンツサイドと呼ばれ、このコンテンツを作り出すためのコストがかかる…当たり前のことです。
投資家はコンテンツの対価に手数料を支払うのですが、同時に注文の発注時トレーディングサイドへの手数料を支払うのです。
これは例えば、アルゴリズムを利用する際の回線やシステム使用料、トレーダーからの情報量なども含まれます。
つまり!
委託手数料=コンテンツサービス対価+トレーディングサービス対価
というわけです。
通常その時の手数料率はbp(べーしす)という単位なのですが話を分かりやすくするために100とします。
手数料100を構成するものを細分化するとコンテンツサービスとトレーディングサービスになりますが、常に議論となるのがこの配分です。
特に外資系証券はこの金額がボーナスに直結するので大変です。
正直どの割合が妥当かなど正解はないのですが、通常、投資家がブローカー評価をするときに総合得点はこのように算出されるということを公表することが多いので、その割合を参考にすることが多かったです。
トレーディングの重要性
しかしながらここ15年くらいを見てみるとこの考え方が大きく変わりました。
変化を起こした最大の要因はトレーディングコストが脚光を浴びた事です。
話を簡単にするために一つ例を挙げます。
1000株ある株を買う投資家がいたとします。
前日引値が100円、その後ファンドマネージャーが買い判断をし発注したとします。
翌日寄付きが105円
翌日引け値が109円
の株式で
証券会社A社のアルゴの約定値107円 手数料率0.5%
証券会社B社のアルゴの約定値106円 手数料率1%
だとすると
証券会社A社への受渡代金は107535円
証券会社B社への受渡代金は107060円
つまりB社への支払手数料は高いけれど執行能力が高いのでトータルの受渡代金が安く済んだ(つまりコストが少なくて済んだ)ということになります。
何が言いたいかというと、コンテンツサイドで評価が高い証券会社だとしてもトレーディング能力が低い証券会社であれば支払いコストがかさんでしまっている可能性があるという考え方。
この考え方は2010年代中盤でMiFID2の議論が巻き起こった時に大いに議論されたポイントでもありました。
MiFID 2|証券用語解説集|野村證券野村證券の証券用語解説集「MiFID 2」のページ。新聞やニュースなどでも使われる証券用語をわかりやすく解説しています。www.nomura.co.jp
 証券会社のビジネスイメージ(2010年代半ば以降)
証券会社のビジネスイメージ(2010年代半ば以降)
もちろん先ほど紹介した古典的証券会社ビジネスイメージは今でも存在しています。
それでも手数料配分割合が限りなく50:50、時にはコンテンツサイドが50以下なんてことも起きるようになりました。
昨今インデックスファンドを中心とするパッシブファンドはほぼ100%トレーディングサービス。
何故ならば、大手運用会社はそれぞれがアナリストを抱え証券会社のアナリストに頼る必要がなくなり、証券会社に期待するものは最新鋭のトレーディングシステムになったためです。
また法人関係情報の扱いにおいて企業とアナリストとのコミュニケーションが厳格化されたため、耳寄り情報が出せず、情報の差別化がしにくくなっているので、なかなか優位性が保てないエリアになってしまったという業界事情もあります。
証券会社によるリサーチ部門戦略
投資家による証券会社コンテンツサービスへの見方の変化は証券会社リサーチ部門の体制変更へとつながりました。
外資系証券会社は大型株特化のリサーチ体制へと舵を切ることになります。
以前は外資系証券会社にも名の通った中小型株アナリストはたくさんいました。
こう考えてみれば分かりやすいと思います。
大型株だろうが小型株だろうが、会社の調査分析の工数自体はそれほど変わらない、一方で投資家からの注文は大型株の方が大きい(時価総額や流動性の違い)ので受け入れ手数料が多い。
もっと具体的な話をするとトヨタ自動車株のリサーチに対する対価は例えば500億円分かもしれませんが、中小型株だと10億円分しか返ってこないと言えば分かりやすいでしょうか?
単純な話です。
であれば、外資系証券会社は大型株(MSCIに採用されているような)に特化した方が収益的に効率が良いということになります。
日本の国内大手証券辺りがこの辺のジレンマを今抱えているのかもしれません。
例えばトヨタ自動車株を例にとると現在多くの証券会社がレーティングを出している訳ですが概ね買いなのです。
それでもビジネスの事を考えると全方位的にカバーをせざるを得ずマーケットが今年のQ1の様であれば全く問題ないでしょうが、今のように売買代金が減ってきてボックス相場だと一気にコストがきつくなるのはそのためです。
外国人持ち株比率を見てみよう
日本の現状を見てみると東証の夜間取引の話は僕は聞いたことがなく、引けの時間が30分延長されることで大騒ぎです。
急に外国人持ち株比率ですが、今日のメインテーマです。
ここまで証券会社のビジネスモデルの変遷を書いてきた理由も理解できると思います。

東証株式分布状況調査2022年版
毎年7月頭に東証から株式分布調査レポートが出されます。今年もあと3週間ほどですね。
こちらを見る限り現在の外国人保有率は約30%ということになります。
つまり個別銘柄(特にMSCI採用の大型株)に関しては外国人持ち株比率が30%を一つの基準として考えれば良いのです。
・30%を超えている銘柄
外国人人気が高い銘柄ではあるがこれ以上外国人が買ってくるかどうかは正直微妙
・30%を大きく下回っている銘柄
外国人が全く興味を示していない、もしくは知らない銘柄。
買えない銘柄の可能性もある。
ここで!今回注目したいのは・・・!?
株式情報 投資戦略 2024.06.19

この記事を書いた人
元クレディ・スイス証券株式本部長マネジングディレクター。
日系証券個人営業から証券人生をスタート。その後ロンドンと東京を拠点に20年以上に渡って外資系証券会社の主にトレーディングデスク及び各マネジメント職を歴任。2019年退職。得意分野はフローの裏側分析及び市場構造分析。現在はXやnoteなどで個人投資家向け株式投資の知識提供中心に悠々自適生活を送る。趣味は食とクルマ。
アクセスランキング
- デイリー
- 週間
- 月間