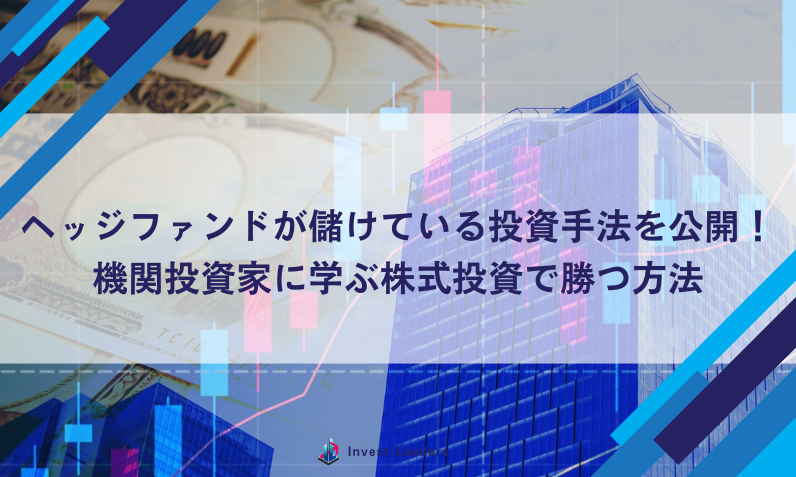ヘッジファンドは、ロング・ショート戦略やテーマ投資を通じて、市場全体の変動に左右されずにリスクを管理しながら超過リターン(アルファ)を追求します。
銘柄選定ではファンダメンタル分析や同業比較を重視し、タイミングに応じた段階的なエントリー・エグジットを行っています。
この記事では、実際にポートフォリオ・マネージャーとして株式運用を行っていた筆者が、ヘッジファンドがどのような投資を行っているのかという具体的な手法を、個人投資家向けに解説します。
[関連]機関投資家(きかんとうしか)とは?種類と役割、個人投資家との違いを徹底解説
ヘッジファンドの儲けの仕組みを徹底解剖

ヘッジファンドは、主に「管理報酬(固定報酬)」と「成功報酬(変動報酬)」の2つで収益を上げています。
投資面では市場価格の歪みやイベント(M&A、金利変動など)を利用して利益を狙います。
たとえば、割安な株を買って割高な株を空売りする「ロング・ショート戦略」や、為替・金利・商品などを動かす「マクロ戦略」などです。
これらは市場全体の上げ下げに左右されず、独自の分析力や判断力による収益を狙う運用です。
ファンド自体のビジネスとしては「2 and 20」と呼ばれる報酬体系が一般的です。
これは、運用資産の2%を年間の固定報酬として受け取り、運用で得た利益の20%を成功報酬としてもらう仕組みです。
つまり、運用で成果を上げれば上げるほど、ファンドの収益も大きくなります。
要するに、ヘッジファンドは「市場の歪みを見抜いて稼ぐ運用の腕」と「成功報酬型のビジネスモデル」の両方で利益を上げているのです。
アルファ(α)とベータ(β)とは?利益の源泉をどう捉えるか

投資の世界では、リターンの源泉を大きく「アルファ(α)」と「ベータ(β)」に分けて考えます。
ベータとは、市場全体の動きに連動して得られるリターンのことです。
たとえば株式市場全体が上がれば、多くの株が一緒に上昇します。
この「波に乗る」ような収益がベータであり、インデックスファンドやETFなどの受動的な投資(パッシブ投資)では、このベータをそのまま取りにいきます。
ベータは市場平均そのものなので、誰でも比較的容易に獲得できます。
一方のアルファは、市場全体の動きとは関係なく、投資家や運用者の分析力・判断力によって得られる「超過リターン」を指します。
やや乱雑な議論ではありますが、市場平均が10%上がった年にあるファンドが15%のリターンを上げたとすれば、そのうち市場の上昇で得られた10%がベータ、残りの5%がアルファということになります。
つまりアルファは「波を読む力」や「独自の工夫による成果」といえ、運用能力の高低が大きく影響します。
[関連]株式投資におけるリスクヘッジとは?機関投資家から学ぶリスクの管理方法
ヘッジファンドの代表的な投資戦略とは?

ヘッジファンドはアルファの獲得を目指す代表的な存在です。
彼らは「絶対収益の追求(市場全体の方向に関係なく利益を狙う)」ことを目的として、多様で高度な手法を組み合わせています。
以下に主要な戦略カテゴリーと概要を整理します。
なお、筆者がポートフォリオ・マネージャーとして株式運用を行っていた際はロング・ショート戦略に主に従事していました。
1. ロング・ショート戦略(Long/Short Equity)
ロング・ショートとは、割安と判断した銘柄を買い(ロング)、割高と判断した銘柄を空売り(ショート)して、市場全体の動きによる影響を抑えつつ、銘柄間の相対的な価格差で利益を狙う戦略です。
《例》同業他社のうち、業績が良いA社を買い、割高なB社を空売り。
2. グローバル・マクロ戦略(Global Macro)
グローバル・マクロとは、金利、為替、株式、コモディティなど、世界的なマクロ経済動向に基づきポジションを取る戦略です。
《例》米国金利上昇を予想してドル買い・国債売り。
3. イベント・ドリブン戦略(Event-Driven)
イベント・ドリブンとは、企業イベント(M&A、再編、倒産、スピンオフ等)に伴う価格変動を狙う戦略です。
《例》
M&Aアービトラージ(買収発表後、ターゲット企業株を買い、買収企業株を空売り)
ディストレスト債投資(経営難企業の債券を割安で購入し、再建・清算で利益を得る)
4. アービトラージ戦略(Arbitrage Strategies)
アービトラージとは、市場間・商品間の価格歪みを利用してリスクの低い裁定取引を行う戦略です。
《例》
転換社債アービトラージ(転換社債を買い、対応する株を空売り)
統計的アービトラージ(AIや数量モデルを使い、ペアトレードなどで小さな価格乖離を狙った取引を繰り返す)
5. マネージド・フューチャーズ/CTA(Managed Futures/Commodity Trading Advisor)
マネージド・フューチャーズやCTAとは、先物・オプションを使い、トレンドフォロー型のシステム取引を行う戦略です。
6. クオンツ戦略(Quantitative Strategies)
クオンツとは、統計・機械学習・データ分析を使い、システマティックに投資を行う戦略を指します。
人的判断を排して、データ主導で運用を行います。
《例》
バリュー、モメンタム、サイズなどのファクター(収益要因)に注目したモデルを用いた戦略
高速で注文を出し、小さな価格差を積み上げて稼ぐ高頻度取引(HFT)
AIモデルによる予測取引
7. マルチストラテジー(Multi-Strategy)
複数の戦略を組み合わせて、リスク分散と安定した収益を追求します。
相関の低い戦略を組み合わせることでボラティリティを抑制できるため、大型ファンドに多い戦略です。
機関投資家が有望銘柄を見つける方法!仕事内容を公開

ここからはより具体的に、ロングショート戦略の運用者の1日と仕事の流れを紹介します。
① 朝:情報収集とポジション確認
・ニュースチェック:経済指標、企業決算、業界ニュース、金利動向などを確認。特に保有銘柄や注目セクターのニュースは最優先。
・ポートフォリオレビュー:昨日の価格変動でポジションのリスク(ベータやネットエクスポージャー)がどう変わったかを分析。
・社内ミーティング:チーム(ファンドマネージャーやアナリスト)でマーケット状況の共有、リスクマネージャーとのディスカッション。
② 午前〜午後:投資アイデアの探索
ロングショート戦略の運用者は、常に「割安な銘柄を買い(ロング)」「割高な銘柄を売る(ショート)」機会を探しています。
アイデアは意外にも、雑談や偶然から生まれることが多いです。
・同業他社の決算説明会で出た一言(多くの国内外の業界や企業に精通する必要がある)
・経営者の語調の変化(同じ会社を定点観測していることで変化に気づく)
・新技術や法改正の記事(半導体や生成AIなど技術動向にも勉強を欠かさず理解する)
・同業種内の「評価ギャップ」への違和感
運用者は常にこうした違和感を拾い、「なぜそうなっているのか?」を掘り下げる習慣を持っています。
それが投資アイデアの種になります。
アイデアには、以下のようなパターンがあります。
(a) テーマ発想型(トップダウン)
《例》「金利上昇局面では地方銀行株が有利では?」
→ 銀行業界を横断的に分析
→ 各社の財務構造・感応度を比較。
割安・割高企業を抽出し、「ロング:堅実な地方銀行」「ショート:高PERのリテール銀行」というペアでロング・ショートのポジションを構築する。
(b) 企業比較型(ボトムアップ)
同業他社比較でのミスプライスを狙う。
《例》「A社とB社は似た事業構造なのに、B社の方がPERが倍近い」
→ ファンダメンタルを掘り下げて理由を検証。
(c) イベントドリブン
決算、M&A、業界再編など特定イベントから歪みを発見。
《例》「A社の子会社上場で親会社の価値が正当に評価されていない」
→ 親会社ロング。
(d) 定量モデルからのシグナル
クオンツ的にスクリーニングして「成長率・利益率・バリュエーション」の異常値を見つける。
クオンツモデルは補助的に使われ、最終判断は人間が意思決定を行うのが一般的。
③ 午前〜午後:分析プロセス(アイデアを磨く)
投資アイデアが定まったら、運用者とアナリストが協働して、次の3点を深掘りします。
(a) ファンダメンタル分析
・財務諸表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書など)、決算資料、IRヒアリングを通じて利益構造やキャッシュフローを精査。
・企業訪問や経営陣インタビューも重要。
(b) リスク評価
・どの要因で損をする可能性があるかを洗い出す (例:マクロ要因、業界全体のショック、モデル誤差など)
(c) リレーション分析
・ロングとショートの組み合わせが適切にポートフォリオ全体をヘッジ(相殺)できているかを検証。
例えば、同じ業界内でのペア(A社ロング、B社ショート)なら、市場全体の動きより企業差に賭ける構造にできる。
④ 午後:ポジション構築とリスク管理
・発注タイミングとサイズ調整:流動性・出来高・市場センチメントを見ながら発注。
・ヘッジ調整:市場全体の変動に対してネットポジション(ロング−ショート)が中立になるよう調整。
・デリバティブ活用:インデックス先物やオプションでリスクを細かく制御。
⑤ 終盤:振り返りと次への準備
・日次のパフォーマンス分析:どのポジションが寄与したか・損を出したかを振り返る。
・「なぜ勝てた/負けたのか」を定性的に記録。
・夜は米国市場の動向をモニターする。
ロング・ショート運用者の本質
「マーケットの歪みを発見し、合理的な価格修正に先回りして賭ける」
これがロングショート運用者の仕事の本質です。
ニュースを読む、数字を分析する、企業に会う──すべてはこの“歪み探し”のためにあります。
そして、1つのアイデアが利益を生むまでに、数週間〜数か月の地道な分析が積み重ねられています。
ロング・ショート戦略の具体例(トヨタ vs日産)

日産自動車とトヨタ自動車のロングショート戦略は、両社の経営戦略や市場での評価の違いを活かした投資手法としてこれまで数年間にわたって有効に機能しています。
以下に、その背景と投資判断の根拠を詳しく説明します。
トヨタ vs 日産:ロングショート戦略の背景
トヨタ自動車は、HVを中心とした電動化戦略を採用し、内燃機関の技術にも強みを持っています。
HVはガソリン車からEVへ移行するなかで、現時点での最適解として消費者に広く受け入れられており、結果として米国事業は相対的に良好です。
世界的に認知度が高く、ブランド価値も高いため、長期的な投資対象として魅力的です。
一方の日産自動車は、EV(電気自動車)への移行を積極的に進めており、特に「e-POWER」技術を中心とした電動化戦略を展開しています。
しかし、EVに対しては近年、向かい風が強いことに加え、同社はハイブリッド車(HV)の米国展開が遅れており、結果として近年の業績・株価は低迷しています。
また、経営の不安定さやガバナンスの問題が報じられており、投資家からの信頼が低下しています。
こうした違いを考慮し、トヨタ自動車を買い、日産自動車を空売りするポジションを構築することで、為替などのリスクを限定して、利益を狙えます。
[関連]トヨタ自動車の下値目途の目安とは?長期の株価推移から買い時を徹底分析
[関連]日産自動車の株価が安い理由は?今後低迷から復活するかをアナリストが分析!
エントリーとエグジットのタイミング
日産の業績発表や経営に関するニュースが発表されたタイミングで、株価の反応を見てエントリーします。
特に、業績の下方修正や経営の不安定さが明らかになった際に、ショートポジションを構築します。
日産の業績改善や経営の安定が確認された場合、ショートポジションを解消します。
また、トヨタのEV戦略の進展や市場での評価の変化が見られた際には、ロングポジションを調整します。
リスク管理と注意点
自動車業界は景気やトランプ大統領の関税政策の影響を受けやすく、市場の変動により株価が大きく変動する可能性があります。
そのため、ポジションサイズの調整やヘッジ手段の活用が重要です。
また、企業の戦略変更や新技術の導入により、投資判断が変わる可能性があります。
定期的な情報収集と分析を行い、柔軟な対応が求められます。
プロの運用手法、個人投資家はどう活かす?
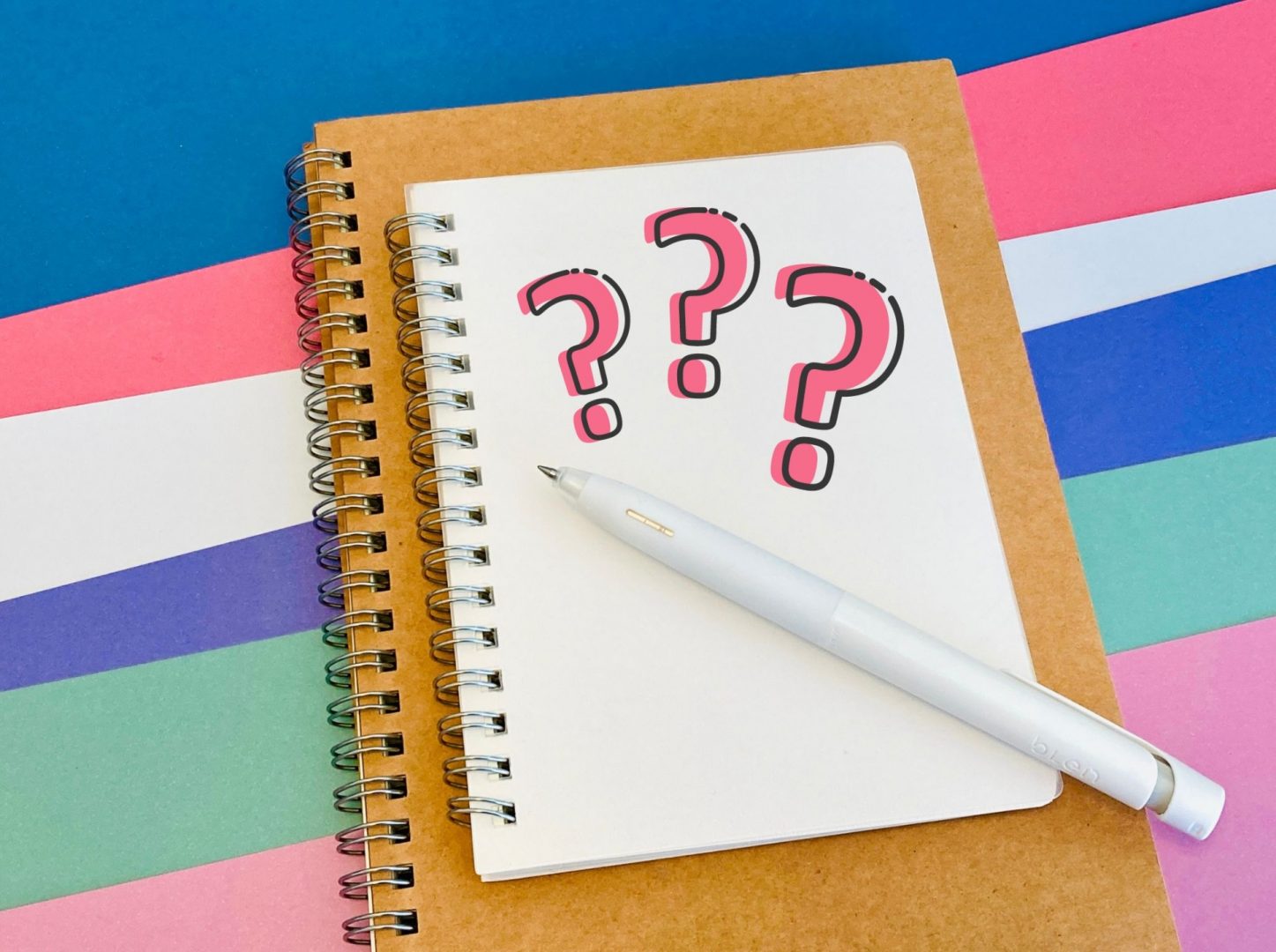
ヘッジファンドは企業の財務状況、成長性、業界でのポジションなどのファンダメンタルを徹底分析しています。
個人投資家も銘柄選定では、「企業価値」「収益構造」「競合優位性」を理解することが重要です。
また、トヨタと日産の事例のように、同業他社との比較で割安・割高を判断する手法も有効です。
個人でも、複数銘柄を比較し、リスクを分散させながら投資機会を見つけることができます。
さらに、ヘッジファンドはAIやEVといった成長テーマや、政府の景気政策などマクロ要因を加味して戦略を立てる場合が多いです。
単一銘柄に依存せず、産業やテーマのトレンドを意識して投資判断をすることで、長期的なリターン向上につながります。
要するに、個人投資家がヘッジファンドの運用から学べる本質は、「銘柄を選ぶ力」や「市場・テーマを読む力」です。
ファンダメンタルと相対評価を意識し、テーマやマクロを踏まえることで、プロに近い投資判断ができるようになります。
執筆者情報

Marina Bay Capital Advisors Pte Ltd (シンガポール) CEO / 記事監修
大学卒業後、ゴールドマン・サックス証券など大手証券会社の投資調査部にてシニアアナリストとして日本株を担当。日経アナリストランキング首位。日本経済新聞、テレビ東京等のメディアにも多数出演。その後、世界有数の株式ヘッジファンドにて日本株ロング・ショートファンドの運用に従事。日本株運用のマネージング・ディレクター、日本株運用責任者などを歴任。ロング・ショート運用を通じて、国内外の様々な業界や企業に精通。
![Invest Leaders[インベストリーダーズ]](https://jioinc.jp/investleaders/wp-content/uploads/2025/07/logo_01.png)