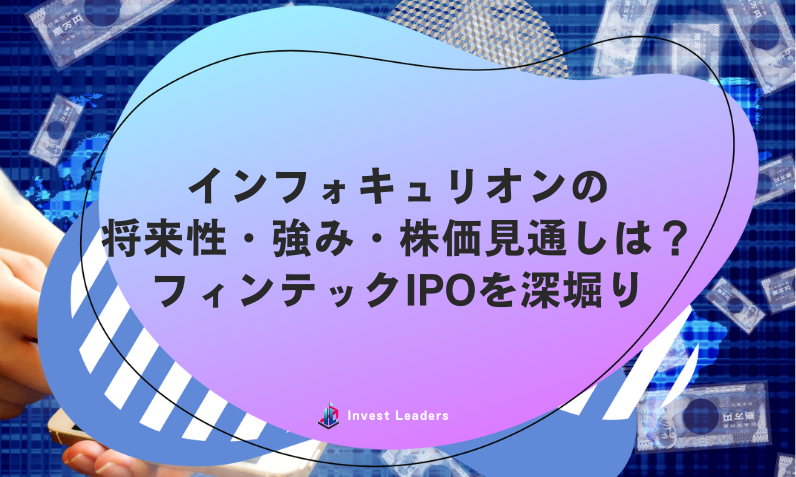インフキュリオンは2025年10月24日に東証グロース市場に上場するIPOです。
消費者向けから事業者間まで、あらゆる産業の事業者や金融機関に決済・金融機能を実装する事業を展開しており、デジタル決済関連というテーマ性を有しています。
また、三井住友カードや三井住友銀行が大株主となっているため、バックボーンの強さが市場の注目を集めるでしょう。
本記事では、インフキュリオンへのセカンダリー投資を検討している個人投資家に向けて、同社の強みや業績、売買で利益を狙うための具体的な戦略を解説します。
インフキュリオンはどんな企業?概要を紹介!

インフォキュリオンは、次世代型の決済システムを中心とした金融サービスを機能単位で柔軟に利用するためのプラットフォームを提供しています。
また、プラットフォームの導入支援を含む決済・金融領域全般に関するコンサルティングサービスも展開。
顧客は幅広く、大手金融機関から新たにフィンテック市場に参入する新興企業まで、あらゆる事業者を対象としています。
具体的な事業内容は、カード・ウォレット発行、チャージ、送金、加盟店決済などの決済基盤、請求書作成・配信、分割・前払い等の金融機能を提供するB2B請求および回収。
本人確認、与信、口座・カード連携などをAPIで提供したり、要件定義から導入、運用まで一気通貫で支援するコンサルティングを手掛けたりしています。
わかりやすく言えば、非金融企業でも自社サービスに、金融の部品を素早く埋め込めるようにする企業ということです。
なお、金融機関にとっても、インフォキュリオンの基盤を活用することで新サービスを短期間で立ち上げられるメリットがあります。
インフキュリオンの売上高規模は?決算を確認
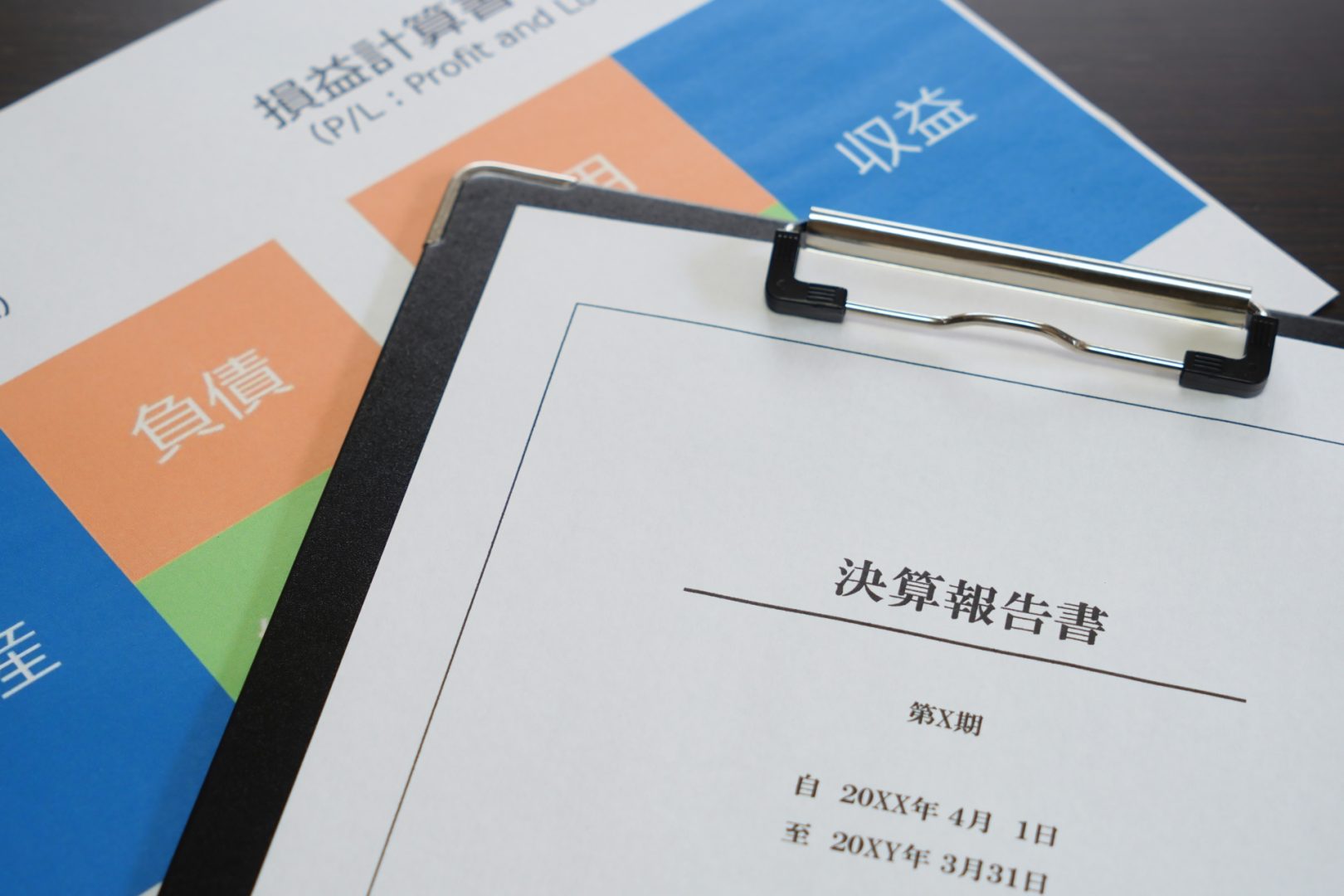
2026年3月期の業績は、売上高が前期比25.4%増の90億円、経常利益が同25.7%減の8000万円と増収減益の見通しとなっています。
導入先が増えるほど基盤利用料と取引量連動が積み上がりやすい構造となっています。
大口案件の稼働が進んだ2025年3月期に黒字転換したのがポイントです。
なお今期は、支払い税額が増加することや新規上場関連費用などの影響で、経常利益は前期比で減益の見込みとなっています。
インフキュリオンの将来性は?|市場環境は良好
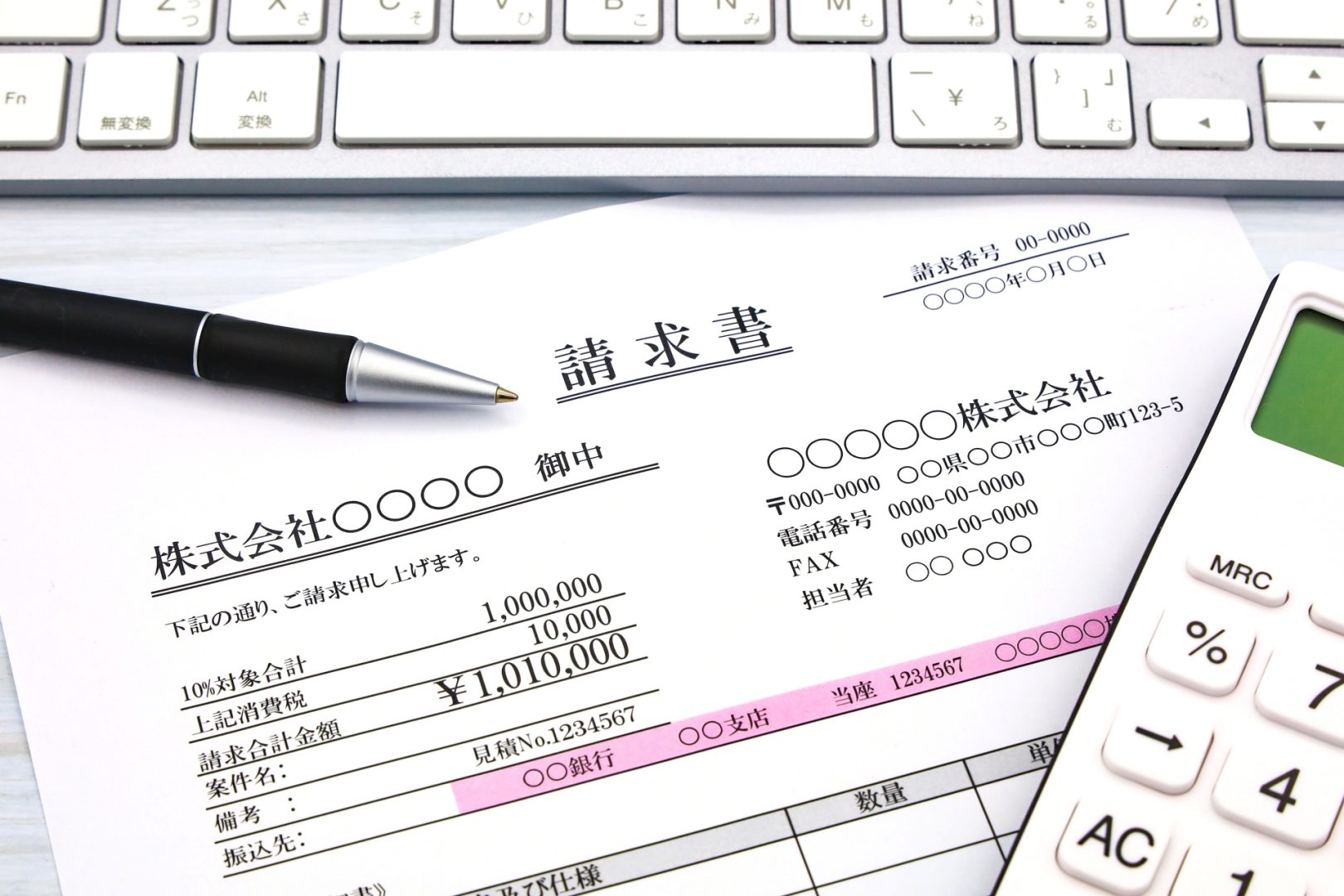
インフォキュリオンは良好なフィンテック市場の環境を追い風にしています。
日本でもキャッシュレス比率は年々上昇しています。
企業間取引ではインボイス制度・電子帳簿保存法などの制度対応が進み、紙・ハンコからデジタル請求・オンライン決済への移行が加速中です。
さらに大手・地方銀行は企業向けの非対面・API連携サービスを拡大しており、銀行機能をアプリ・SaaSに埋め込む「エンベデッド・ファイナンス」は今後も高い成長が見込まれるテーマです。
政策・規制の後押し、企業のDX投資、そして「金融をプロダクトの中に組み込む」ニーズの広がりが同社の事業ドライバーになっています。
規制による義務化を起点とした市場の成長と、DXによる効率化、さらにシステム開発の内製化が同時進行しているのが今のフィンテック市場です。
この流れは請求・決済・オンライン本人確認・与信の金融の部品化ニーズを継続的に生み、その基盤を持つ同社に追い風を与えることになります。
インフォキュリオンの強み|ワンストップでのサービス提供

市場環境は良好ですが、フィンテックは競合の多い領域です。
ここからは、ワンストップ提供・エンタープライズ実装の型・制度対応前提の設計といったインフォキュリオンの3つの強みについて解説していきます。
インフォキュリオンの競合を分析
インフォキュリオンに競合するフィンテック企業のタイプは大きく4つに分けられます。
同じ「お金まわりのDX」でも、得意分野が少しずつ違うため、具体的な企業を例に挙げながら解説していきます。
①銀行直系で金融機能を提供するビジネスモデル
銀行が自らの勘定系・口座・振込インフラをAPIで外部に開放し、企業アプリに銀行機能を組み込ませるモデルです。
金融の根幹に直接接続できる一方、審査やガバナンス要件で開発スピードは抑制されやすいです。
〈例〉
・【7163】住信SBIネット銀行
NEOBANKで提携先に口座・振込・入出金をAPI提供。BaaS型で金融機能を直結。
・【5838】楽天銀行
口座・振込・デビットをグループ横断で提供。外部サービスともAPI連携。
強み:口座・振込など銀行機能に直結できる。銀行ブランドによる高い安心感・信頼感。
弱み:開発スピードと柔軟性に限界がある。他行との連携に制約がある。
②決済代行・請求サービス提供の企業
ECやサブスクなどの標準的な「請求~決済~回収」をSaaS/ゲートウェイで短期導入するモデルです。
料金が明瞭で運用負荷が低い反面、KYCや高度与信など銀行級の機能は薄く、複雑な業務フローは苦手としています。
〈例〉
・【3769】GMOペイメントゲートウェイ
オンライン決済代行の大手。カード・コンビニ・ペイ系をワンストップで提供。
・【7383】ネットプロテクションズホールディングス
後払い決済(BtoC/BtoB)。請求〜回収をパッケージで提供。
強み:請求から決済の一点特化で導入が早い。料金体系も明瞭な傾向。運用不可の低さ。
弱み:本人確認・与信・カード発行など周辺機能の薄さ。高度な拡張でつまずきやすい点も挙げられます。
③カード発行プラットフォーム
既存のカード発行・決済基盤を活用し、プリペイド/デビット/法人カードを短期間で立ち上げるモデルです。
UX設計や権限管理を素早く形にできますが、口座連携や請求・回収など横断機能は別途実装する必要があります。
〈例〉
【8253】クレディセゾン
提携・法人カードの発行基盤。コブランドやバーチャル発行に強み。
【8585】オリエントコーポレーション(
提携発行・法人/個人カードの多様なスキームを提供。
強み:プリペイドやデビット、法人カードの立ち上げスピードが速い。
弱み:請求・回収や口座連携まで横断して揃うわけではない。口座連携・資金移動の機能不足。
④システムインテグレーター
企業ごとの要件に合わせて設計・開発し、基幹/勘定系やクラウド、API連携を含めたフルカスタムで金融機能を作り込むモデルです。
自由度と適合性は高いですが、時間とコストが大きく、共通部品が乏しいと非効率になりやすいです。
〈例〉
【9613】NTTデータグループ
勘定系・決済系・API連携の大規模構築。金融機関〜事業会社まで対応。
【3626】TIS
カード/決済/与信の専門SI。スキーム設計〜運用まで一気通貫。
強み:個社要件に合わせたフルカスタマイズ。既存基幹・勘定系との高い接続適合性
弱み:開発リードタイムの長さ、初期コストの大きさ。
インフォキュリオンの競合と比べた時の強みとは
インフォキュリオンの強みとして、まずは、最初から「請求・決済・本人確認(eKYC)・与信・送金」をひとつの土台で提供している点が挙げられます。
バラバラのサービスを後でつなぎ直す必要が少なく、導入も運用もスムーズに進みます。
もう1つは、大企業向け導入の場数です。
要件整理から試験、本番移行、監査対応までの進め方が型になっているため、手戻りや遅延を抑えやすいです。
さらに、制度対応を前提に設計しているという点も強みです。
インボイスや電帳法、オンライン本人確認、資金移動など法規制を織り込んだ設計となっており、制度変更があっても、土台を保ったまま必要な部分だけを広げられます。
競合は単機能に強みがある一方で、複雑になるほどつなぎ込みが負担になりがちです。インフォキュリオンはその“つなぎ込み”を最初からまとめて面で対応できるのが違いです。
投資家目線では、手戻りの少なさ=獲得コスト(CAC)の効率化、横断でのアップセル=単価やNRRの押し上げ、導入が早い=売上計上の前倒しにつながりやすい点が魅力です。
インフォキュリオンの株価見通し|2つの注目ポイント

ここからは、上場後にインフキュリオンの株価が上昇する可能性について、アナリスト目線で分かりやすく解説していきます。
インフキュリオンの市場での評価を考える上で、注目すべきポイントは2つあります。
ポイント①:テーマ性×実需の両立
キャッシュレス・請求書DX・金融の内製化は、政策の後押しと「生産性を上げたい」という企業ニーズが重なり、実需が強い分野です。
テーマ性で買われつつ、実際に導入・運用が進めば、受注や利用件数、継続率などの業績トレンドで評価の裏付けも取れます。
テーマで注目を集め、導入が増える→使われる→ 取引量が伸びるの順に実需が数字化していけば、テーマ性だけではなく、成長性の評価が株式市場で定着します。
ポイント②:法規制主導の追い風
日本ではここ数年、「やらざるを得ない」制度対応が一気に進みました。
これがそのまま、インフォキュリオンのサービス提供領域への強力な追い風になっています。
例えば、インボイス制度や電子帳簿保存法、犯収法のオンライン本人確認解禁など、様々な制度対応が求められています。
インフォキュリオンはこのような様々な制度を最初から前提にした設計でまとめて提供できます。
制度対応が義務化された今、対応したサービスを横断で持つ基盤が選ばれていくでしょう。
その最短ルートを提供できるのがインフォキュリオンであり、テーマ性と実需が一直線につながるのです。
インフキュリオンの注目ポイントや株価見通しについて以下の動画で詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
インフキュリオンの投資戦略と注意点

インフキュリオンに投資する際には、IPOの基本情報だけではなく、需給構造を見極めて、セカンダリー投資におけるタイミングとスタンスをどう取るかが重要となります。
ここでは、IPOの基本情報とリスク、そして実際に投資する場合の戦略について整理します。
インフキュリオンの初値&基本情報
インフキュリオンに投資する上で、まずは基本的な情報を押さえておきましょう。
公開価格:1,680円
時価総額:342億円(公開価格ベース)
主幹事:SBI証券
上場後の株価はどうなる?セカンダリー投資のポイント
上場後の株価の動きを予想する上で、「誰が株を持っているか」「今後株を売る可能性があるか」という需給バランスの見極めが重要です。
大株主にはベンチャーキャピタルが複数社確認され、売出株式比率は74.7%となっています。
公募株式数の7割以上が売出しとなりますが、事業内容や時価総額のサイズ感から初値高騰の可能性も考えておきましょう。
また、ベンチャーキャピタルへのロックアップには価格解除要項がついており、それぞれ公開価格の1.5倍、2倍となっています。
公開価格の1.5倍となる2,520円、2倍となる3,360円ではベンチャーキャピタルからの売りが警戒されるため、同価格帯をしっかりと上抜けるかに注目です。
セカンダリーを狙うならまずは、初値がついてから1.5倍ラインを超えられるかを見極めましょう。
また、初値が公開価格1,680円を超えるかには注目です。
今回の場合、投資家の注目度が高いこと、外部環境が好調なことから初値が公開価格を下回るいわゆる「公募割れ」になる可能性は低いとみています。
まとめ|テーマ性×業績拡大で評価の定着に期待!

インフォキュリオンは「請求・決済・eKYC・与信・送金」をワンストップで実装できる基盤力を武器に、政策の追い風と企業の生産性向上ニーズを実需へつなげている企業です。
上場後は、導入社数や取引高、基盤利用料の積み上がりといったKPIが株価の物差しになり、提携・受注などのニュースが需給と相まって評価を押し上げる局面が期待できます。
短期ではロックアップ価格の節目(1.5倍、2倍)を意識しつつ、出来高を伴って上抜ければ流れに乗る姿勢が現実的で、中期ではエンタープライズ案件の再現性とクロスセルによる単価上昇が持続性の鍵になります。
テーマ性だけでなく実需の数字が伴ってくれば、評価の定着とレンジ切り上げを狙える銘柄です。
アナリストが選定した銘柄が知りたい!
今なら急騰期待の“有力3銘柄”を
無料で配信いたします
買いと売りのタイミングから銘柄選びまで全て弊社にお任せください。
投資に精通したアナリストの手腕を惜しげもなくお伝えします。
弊社がご提供する銘柄の良さをまずはご実感ください。
▼プロが選んだ3銘柄を無料でご提案▼
執筆者情報
日本投資機構株式会社 投資戦略部 室長
大学時代に投資家である祖母の影響で日本株のトレーディングを始める。大学時代、アベノミクスの恩恵も受けて資金を増やすことに成功する。卒業後、証券会社、投資顧問会社を経て2019年2月より日本投資機構株式会社の分析者に就任。モメンタム分析を最も得意としており、IPO(新規上場株)やセクター分析にも長けたアナリスト。
![Invest Leaders[インベストリーダーズ]](https://jioinc.jp/investleaders/wp-content/uploads/2025/07/logo_01.png)