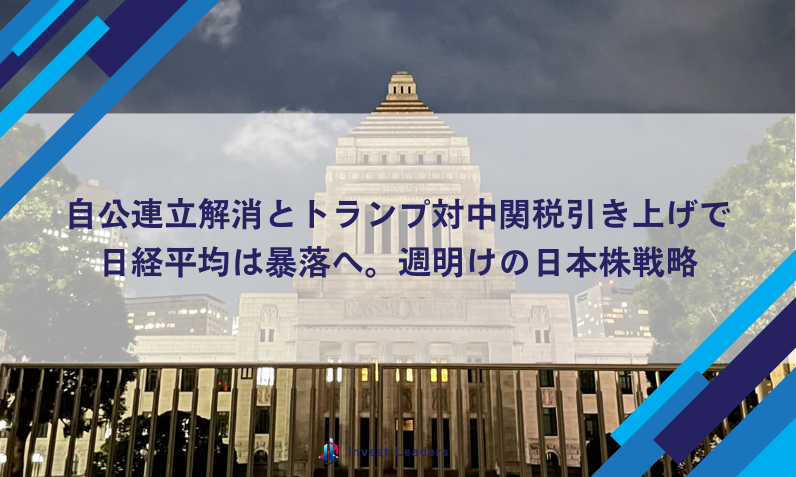10月11日(金)~13日(月)の3連休明けの日本株市場は、「自公連立解消」と「米国による対中関税引き上げ」という2つのニュースを受け、大きく値を下げて始まりそうです。
そこで本記事では、これらのニュースと株式市場の急変動をどう捉えるべきか、ポイントと具体的な投資戦略について解説します。
週明けの日経平均株価は3,000円安か

※TradingViewより引用
日経平均先物は、10月10日(金)の大引け後に自公連立解消のニュースが伝わると下げ幅を拡大。
その後、NY時間にトランプ米大統領がSNSに対中関税の引き上げと米中首脳会談の中止を示唆する投稿をしたことで、さらに下値を模索しています。
10日(金)における大阪取引所ナイトセッションの日経平均先物の終値は4万5,200円となっており、同日の日経平均株価の終値(4万8,088円)と比較すると、2,800円超下落しています。
日本株市場が祝日で休場となる13日(月)の米国株式市場がさらに下値を模索した場合、3連休明けの日経平均株価は3,000円を超える値下がりで始まる可能性が想定されます。
ただし現時点では、私はこの下落は直近の株高に対する「揺り戻し」の範囲内だと考えています。
短期的には混乱が続く可能性が高いですが、株価は10月後半にはボトムをつけて、再度年末に向けて上昇するというのがメインシナリオです。
なぜなら、下落の要因になった「自公連立解消」と「トランプ氏による対中関税引き上げ投稿」は長期的な株高シナリオを否定する材料ではないと考えられるからです。
それぞれの材料について詳しく見ていきましょう。
自公連立解消で混乱も、長期的な財政拡張路線は不変か

自民党総裁選での高市氏の勝利を受けて、アベノミクスの継承者ともされる同氏が掲げる積極的な財政政策が日本経済を活性化させるとの期待が高まっていました。
「高市ラリー」とも呼ばれる株高と円安進行が加速し、日経平均株価は10月9日(木)に市場最高値である4万8,597円をつけています。
しかし、公明党の連立離脱を受けて、衆参両院での過半数確保がさらに困難になり、高市氏の掲げる政策はなかなか実現しないのではないかという見方が出ています。
政権交代が現実味を帯びる
さらに、今月20日もしくは21日に行われるとみられている首相指名選挙で、高市氏が指名されず、政権が交代する可能性まで浮上しています。
首相指名選挙では、1回目の投票で過半数の票を獲得する議員がいない場合、上位2人による決選投票が行われます。
公明党が連立から離脱した今、1回目の投票で高市氏が過半数を獲得するのは困難で、決選投票にもつれ込む可能性が高まっているのです。
この場合に、公明党が高市氏に投票せず、斎藤代表の名前を書くなどした際には、公明党票は無効となります。
こうなると高市氏が決選投票で見込める得票数は自民党の197票で、立憲民主党(149票)と日本維新の会(35票)、国民民主党(27票)が協調して同じ候補に投票した場合などには、高市氏は決選投票で勝てず、政権が交代すると考えられます。
首相指名選挙の結果を受けた株式市場の反応は?
政権交代の可能性は高くはないものの、無視はできないテールリスクになりつつあります。
そのため、20日もしくは21日に行われる首相指名選挙は、非常に注目度の高いイベントとなるでしょう。
本記事でも、首相指名選挙の結果を受けた株式市場の展開を整理しておきたいと思います。
政権交代が起きれば市場はトリプル安で反応か
もし政権交代が起きれば、サプライズとなり株式市場は売りで反応するとみられます。
政治の混乱が長期化するとの見方が広がるほか、野党に政策運営ができるのかという警戒感が高まりそうです。
ただし、野党の多くが減税などを掲げているため、長期的に日本が積極的な財政政策に傾いていく可能性も高まります。
過度の積極財政を織り込む動きとなれば、財政悪化への警戒感から円安、株安、債券安の「日本売り」とも言えるようなトリプル安が発生し、市場のボラティリティが非常に高くなると思われます。
一方で、長期的には、積極的な財政出動でインフレ率が高まり、株高基調が継続すると考えられます。
この場合には、円(現金)の価値が下落し、相対的な株高が進むイメージを持っておくと良いでしょう。
高市氏が指名された場合も短期的には弱含み
首相指名選挙で高市氏が指名された場合も、自公連立が解消された今、政策のスムーズな運営は困難です。
短期的には政治的な混乱が続き、株式市場でも上値の重さが続く可能性が高いでしょう。
自民党は、高市政権発足後、直ちに経済対策の策定を進め、補正予算を成立させようとしていましたが、多数派の確保に難航し、補正予算の年内成立は難しくなるとみられています。
とはいえ、野党は概ね拡張的な財政政策を掲げているため、野党と連携して高市政権が政策を進めるとしたら、やはり財政拡張的な政策になりやすいです。
この場合にも、政策の遅れを嫌気して短期的には弱い相場が続いても、積極財政を織り込む形での日本株市場の長期的な上昇は続くとみられます。
トランプ氏激怒も「TACOトレード」が有効となる可能性

続いて、もう1つの株売り材料となっている米中の関係悪化についても見ていきましょう。
中国によるレアアースの輸出規制にトランプ氏が激怒
中国商務省は9日(木)に、レアアース(希土類)の新たな輸出管理規制を発表。
レアアースを使った磁石の製造など、関連技術の輸出も規制するとしています。
これを受けて、トランプ米大統領は10日(金)の日本時間23時57分に、中国を批判する内容をSNSに投稿。
今月末の日程で調整が進んでいた中国の習近平主席との首脳会談を中止する可能性を示唆しました。
さらに、中国からアメリカ合衆国に輸入される製品に対する大幅な関税引き上げを検討していると投稿しました。
その後日本時間の11日(土)朝5時50分には、「2025年11月1日より(もしくは中国がさらなる措置・変更を行った場合にはそれ以前に)、アメリカ合衆国は現在の関税に加え、対中国に100%の追加関税を課します」「さらに同日、あらゆる重要ソフトウェアの輸出規制も実施します」などと投稿しています。
11月1日に向けて交渉が進むかが焦点に
とはいえ、トランプ氏が交渉のために強硬な発言をするのは「いつものこと」であり、どこまで実際に関税が引き上げられるかは不透明です。
TACO(Trump Always Chickens Out:トランプはいつも尻込みする)トレードなどと揶揄されてきた経験則から考えれば、土壇場で交渉がまとまり、関税の引き上げが撤回される可能性は十分に残っています。
米中の首脳会談は10月31日、11月1日に開催されるアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議に合わせて調整されていましたので、まずはこの日程に向けて交渉の行方を見極めることになりそうです。
米中首脳会談がやはり行われるとなれば、その時点で株式市場はポジティブに反応するとみられます。
今年は、相場が悲観に傾いた場面で、トランプ氏が派手な前言撤回を行い、株価が大きく戻す場面がすでに見られています。
中国の出方にも左右される部分はあるものの、同様の急反発が起こる可能性も十分に想定されるため、冷静に先行きを注視したいと思います。
目先の主要指数の下値目途を確認

以上のように、国内政治が混乱したとしても財政拡張路線は不変だとみられ、中長期的な株高期待は残ります。
また、土壇場で米中の交渉がまとまり相場が急反発する可能性も十分に想定されます。
首相指名選挙(10月20日もしくは21日)や米国による対中関税引き上げ予定日(11月1日)を通過し、不透明感が晴れれば株式市場も徐々に落ち着きを取り戻す可能性が高いでしょう。
そうであれば、今月後半にかけて、下値をどう拾うかという戦略がまずは重要になるとみられます。
そこで直近の各指数の値動きを確認し、下値目途がどの程度の価格帯になるかを考えておきたいと思います。
日経平均は4万4,000円近辺が目先の下値目途に
まず日経平均株価を見ておきましょう。
日経平均株価は、高市氏の総裁選での勝利を受けて、先物主導で上昇を加速させました。
踏み上げ相場、需給相場のような動きであったため、日経平均株価に対する寄与度の高い半導体関連株などの上昇には行き過ぎ感があったことも事実です。
そのため、これを巻き戻す形での日経平均株価の下落幅は大きくなりやすいと考えられます。
▼日経平均の動きをCFDで見ると、すでに25日移動平均線を割り込んでいます。

※TradingViewより引用
現物の日経平均株価は、週明けにギャップダウンから始まり、高市氏の勝利を受けて窓を開ける前の水準まで値を戻すとみられます。
テクニカル的には、いわゆるアイランドリバーサルのような形になるとみられ、高市トレードに乗って上値で買いを入れた投資家が、軒並み取り残されてしまいそうです。
このように、急騰後に株価が急落する「往って来い」のような値動きが発生した場合、急落前の水準を再度回復するまでには、それなりに長い、もしくは深い調整が必要になるケースが多いです。
▼そのため、まずは50日移動平均線の位置する4万4,000円近辺まで下落して、同価格帯で揉み合いながら国内政治の動向や米中協議の行方を見極める展開をメインシナリオとしておくと良いでしょう。

※TradingViewより引用
悪いニュースが投資家心理を悪化させた場合には、75日移動平均線との接近が意識される4万2,000円から43,000円程度の価格帯まで一時的に突っ込む展開も考えておきたいです。
焦らずに下落ペースが鈍化するのを待って、50日移動平均線を少し下回る水準から少しずつ押し目買いを入れるのが有効な戦略になりそうです。
財政拡張路線で円高進行は限定的か
▼自公連立解消のニュースが伝わった場面と、トランプ氏が対中関税引き上げについて投稿した場面では、いずれもドル円相場が円高方向に動きました。

※TradingViewより引用
しかし、前述のように日本政府が積極財政に傾くことを織り込む動きとなれば、中長期的に為替の円高進行は限定されるとみられます。
対ドルで考えても、円高進行が加速する可能性は限定的です。
なぜなら現時点では、今後の追加利下げについて慎重な見方を示すFRBメンバーも多く、FRBがどんどん利下げをして、日米の金利差が大幅に縮小するシナリオは描きづらいからです。
ドル円チャートを見ても、夏に1ドル=147円を挟んだもみ合いが長らく続いた後、円安方向にトレンドが発生している状況です。
円高方向に動いたとしても、同価格帯がサポートして強く意識されるでしょう。

※TradingViewより引用
円高進行が限定されれば、日本株にとっての一定の支えになるとみられます。
米国でもハイテク株の揺り戻しが継続
米主要3指数の値動きも確認しておきましょう。
▼NYダウ平均は、10月10日(金)に9月の上昇分を全て吐き出す形で大きく陰線をつけて取引を終了。

※TradingViewより引用
▼S&P500指数も同様の値動きとなっており、来週も下値を模索する展開が続きそうです。

※TradingViewより引用
▼目先は13週移動平均線の位置する水準が下げ止まりを試すポイントとなるでしょう。

※TradingViewより引用
▼ナスダック総合指数は、9月以降の上昇幅が大きかっただけに、13週線とまだ乖離が大きく、来週にかけてさらに下落幅を拡大する余地がありそうです。

※TradingViewより引用
AIブームの継続を狙って半導体株への買いを考えている方は、13週線どころで値動きが落ち着くかを確認してから買いを入れていくのが良いでしょう。
米政府閉鎖長期化が改めてリスク要因に

株価は、短期的には材料や需給で大きく乱高下しても、最終的には景気の実態や企業業績に応じた水準に落ち着いていくものです。
つまり、景気後退懸念が高まらない限りは株価が反発に向かうシナリオが描けますが、景気後退懸念が高まった場合には下落が長期化するリスクも考慮しなければなりません。
その上で注目すべきなのが、長引く米政府閉鎖が米国景気に与える影響です。
現在は、政府閉鎖の影響で、雇用統計などの一部の米経済指標が発表されておらず、景気の実態が見えづらくなっています。
そうした環境下で10月1日から始まった米政府閉鎖がじわじわと米国景気に打撃を与える可能性が懸念されるのです。
ただでさえ政府閉鎖で給与を受け取れない職員が増えている上に、トランプ米政権は10日(金)に連邦職員の大量解雇を開始したと発表。
給与の未払いや大量解雇は消費や雇用に打撃を与える可能性が高いです。
今後は雇用悪化が警戒されるなかで、その実態を政府統計で把握できないことによる不安が、金融市場で強まっていく可能性があります。
地合いが悪化すると投資家は悪い材料に目を向けやすくなります。
これまでの株高局面ではあまりリスク視されてこなかった米政府閉鎖が改めて懸念され、景気後退が意識される可能性は充分に想定されます。
米政府閉鎖が長引いた場合には、相場の回復を遅らせる要因になりやすいとして先行きを注視しておきたいです。
下落が一巡した後は企業決算が焦点に
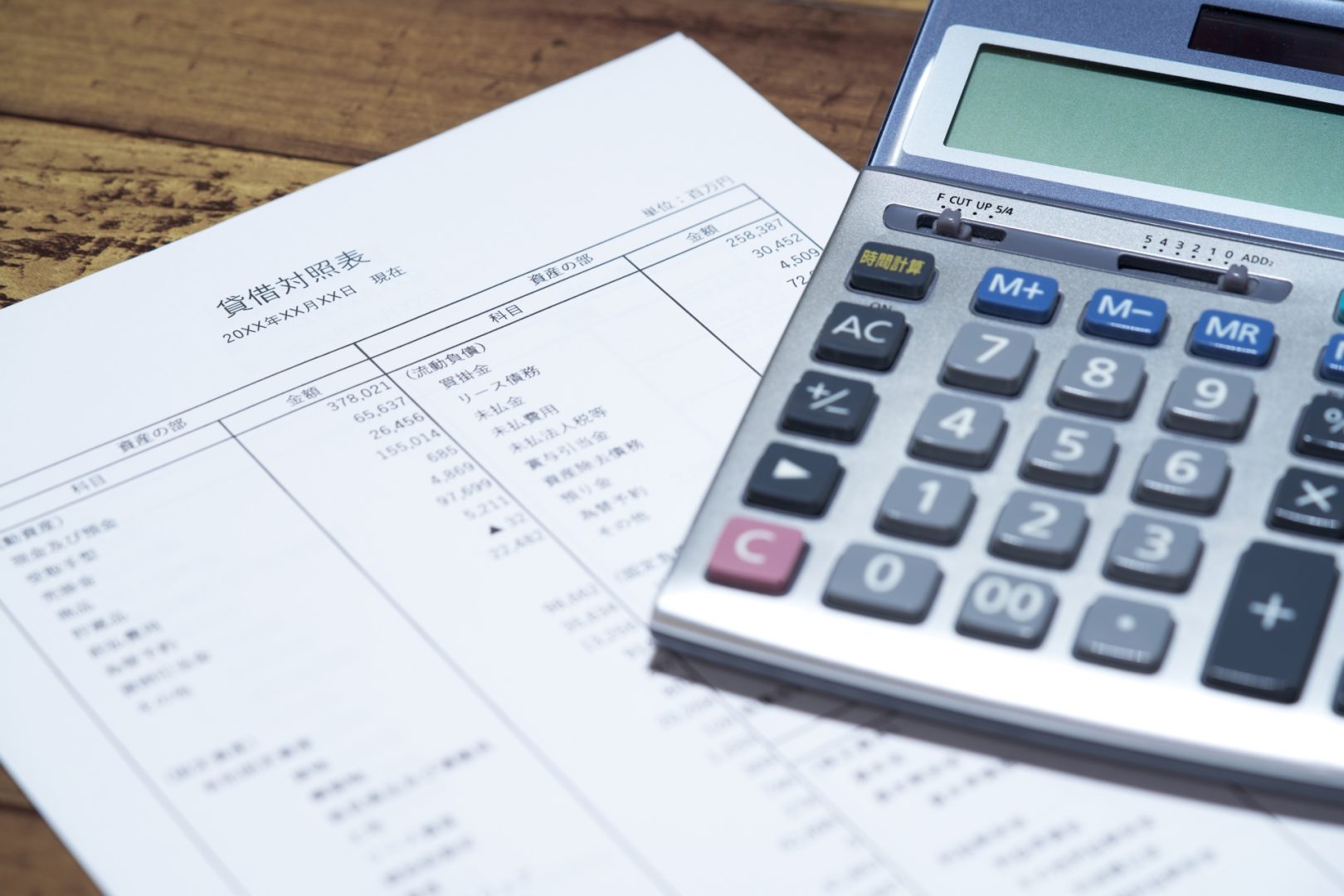
景気や企業業績に基づいた水準に株価が落ち着くという意味では、これから本格化する企業決算の発表にも注目しておきたいです。
米国では14日(火)のゴールドマン・サックスやJPモルガンなどの米金融大手を皮切りに、企業決算の発表が開始。
16日(木)には台湾の半導体大手TSMCの決算発表も控えています。
TSMCの決算は日本時間の15時と場中に発表されるため、ボラティリティが高い相場展開のなかでTSMCの決算内容を手がかりに半導体株が激しく値を動かす可能性も想定されます。
投資家心理がネガティブに傾くなかで、決算発表シーズンが始まりますので、序盤は企業からのネガティブなガイダンスに市場が過敏になりやすい時間帯が続くとみられます。
ただし、関連する企業のネガティブなガイダンスを受けて、まだ決算を発表していない他の銘柄にも過度に売りが広がるようであれば、決算発表シーズン後半にかけてはさほど業績が悪くなかった企業への見直し買いが入りやすくなるでしょう。
業績が悪くない銘柄に連想売りが出た場面が、買いのチャンスになるとみられます。
市場全体の落ち着きどころを探りながらも、決算内容を丁寧に見ていくことで、リスクを抑えながらも、今後の株価反発に乗れると考えています。
アナリストが選定した銘柄が知りたい!
今なら急騰期待の“有力3銘柄”を
無料で配信いたします
買いと売りのタイミングから銘柄選びまで全て弊社にお任せください。
投資に精通したアナリストの手腕を惜しげもなくお伝えします。
弊社がご提供する銘柄の良さをまずはご実感ください。
▼プロが選んだ3銘柄を無料でご提案▼
執筆者情報
日本投資機構株式会社 投資戦略部 主任代理/日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)/日本テクニカルアナリスト協会認定テクニカルアナリスト(CMTA®)
国内株式、海外株式、外国為替の領域で経験豊富なアナリスト・ファンドマネージャーのもと、金融市場の基礎・特徴、マクロ経済の捉え方、個別株式の分析、チャート分析、流動性分析などを学びながら、日本投資機構株式会社では唯一の女性アナリストとして登録。自身が専任するLINE公式など各コンテンツに累計7000名以上が参加。Twitterのフォロワー数も3万人を超える人気アナリスト。
![Invest Leaders[インベストリーダーズ]](https://jioinc.jp/investleaders/wp-content/uploads/2025/07/logo_01.png)