資産運用に興味はある。
けれど、最初の一歩で「とりあえず日本株かな」と考えた瞬間、あなたのリターンは限定的、いやゆっくりと目減りし始めているなんて事を考えたことはありますか?
本記事は、米国株をやるべきか迷う選択肢として扱う発想を捨て、米国株を資産形成の大前提として考えるべき理由を、できる限り平易な言葉と定量データで紹介します。
米国株は初めて
英語や為替が不安
高配当の日本株に惹かれている
という個人投資家の方は読み終えたとき、「なぜ米国株が世界標準なのか」「なぜ日本株中心はだめなのか」を、理解できるようになります。
投資を始めるなら米国株は迷う“選択肢”ではない
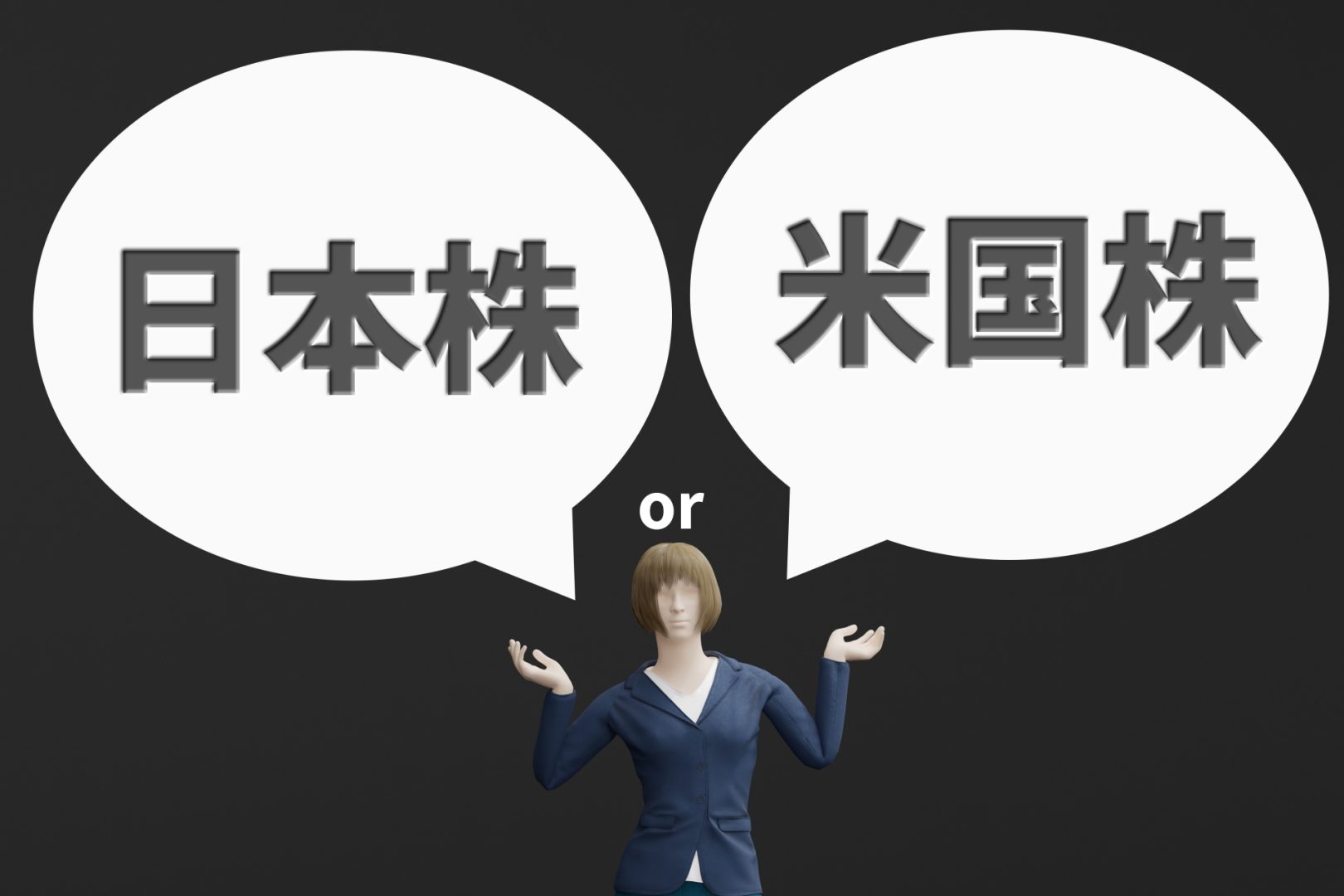
「米国株をやる理由」を探している時点で負けている
2025年8月8日の日経新聞の記事を読んで少し驚きました。
ACWI指数は世界の時価総額のおよそ85%をカバーする代表的な指数。その指数の時価総額構成比をみると、エヌビディア1社で5.1%(7月31日時点)と、日本株(4.7%)を上回っているのです。またM7全体では米国を除く日本、英国、中国など比率上位8カ国と同等の水準になっているとの内容。
エヌビディアだけ保有していれば日本株を保有するより合理的?
この数字が示す通り世界の株式時価総額の中心は米国です。MSCI ACWIの国別ウエイトで、米国は約64.9%、日本は約4.7%にすぎません(2025年7月時点)。
つまり「世界に合わせる」と、ほとんどが米国への比重になります。逆に日本株だけに投資対象を限定してしまうと、世界の株式市場の大半を自ら放棄するのに等しいのです。
ホームバイアスの罠
個人投資家は「知っている国・通貨・企業」に偏りがちです。
しかし慣れで資産配分を決めると、期待リターンを見逃したり、通貨・市場の集中リスクが同時に膨らむ可能性をはらんでいます。見える範囲、見やすい範囲だけ投資すること自体が、機会損失の源泉になりうるのです。
米国株は「選択肢」ではなく「基本」
実際のリターン比較はさらにわかりやすいです。
S&P500に連動する米国ETF(IVV)のベンチマーク10年年率リターンは13.65%(2025年6月末)。一方、日本株の代表的ベンチマークであるMSCI Japan(米ドル換算)の10年年率は約6.07%です。
長期でみれば、米国の「株主価値創造の総合力」が数字に現れています。
米国に広く安く簡単にアクセスできるという実務面の優位も見逃せません。
米国市場には多種多様なETFが上場しています。
例えばS&P500の低コストETFは経費率0.03%が一般的(VOO/IVVなど)。同じ指数に連動しつつ、スプレッドや出来高の厚みまで含めて世界最高水準の取引環境が個人にも簡単に利用可能となっているのです。
成長性・株主重視の姿勢が違う――米国株が合理的な理由

株主還元と資本効率
米国市場を語るうえで欠かせないのが株主重視の姿勢です。
米国市場では機関投資家の存在感が強く、経営はROE(自己資本利益率)・マージン(利益率)・ROIC(投下資本利益率)といった実利指標で厳しく評価され、余剰資本は配当と自社株買いで機動的に株主に還元されます。
事実、S&P500の年間自社株買いは2024年に過去最高の9,425億ドルに達し、2025年1Qは四半期で過去最高の2,935億ドルに。株主還元の規模と継続性は、米国市場そのものです。
情報面でも優位です。米国の上場企業は四半期ごとの10-Q/10-Kなどの厳格な定期開示が義務化され、重要情報の選別的開示を禁じるReg FD(フェア・ディスクロージャー)により、投資家は同時・公正な情報入手が担保されています。

もちろん日本でも2023年以降、東証が「資本コストと株価を意識した経営」を全上場企業に要請し、PBR(株価純資産倍率)1倍割れの是正を促すなど前向きな改革が進んでいます。
しかし足元の分布を見ると、プライム市場でPBR1倍を下回る企業が43%、スタンダードでは58%(2024年5月時点)。ROE8%未満の企業比率も主要先進国指数に比べ高止まりです。構造が変わりつつあるのは確かですが、「変革の途中」であることもまた事実です。
日本市場の成長限界
S&P500は採用基準が厳格で、勝者が残り敗者は抜ける入替が随時行われます。
結果として、テクノロジーやヘルスケアなど成長分野の比重が時代とともに移り、指数そのものが未来志向に調整され続けます。
一方、日経平均やTOPIXは構成の見直しが相対的に緩やかで、過去の産業構造が残りやすい。
株式投資は本来「企業の将来キャッシュフローに賭ける行動」なのに、指数の設計自体が未来志向になりにくい。ここに、長期パフォーマンスのギャップが生まれるのです。
“日本株だけ”にこだわることがリスクになる時代
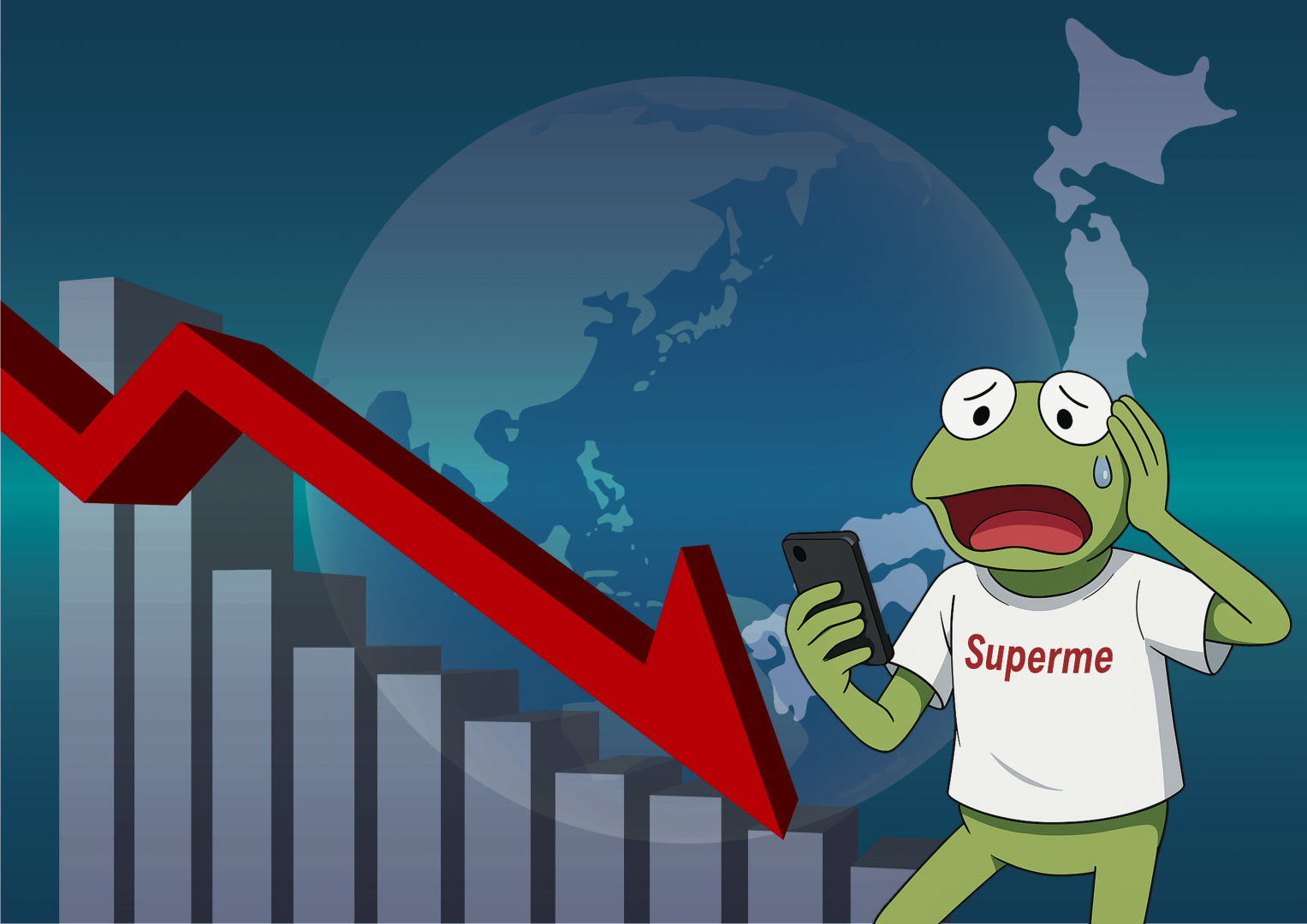
高配当の落とし穴
「日本株は高配当が魅力」という声はよく聞きます。
けれど、その配当が低成長と低ROEの裏返しであるケースは少なくありません。
成長を諦めて配当で埋め合わせる構図では、長期の資産曲線は緩やかになります。
もちろん日本株の中にも優良企業はありますが、市場全体としての設計まで含めて考えると、米国株のほうが長期パフォーマンスが優れるという前提条件が整っていると言えます。
為替リスクを避けた結果の通貨リスク
「為替が怖いから米国株は…」と円だけに寄せると、家計の資産は円の購買力に依存することになります。
2022〜2024年の1ドル160円に迫るような急速な円安局面では、円建て資産の国際的価値が大きく目減りしました。
米国株のような外貨建て資産を一定比率で持つことは、為替ヘッジであると同時に通貨分散でもあります。
率直に言えば、「日本という一つの通貨と政治・経済運営に全資産を賭ける」のは、あまりにもリスクが高いと言えます。
「知っている企業だから安心」は誤解
社名を知っていることと、事業・財務・競争力を理解していることは別物です。
名前の安心感に頼る投資ほどホームバイアスの罠に落ちやすい。市場の中心で、透明で、厳しく選別される土俵に立つ方が、長期の再現性は高まります。
初心者こそ米国株を始めるべき理由

米国株は始めるハードルが低い資産です。
国内の主要ネット証券なら1株単位で発注でき、円からでもドルからでも買えます。迷う場合は、まずS&P500連動のETFを少額で購入し、毎月の積立にしてしまうのが最短ルートです。
情報の透明性も魅力です。米国企業は四半期決算と詳細な開示が当たり前で、重要情報は同時・公正に公開されます。決算説明会の資料やカンファレンスコールの要旨は翌日に要点がまとまり、AI翻訳を使えば英語の壁は実質的にない時代です。「英語が苦手だから米国株は無理」は、もはや過去です。
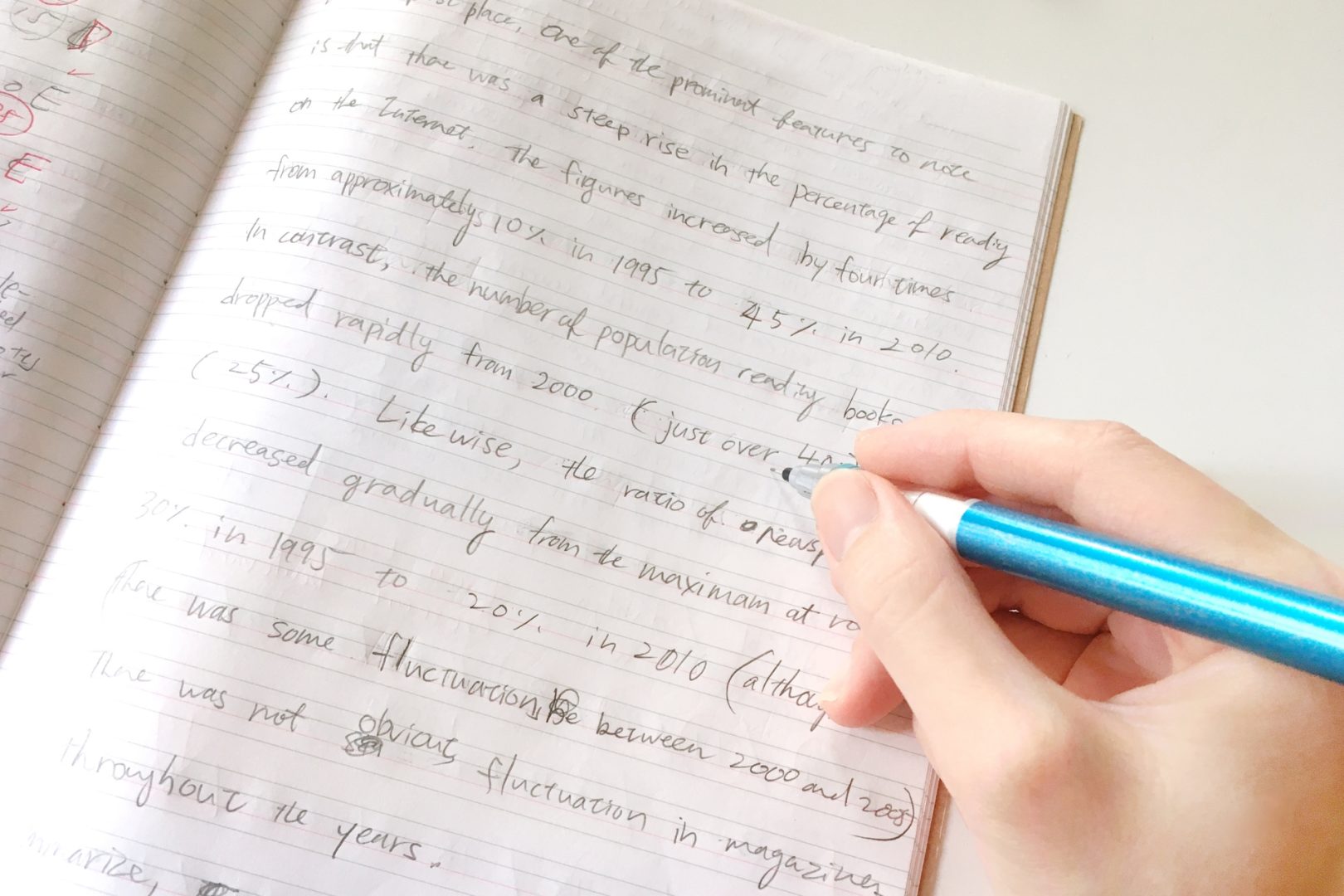
さらに米国株トレードは時差が問題になる、というのも言い訳に過ぎません。時差を武器にすることも考えてみてはいかがですか?
例えば「日本の夕方=米プレ、就寝前=寄り、早朝=引け」と分解して活かします。寄り90分だけ参加するか、夕方のプレで完結し、引けはMOC/LOCで自動化。事前にIFO+OCOやトレーリングを置き、未達はノートレ。
終値ベースのスイングやカバードコール戦略で時間価値を取りつつ、日本時間は米指数連動ETFや先物でヘッジと微調整。成行を避け、サイズとイベントをルール化し、為替ヘッジは状況に応じて使い分けることだって出来るのです。
米国株は「成長性」だけじゃなく資産防衛にもなる

米国株は「攻め」の資産であると同時に、「守り」の資産でもあります。
第一に、インフレへの耐性。グローバルに価格決定力を持つ企業が多く、売上や配当がインフレに追随しやすい収益構造が一般的です。
第二に、世界経済との連動性。S&P500の大企業は海外売上の比率が高く、日本だけが停滞しても世界の成長を反映させることができます。
第三に、長期資金のサポート。年金やファミリーオフィスといったプロが基盤資産として組み入れているからこそ、透明性・流動性・規律が維持され、家計に長期安定的な株式エクスポージャーを提供してくれるのです。
実際の投資家はどう使い分けている?

実際にはグローバル機関投資家、特にアクティブファンドはコア資産をベンチマークであるMSCI ACWIやFTSEグローバル指数に置き、必然的に米国株の中でもM7中心の大型株で運用します。
そこに小型株、日本株や新興国株をスパイスとして組み入れることで他社との差別化を図りながら円高局面はヘッジ付き、円安局面は外貨比率を高めるというポートフォリオ管理をしています。
プロ投資家は米国株を資産運用の基本として扱いグローバルな成長やイベントの収益化に遅れないよう保有し、その上に差別的な追加リターンの源泉として戦略的な投資先を積み上げています。
データで背中を押す最後の一押し
ここまで読んでもまだ米国株投資が当たり前だと考えられない方がいるかもしれません。
そんな方がいらっしゃったらもう一度これらのデータを考えてみてください。
プロの機関投資家が使う世界株式資産配分に素直に従えば、米国の比率は自動的に約65%、日本は約5%。世界の時価総額構造そのものが、リスクを軽減します。
10年というサイクルでパフォーマンスを振り返ると、S&P500は年率13%台、MSCI Japan(USD)は6%前後。指数の新陳代謝と株主重視の姿勢の差がこのパフォーマンスの差を生んでいます。
また円だけに資産を置くこと自体がリスク。2024年の160円台という歴史的な円安は、単一通貨しか持たないリスクが現実化しました。円は紙切れになるかもしれませんが、世界の基軸通貨であるドル保有はあなたの資産を守ります。
よくある不安と向き合う
「今から入るのは遅いのでは?」という不安もよく聞きます。
過去の数字が将来を保証することはありませんが(投資は自己責任・元本割れの可能性あり)、長期の好パフォーマンスは時間を味方につけるかどうかでほぼ決まります。
よほど不安な方は指数に連動する時間分散投資も検討すべきかもしれません。
価格変動のノイズを平均化しつつ、企業の稼ぐ力と株主還元を取りにいく戦略です。米国では自社株買いと配当という「株主への現金還元」が制度として整備され、それがEPSの伸びと需給の安定に結びついてきました。
その流れに乗れるかどうかはあなたがその一歩を踏み出せるかどうかにかかっています。
まとめ
世界の時価総額の中心が米国に偏っている以上、米国株はやる/やらないの議論ではありません。どれだけの比率で組み込むかを決める作業です。
株主重視の文化、厳格な開示、指数の新陳代謝という構造的追い風が、長期のパフォーマンスを押し上げます。一方、日本株だけにこだわることは、通貨と市場の二重の集中リスクを抱える選択です。
今日やることは難しくありません。米国株はおすすめではありません。やっていて当たり前というマインドに変えるべき時です。
執筆者情報
元外資系証券株式本部長マネジングディレクター
日系証券個人営業から証券人生をスタート。その後ロンドンと東京を拠点に20年以上に渡って外資系証券会社の主にトレーディングデスク及び各マネジメント職を歴任。2019年退職。得意分野はフローの裏側分析及び市場構造分析。現在はXやnoteなどで個人投資家向け株式投資の知識提供中心に悠々自適生活を送る。趣味は食とクルマ。
![Invest Leaders[インベストリーダーズ]](https://jioinc.jp/investleaders/wp-content/uploads/2025/07/logo_01.png)

