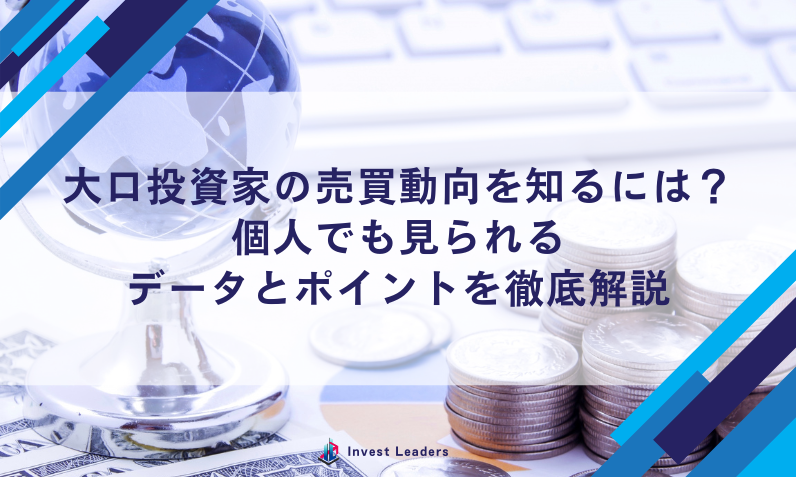日本株投資を始めるなら、個別企業の決算やニュースだけでなく、「誰がどこでどれだけ売買しているのか」という資金の流れを押さえておくと、相場観がよりクリアになります。
僕はよくフロー読みという言葉を使います。(フローは、需要・供給や資金の流れを意味します)
日本市場は、個人でもアクセス可能なフローに関する開示データが整っています。
フロー読みの精度を上げるには一定の経験が必要ですが、日々チェックすることで少しずつ相場観が養われると思います。
そこで今回は、初心者が時間をかけずにフローをチェックする方法やポイントをいくつかご紹介します。
大口投資家の動向を知る重要性

株価は「価値(バリュエーション)」と「需要・供給(フロー)」の両輪で動いていると考えます。
たとえば海外年金やヘッジファンド、国内の生保・投信・自己売買など大口といわれる需給は、指数先物や裁定取引を通じて、短期間に指数や主力株へ波及します。
材料が同じでも、フローが買い越しに傾けば上振れ、売り越しなら下振れしやすい。
このトレンドをいち早く察知し捉えるのが、無理のないエントリー/エグジットにつながると考えています。
相場全体のフローを読むために見るべき開示データ

ここからは、個人でもアクセス可能な相場全体のフローを読むために見るべき開示データの概要と、入手先やポイントを解説していきます。
投資部門別売買状況とは?|海外投資家の売買差額に注目
投資部門別売買状況とは、東証が週次で公表する、投資家区分(海外投資家、個人、信託銀行、自己など)別の売買代金・売買差額です。
直近1週間の“誰が買って誰が売ったか”が一目で分かります。
【入手先】
JPX(日本取引所グループ)が公式サイトで、「週間・投資部門別売買状況」として公表しています。
公表は通常毎週第4営業日(祝日が無ければ木曜日)の15:30頃です。
※URL:
週間 | 株式 | 投資部門別売買状況 | 日本取引所グループ
https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/investor-type/
【ポイント】
海外投資家の売買差額(買い越し/売り越し)は日経平均・TOPIXの方向性と相関が高い傾向があります。
海外が順張り、個人が逆張り、自己(証券会社勘定)が裁定・先物ヘッジの影響を受けやすい点も合わせて見ると、週明けの地合いを推測しやすくなります。
対外及び対内証券売買契約等の状況とは?|中期トレンドと整合的
対外及び対内証券売買契約等の状況とは、財務省が週次で公表する資金の出入りに関する統計です。
外国人による日本株・日本債の売買(対内)と、国内投資家による海外証券の売買(対外)のネットフロー(取得と処分どちらが多いか)が分かります。
【入手先】
「対外及び対内証券売買契約等の状況」は 財務省が週次で発表しており、公表スケジュールも別ページで案内しています。
※URL:
統計表一覧(対外及び対内証券売買契約等の状況)
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/itn_transactions_in_securities/data.htm
対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関ベース)公表予定(週次・月次)
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/itn_transactions_in_securities/schedule.htm
【ポイント】
「外国人の日本株の取得超(+)/処分超(-)」をまず確認しましょう。
足元で取得超(+)が続けば買い圧力が効いている可能性があります。
月次・四半期のトレンド化もセットで追うと、指数の中期トレンドと整合が取れます。
先物・オプションの動向も参考に|SQ前には指数を動かすことも
デリバティブ市場(先物・オプション)は、裁定(同じ価値を持つ商品の価格差を利用した取引)とヘッジ(リスク回避目的の売買)を通じて現物に影響を与えます。
建玉(オープン・インタレスト)や投資部門別の売買、行使価格別の集中度は、市場参加者のポジションの偏りや将来の価格変動に対する期待を測るのに役立ちます。
【入手先】
日本取引所グループ(JPX)が週次で公表している「先物・オプション:投資部門別取引状況」「取引参加者別建玉」や、日次で公表される「大阪取引所/東京商品取引所日報」が参考になります。
※URL:
週間 | 投資部門別取引状況 | 統計情報(先物・オプション関連) | 日本取引所グループ
https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-derivatives/sector/index.html
取引参加者別建玉残高一覧 | 先物・オプション | 日本取引所グループ
https://www.jpx.co.jp/markets/derivatives/open-interest/
大阪取引所/東京商品取引所日報 | 日本取引所グループ
https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-derivatives/daily/index.html
【ポイント】
満期(SQ)前はガンマの偏りで指数が動くことがあり、イベント週のボラティリティは高まりやすいです。
また、プット・コールレシオ(オプション取引のプット(売る権利)とコール(買う権利)の比率から計算される指標)などのセンチメント指標も補助線としても有効です。
裁定取引残高・プログラム売買|需給の強さを確認!
現物と先物のスプレッド(価格差)を利用した裁定の買い残/売り残は、需給の強さを示します。
買い残が膨らむと、相場反落時に外れる(解消される)圧力が高まる傾向があります。
【入手先】
日本取引所グループ(JPX)が「プログラム売買・裁定取引」を週次で公表しています。
※URL:
プログラム売買 | プログラム売買・裁定取引 | 日本取引所グループ
https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/program/01.html
【ポイント】
短期のトレンド局面では買い残の積み増し、調整局面では解消増が出やすいなど、週次での転換点をメモして、指数のモメンタムと重ねて確認しましょう。
大口投資家の個別株ポジションを知るには?

個別銘柄の売買を行う際にも、大口投資家のポジションを知ることは重要です。
ここからは個別銘柄の売買を行う際に参考となる開示データを紹介します。
大口投資家の空売り残高の見方|イベントと組み合わせてチェック
一定以上(0.5%)の空売りポジションを保有する投資家は、残高と増減を当局に報告しており、東証サイトで銘柄別に開示されます。
加えて、市場全体の空売り比率(日次集計)も公開されています。
【入手先】
日本取引所グループ(JPX)が毎営業日17時を目処に「空売りの残高に関する情報(0.5%以上)」として公表しています。
また、市場全体については「空売り集計(日次)」が公表されています。
※URL:
空売り残高 | 空売りの残高に関する情報 | 日本取引所グループ
https://www.jpx.co.jp/markets/public/short-selling/
【ポイント】
①残高が新規に開示ライン(0.5%)を超えた、②短期間で段階的に積み上がった、③上昇局面でも残高が減らないなど、これら3点は需給上の厚みを示唆しています。
ただし悪材料の先回り(ヘッジ)も多いため、決算やイベントと組み合わせて解消されるタイミングを同時に考えるとより実戦的です。
信用・貸借データを合わせて読む|需給の傾向を測る基本指標
東証の信用残(制度・一般)と、日証金(日本証券金融)の貸借取引残高は、個別の短期需給の傾向を測る基本指標です。
一般的に、買い残が膨らみすぎると上値が重くなり、貸株超過や逆日歩の常態化は需給逼迫を示します。
【入手先】
日本取引所グループ(JPX)が「信用取引残高等」を毎営業日16時を目処に、日証金(日本証券金融)は日次で「銘柄別残高一覧」や「品貸料率」を公表しています。
※URL:
個別銘柄信用取引残高表 | 信用取引残高等 | 日本取引所グループ
https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/margin/index.html
DATA | 日本証券金融株式会社 | 貸借取引情報
https://www.taisyaku.jp/download/
【ポイント】
信用買い残が高水準かつ株価が伸び悩む場合は、解消売りに警戒が必要です。
逆に、売り残が多い銘柄がポジティブ材料で上放れると踏み上げが起きやすく、短期の値幅が出ます(品貸料率の高止まりは需給ひっ迫のサイン)。
大量保有報告を参考にする際のポイントは?
いわゆる5%ルール。上場株の保有割合が5%を超えた投資家はEDINETで「大量保有報告書」を提出し、以後1%以上の増減等で「変更報告書」を提出します。
目的(純投資/経営参加)やデリバティブの使い方、保有主体の内訳は、個別の中期ストーリーを読む強力なヒントになります。
【入手先】
金融庁が運営するEDINET(Electronic Disclosure for Investors’ Network:金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)や各財務局のページで確認できます。
現行の提出期限は報告義務発生日の翌日から起算して5営業日以内です。
※URL:
EDINET
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/week0010.aspx
【ポイント】
提出は事後(最長5営業日)なので、短期売買のタイミング指標ではなく資本異動の足跡として使いましょう。
また、デリバティブ・貸株・共同保有の扱いは注記まで丁寧に読む必要があります。
制度は2024年の法改正を受けて記載の明確化等が順次進む見込みですので、将来の運用変更に注意してください。
実践編|大口投資家の動向を掴むにはいつどのデータを見るべき?

ここまで紹介したデータのチェックを、個人投資家でも実践しやすいルーティンに落とし込んでみました。
まずは以下の手順で、データを習慣的に見てみてください。
1、週次(木・金)
東証「投資部門別売買動向」で海外・個人の売買差額をチェックし、財務省の対外対内フローと突き合わせて外需/内需の傾向をメモ。裁定残の増減も確認。
2、日次
空売り比率(日次集計)と、気になる銘柄の空売り残高更新を確認。
信用残・日証金データで踏み/投げの兆候を探す。
3、個別材料発生時
EDINETで大量保有(新規/変更)を検索。
目的とコメント、デリバティブの内訳まで読み、値動きがフローによるものかバリュエーションなのかを判断。
フローの読み方のコツをプロが解説!

開示データをもとにフローを読む上では、以下の点に注意が必要です。
ラグを理解する
週次データは数営業日遅れて出ます。
価格は先に動き、データは後から確証を与える答え合わせと割り切ると、高値掴みや安値売りをせずに済みます。
データを組み合わせる
たとえば、対外対内で外国人の株式が取得超→東証の投資部門別でも海外が買い越し→裁定買い残が増加、の3点がそろうと、トレンドの信頼度はグッと上がります。
季節性を意識する
決算期、配当・権利落ち、指数入替、SQ週など、定期イベントはフローの癖が出やすい場面です。
スケジュールを管理しておくと、ノイズに振り回されにくくなります(SQや最終取引日の基礎は取引所のルール要綱で確認可能です)。
最後に|フローは追い風を探すコンパス

フローは未来を完璧に当てる水晶玉にはなりませんが、値動きの癖を理解し、無駄を避ける強力なコンパスになります。
最初は「海外投資家の買い越しが続く→主力株の押し目は強気」「空売り残高が急増→決算やイベントまで触らない」など、単純なルールで十分です。
公式データに沿って観察を続ければ、フロー読みの解像度は必ず上がります。
ポジティブに、そしてルールに則ったフローを見る目を、今日から育てていきましょう。
執筆者情報
元外資系証券株式本部長マネジングディレクター
日系証券個人営業から証券人生をスタート。その後ロンドンと東京を拠点に20年以上に渡って外資系証券会社の主にトレーディングデスク及び各マネジメント職を歴任。2019年退職。得意分野はフローの裏側分析及び市場構造分析。現在はXやnoteなどで個人投資家向け株式投資の知識提供中心に悠々自適生活を送る。趣味は食とクルマ。

![Invest Leaders[インベストリーダーズ]](https://jioinc.jp/investleaders/wp-content/uploads/2025/07/logo_01.png)