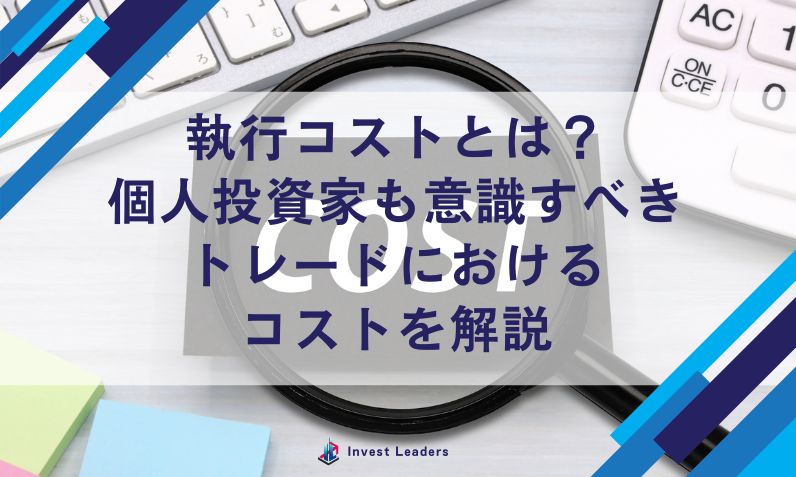執行コストとは、売買注文を市場で実行する際にかかっているコストを指します。
具体的には、スリッページ(思った価格で約定しない差)やスプレッド(買値と売値の差)、マーケットインパクト(自分の注文が市場価格に与える影響)、手数料などをすべて含んだトレードの実質コストのことです。
実際のトレードでは、表面上の売買手数料より、執行コストの方がリターンに大きく影響を与える場合がよくあります。
個人投資家の多くはここを軽視しがちですが、本当にもったいない部分です。
そこで本記事では、プロの投資家が執行のクオリティを上げるために、どのように取引を行っているのかを解説します。
プロが重要視する執行クオリティとは?

「執行クオリティ」という言葉は、初心者個人投資家にとっては少し聞き慣れない表現かもしれません。
執行なんて買いか売り、成り行きか指値しかないじゃん!と思われるかもしれませんね。
執行クオリティとは、執行の仕方の質(クオリティ)のことです。
実はこの言葉の中には、投資パフォーマンスを左右する重要なポイントが隠されています。
証券会社やバイサイドトレーダーなら間違いなくこの執行クオリティを重要視しています。
多くの個人投資家が注目するのは「どの銘柄を買うか」ですが、実際のリターンを決めているのは、しばしば「どのように買うか」、そして「いつ約定させるか」という執行のところなのです。
わずかなスリッページやタイミングのずれが、気づかないうちに長期的なリターンに差を生み出します。
個人投資家の方でも、デイトレードをやっている方はトータルの約定代金も増えるでしょうし、ちりつもですから知っておくべきことです。
なぜ執行クオリティがアルファになるのか?

よくアルファ(超過利益)創出なんてことが書かれていますが、大体の場合それは銘柄選択によるアルファ創出についてです。
しかし、今回はトレーディングアルファ創出について書いています。
執行クオリティがトレーディングアルファを生み出す理由は、取引に伴う見えないコストが無視できないほど大きいからです。
一般個人投資家レベルだと、なかなかそのインパクトは分かりにくいかもしれませんが、機関投資家サイズだとそのコストはパフォーマンスに直接影響を与えます。
スリッページ、マーケットインパクト、手数料やスプレッド…
これらを積み上げると、ファクター投資や銘柄選択に匹敵するインパクトを持つこともあります。
また、AIやアルゴリズム取引の普及により、情報や分析の優位性は急速に縮小しています。
そんな中で残るのは、市場構造(マイクロストラクチャ)を理解しているかどうかという点です。
執行クオリティを高めるには市場の仕組みの理解が必須

執行クオリティを高めるには、まず市場の仕組みを理解することが不可欠。
たとえば、東京証券取引所では寄り付きや引けにすべての注文を板寄せして清算するオークションという方式がとられています。
このオークションの時間帯には流動性が集中し、大口注文を低コストで約定しやすくなります。
一方、ザラ場で行われる取引では、価格優先・時間優先のキュー(順番)やティックサイズ(価格が動く最小単位)が約定の有利不利を生み出します。
ティックサイズが大きい銘柄では、値段を細かくきざんで指値を出すことができません。
そのため、時間優先をいかに確保するか、つまりいかに早く注文を出すかが重要です。
また、ETF(上場投資信託)やブロック取引(証券会社を通じて大量に相対取引で売却または購入する取引)ではRFQ(Request for Quote)という仕組みが用いられます。
証券会社のディーラーが売買を希望する銘柄・数量等をリクエストし、多数のマーケットメーカーに打診することで、個別に提示された価格で売買ができる仕組みです。
板に現れない隠れた流動性を活用でき、結果として執行コストを抑えられます。
[関連]株の板情報の見方完全版|プロのアナリストが初心者向けにわかりやすく解説
時間ごとの執行クオリティを高める戦略

執行クオリティは「いつ注文を出すか」でも大きく変わります。
寄り付き直後の15分は前日の欧米市場の動き、ニュースやその他株価に影響を与えそうな情報を価格に織り込むので、ボラティリティが高くなります。
成行注文を多用する戦略、例えばISや出来高追随型アルゴなどが多用されスプレッドが広がる傾向があります。
指値や分割した注文で慎重に攻めたい時間帯です。
日中(11時〜14時半)は板が薄くなりやすく、VWAP(出来高加重平均価格)やTWAP(時間加重平均価格)を使った分割発注が有効です。
そして引け前30分は、クロージングオークションの流動性が高まるため、執行クオリティを最大化できるチャンスでもあります。
また、決算やリバランスなどのイベント時には、「どこで流動性が出るか」を事前に予見することが重要です。
一発で約定させるよりも、時間と場所をコントロールする方が、より良い価格を実現できます。
シーンごとに最適な発注方法を選ぶ
市場が落ち着いている通常日には、Iceberg(小口×多回数)戦略が有効。
小さく分けて発注し、マーケットインパクトを抑えることができます。
逆に、流動性が集中する寄りや引けではオークションに集約する戦略が有効です。
特に大型株やETFでは、引け成行(MOC)を活用することで執行コストを大幅に減らすことができます。
さらに、RFQや相対取引を利用すれば、板には見えないブロックの流動性にアクセスできます。
ETFや閑散時間帯での執行改善に特に効果的です。
日本市場特有のポイント|引け成行とティックサイズ変更

日本市場では、引け成行の流動性をうまく活用することが重要です。
リバランス日や決算集中日には引けにかけて板が厚くなり、スプレッドも縮小します。
もちろん引けオークション内のボリュームも多いです。
このタイミングを狙えば、執行クオリティを高めることができます。
また、単元未満株(Odd-lot)は価格形成から外れやすく、想定以上に約定コストが高くなる場合があります。
夜間PTS取引や立会外取引は、情報漏洩リスクを抑えながら価格改善を狙う方法として有効です。
ティックサイズも無視できません。ティックが小さくなることでスプレッドは狭くなりますが、板が薄くなりやすくなるため、指値位置と待機時間の最適化が必要になります。
まさにアルゴリズム取引手段がないと太刀打ちできません。
執行クオリティを計測する重要性
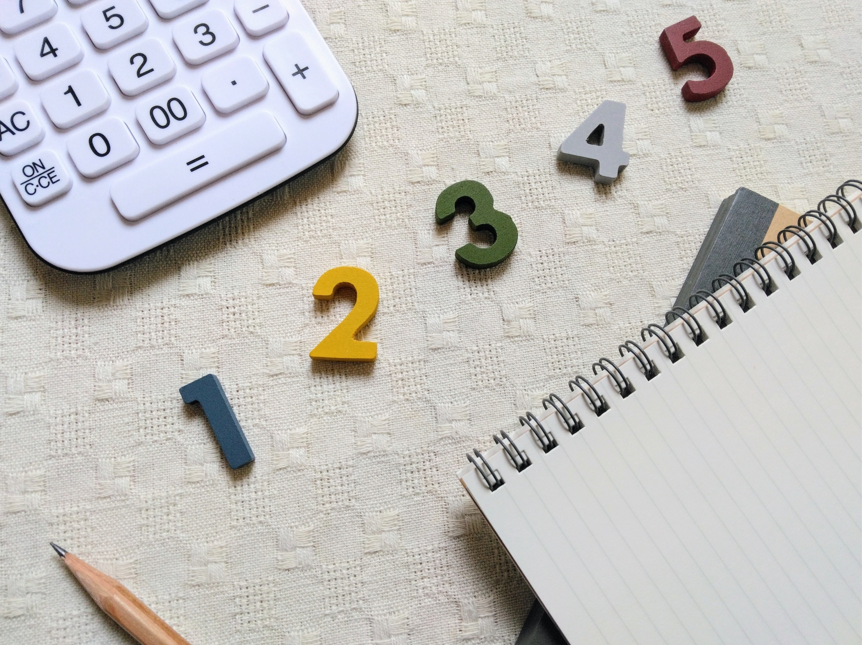
執行クオリティ改善の第一歩は「計測」することです。
実効スプレッド(約定価格と中間気配の差をbps換算)を日々記録することで、自分の執行コストを可視化できるようになります。
実現VWAPと市場VWAPの比較も有効です。自分の取引が市場平均より有利かどうかを確認し、戦略の妥当性を検証できます。
さらに、マーケットインパクトを推定するには、発注開始から終了までの相対リターンをロットで加重します。
出来高関与率が基本的にマーケットインパクトを決定します。
もし発注後に同方向の値動きが異常に続く場合は、情報漏洩が発生している可能性を疑ってよいです。
もしくはご自身がそのフローに乗っている可能性も個人投資家ではあるかもしれません。
個人投資家でもできる簡単な検証のすすめ
個人投資家でも執行クオリティを磨く方法はあります。
たとえば、同じ銘柄で「時間分散」と「オークションのみ」を交互に行い、VWAPを比較してみる。
ETFでは、成り行きとRFQの価格差を記録して、どちらが効率的かを検証する。
ティックサイズが異なる銘柄で指値約定率を比べるのも良い訓練です。
小さな実験の積み重ねが、執行感覚を大きく変えます。
よくあるもったいないコスト

寄り付き直後の成行連打は典型的な失敗です。
板が薄いため、実効スプレッドが広がりコストが悪化します。
中型銘柄での一括発注も同様で、価格を押し上げてしまいVWAPを悪化させます。
また、最良気配の内側に指値を置けない銘柄で中途半端な価格に注文を出すと、時間優先を取れず約定が遅れます。
さらに、サイズ次第では指値注文がシグナリングリスクになるかもしれません。
指数連動フローが多い日にザラ場時間分散取引するより、引けで執行した方が低コストになることも多いのです。
まとめ|「トレードの仕方」がリターンを変える
執行クオリティとは、見えないコストを意識的に測り、継続的に改善するプロセスです。
銘柄選択やマクロ分析と同じように、投資家の力量を決める重要な技術です。
日々の取引で「どう買うか」を意識するだけで、リターンの積み上げ方が変わっていきます。
派手な戦略よりも、地道な観察と微調整の積み重ねこそが真のアルファを生みます。
スプレッドを記録し、VWAPを比較し、トレードスケジュールやトレード戦略を見直す。
その繰り返しの先に、こつこつと静かに積み上がるトレーディングアルファが待っているのです。

執筆者情報
元外資系証券株式本部長マネジングディレクター
日系証券個人営業から証券人生をスタート。その後ロンドンと東京を拠点に20年以上に渡って外資系証券会社の主にトレーディングデスク及び各マネジメント職を歴任。2019年退職。得意分野はフローの裏側分析及び市場構造分析。現在はXやnoteなどで個人投資家向け株式投資の知識提供中心に悠々自適生活を送る。趣味は食とクルマ。

![Invest Leaders[インベストリーダーズ]](https://jioinc.jp/investleaders/wp-content/uploads/2025/07/logo_01.png)