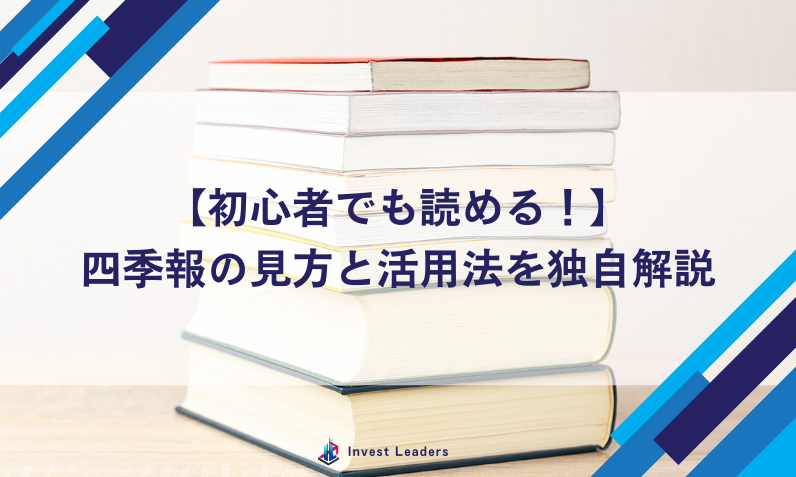株式投資を始めたばかりの方にとって、「会社四季報」はハードルが高く感じるかもしれません。しかし、実は投資の地図帳とも呼べる存在で、使いこなせば銘柄選定の力強い武器になります。
本記事では、初心者向けに四季報の読み方や活用法を徹底解説。目的別にどう読むか、Webとの違い、スクリーニング機能まで、本当に使える情報をまとめました。
これを読めば、四季報で「宝の山」を掘り出す第一歩が踏み出せます。
会社四季報は日本の上場企業情報を網羅したデータブック
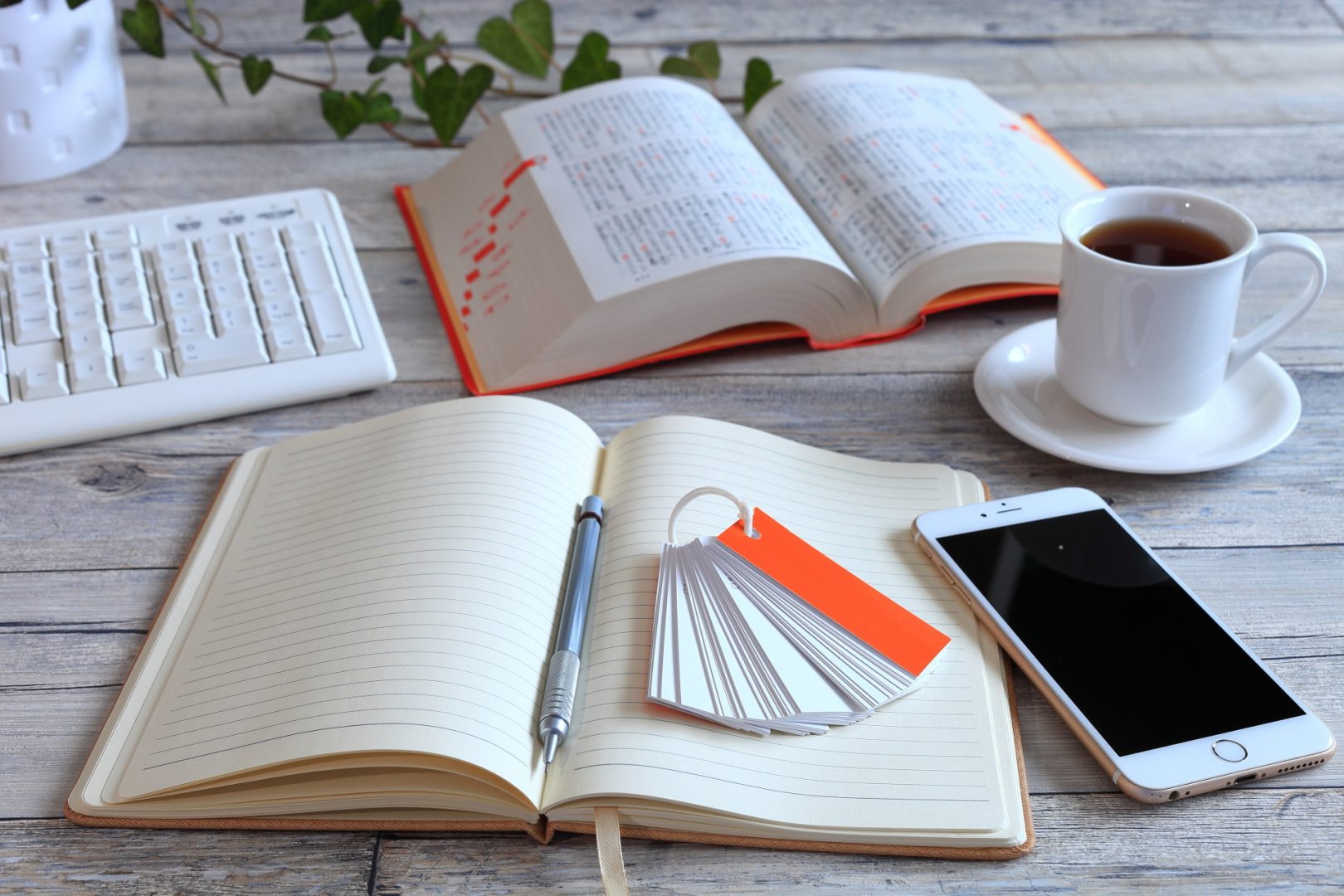
全上場企業3,800社超の情報がコンパクトにまとめられており、投資家・アナリスト・企業関係者にとっても参考になるものとなっています。
紙とWebでは掲載情報の深さや検索性が異なります。
紙は一覧性に優れ、Webは検索やスクリーニングが可能という特長があります。
四季報の歴史と信頼性
1936年に創刊されて以来、毎年4回発行(戦中・戦後の混乱期を除く)し続けてきた「株式投資のバイブル」とも呼ばれる会社四季報。
四季報の情報は企業から直接入手したデータだけでなく、業界担当記者が行った独自取材と分析に基づいているため、株価動向の分析や投資判断に高い信頼性を誇ります。
長年の実績と徹底した情報収集により、個人投資家から機関投資家まで幅広く利用される、日本株投資に欠かせないツールとしての地位を確立しています。
四季報、各号の特徴一覧
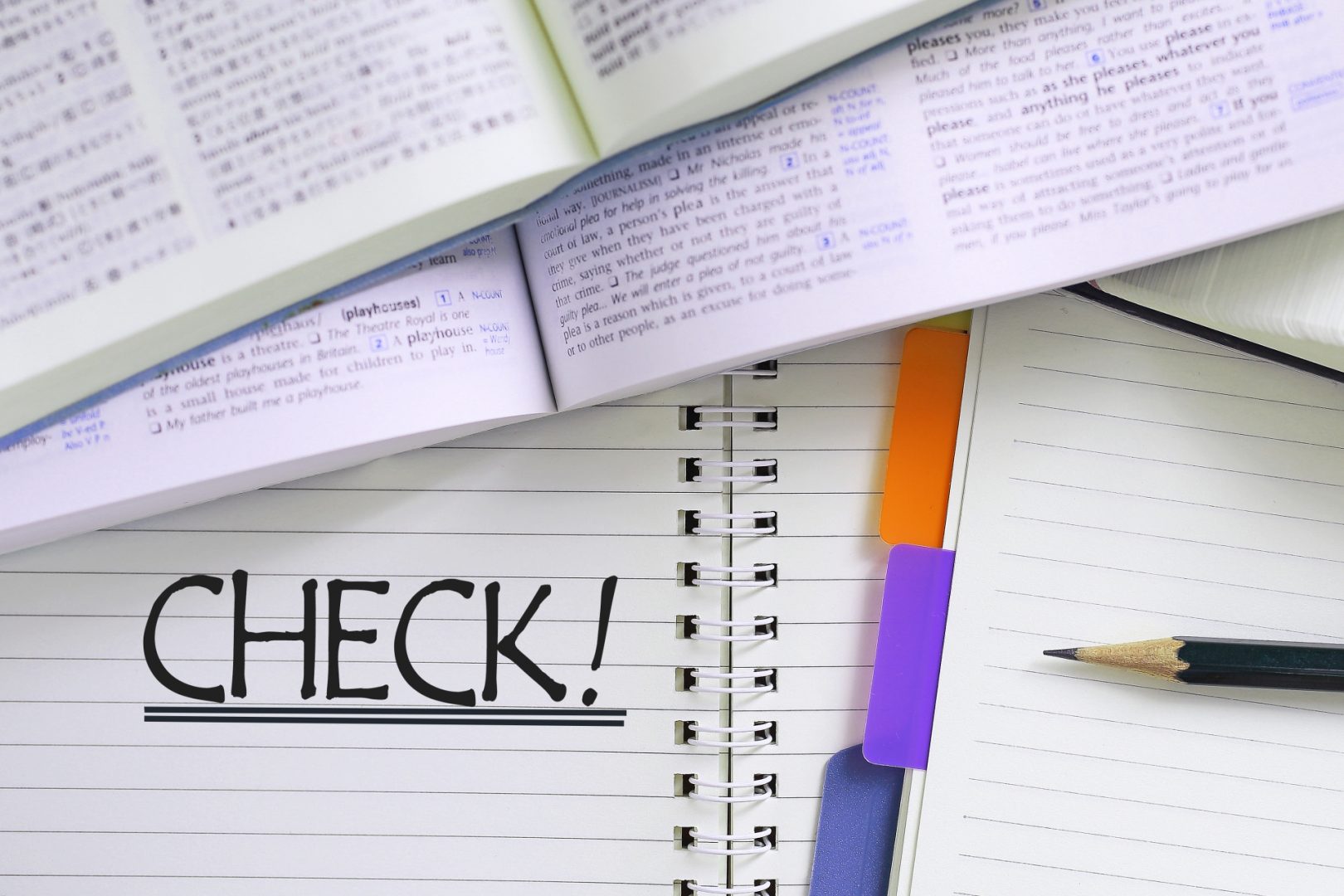
春号(3月中旬発売)|新年度の予想を初掲載!企業戦略の方向性が見える
企業にとって新たな1年がスタートするタイミングであり、来期(これから始まる会計年度)の業績予想や、事業の方向性が初めて掲載されます。
とくに「今期はどんな戦略で売上や利益を伸ばしていくか?」といったコメントが反映されやすく、企業の成長シナリオを先取りするのに役立ちます。
夏号(6月中旬発売)|1Q業績などを受けて、初回予想の修正が多い
春号で出された予想に対して、最初の見直しが行われやすいのがこの夏号。すでに4~6月期の業績速報も出てくる時期なので、現実とのズレが修正されることがあります。
初動の業績トレンドや、当初の会社方針にブレがないかをチェックするのに適しています。
秋号(9月中旬発売)|中間決算直前!下期見通しや業績修正リスクを反映
半年間の実績がある程度出そろい、「このままいけばどうなるか?」という通期予想の精度も高まる時期です。
ここで業績の下方修正が入る企業も出てくるため、「業績に暗雲がある会社を避ける」ための参考にもなります。反対に、強気な修正が出た銘柄は再注目のチャンスとなることもあります。
新春号(12月中旬発売)|通期業績が固まりつつあり、来期のヒントが出始める
3月決算企業では、通期の8~9割の実績が見えてくる時期です。そのため、会社側のコメントから「来期の見通し」や「新事業の方向性」がうっすら現れてくるのが特徴です。
また、年末年始にじっくり銘柄研究をする人が多いため、この時期に注目されやすい号でもあります。
会社四季報は紙とWebで用途が変わる
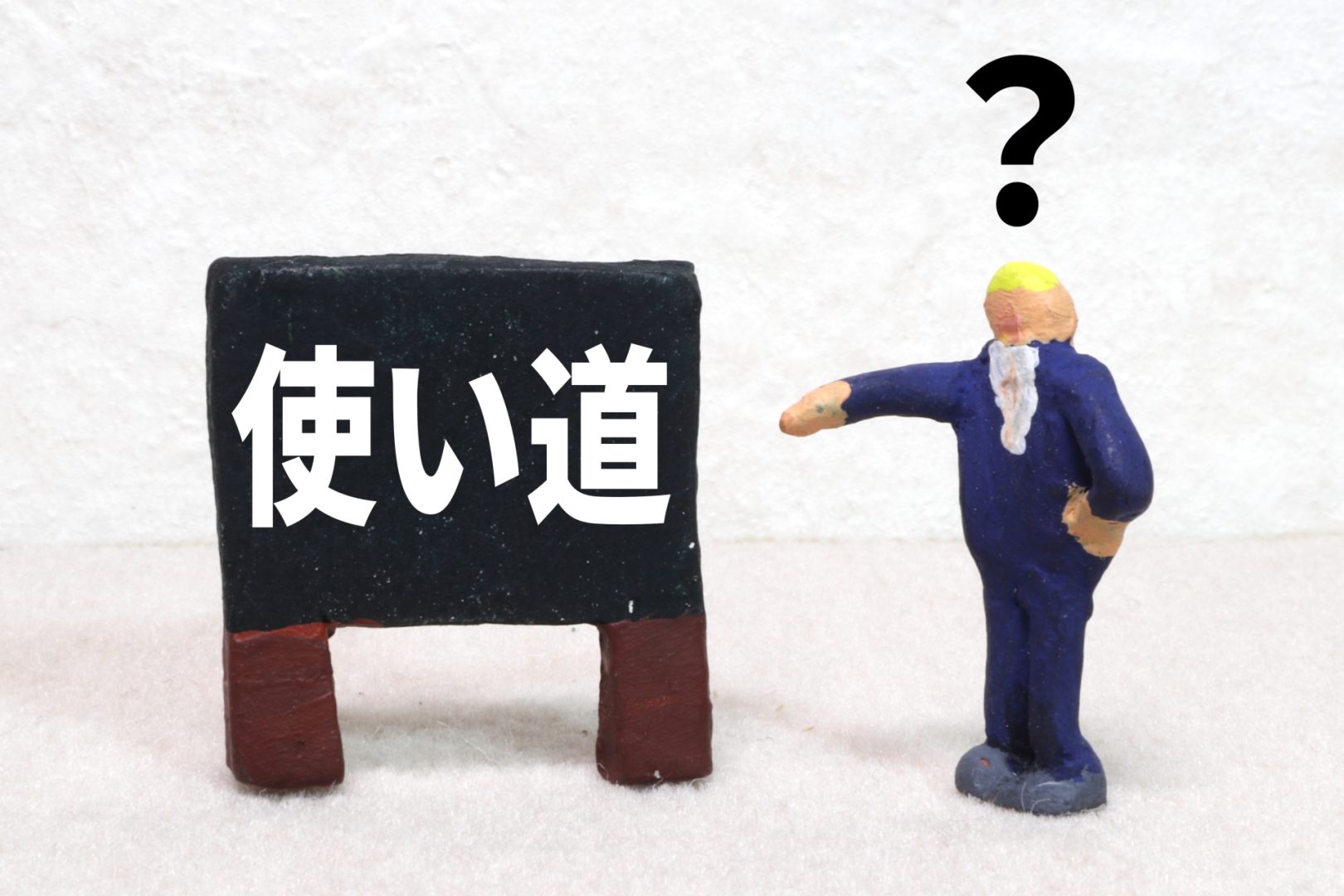
紙の四季報を活用するメリットとして、全企業をパラパラと一覧で眺められ、自分の気付きで銘柄発見できます。
一方Web版(会社四季報オンライン)の特徴は、キーワード検索や条件スクリーニングが可能となることです。
また一部の内容は無料で閲覧可能で、月額2,200円で有料会員になると、「独自コメント」など詳細項目も閲覧ができるようになります。
投資初心者の方はまず紙で感覚を掴みつつ、必要に応じてWeb版の検索機能を使うのがオススメです。
四季報を初心者が最初に見るべきページと項目

会社四季報の1社ごとの掲載情報は、見開き2ページで約8〜10社分がコンパクトに記載されています。情報量が多いため、最初からすべてを読む必要はありません。まずは、掲載情報の見方を確認していきましょう。
会社概要欄
企業がどんな事業をしているのかを簡単に把握できるエリアです。セグメント(事業の区分)や主力商品の内容、ニッチな技術、海外展開などが簡潔にまとめられています。業種分類も記載されているため、同業他社と比較する際の基準にもなります。
業績欄
過去2期分と今期・来期の業績予想(売上高・営業利益・経常利益・純利益) が掲載されています。売上や利益が右肩上がりか? 利益率(営業利益÷売上高)は何%なのか?営業利益率10%以上なら高収益企業の可能性(営業利益率=営業利益÷売上高×100)をチェック。
前号比欄
3カ月前に出た前号と比較して、業績予想がどう変化したかをチェックできる欄です。数字が引き上げられていれば「増額(ポジティブ)」、下がっていれば「減額(ネガティブ)」という評価になります。
ここでは、企業が“予想を上回る成長をしているのか、それとも見込みが下がっているのか”を一目で把握できます。
四季報独自コメント
四季報の記者が独自に取材した情報をもとに、企業の動向を一言でまとめた解説文が書かれています。
また「拡大」「好転」「新製品投入」といったポジティブなキーワードがあれば注目。
来へのヒントとなる「新工場建設」「海外進出」などの記述があるかも要チェックです。
株価指標欄
PER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率)、配当利回りといった「株価が割安かどうか」を見るための指標が掲載されています。
一般的にPERが15倍以下であれば割安とされ、PBRが1倍未満なら資産に対して株価が安いと評価されやすいです。配当利回りが5%以上あると、高配当株として注目されることもあります。
[関連]PER(株価収益率)とは?意味や日本株と米国株における目安、活用方法を徹底解説
[関連]PBR(株価純資産倍率)とは?業種別の目安や計算式、投資での活用術をプロが解説!
株主構成/財務指標欄
自己資本比率が50%以上であれば、借金に頼らずに経営している健全な企業といえます。また、ROE(自己資本利益率)が10%以上であれば、株主から預かったお金を効率よく活用している企業と評価できます。倒産リスクが低く、安定した経営をしているかどうかの判断材料になります。
[関連]自己資本比率の目安は?株式投資で倒産リスクを回避するための見方と使い方
[関連]ROE(自己資本利益率)とは?|計算式や目安を株式投資で使えるようにプロが徹底解説
「業績」「評価」「注目ポイント」の3つに焦点を絞りましょう。
このように四季報には様々な情報があり、最初はどこをどう見るのか悩んでしまう方も多いんです。ですので、ここでは株初心者でも読める「最小セット」の指標の見方をご紹介します。まずはこれを参考にして四季報を読んでみてくださいね。
▼見るべき“最小セット”の指標
| 項目 | 見る目的 | 初心者向け目安 |
|---|---|---|
| 営業利益率 | 高収益企業か? | 10%以上 |
| PER(株価収益率) | 割安感の目安い | 15倍以下 |
| ROE(自己資本利益率) | 資本効率の高さ | 10%以上 |
| 自己資本比率 | 財務健全性 | 50%以上 |
| コメント欄 | 業績修正・成長性のヒント | ポジティブワードを探す |
四季報を読むときの注意点

四季報は万能な「正解」ではない
四季報は情報の宝庫ですが、万能な投資判断ツールではありません。
掲載されている業績予想(売上・利益など)は、企業が公式に発表した数値ではなく、東洋経済の記者・編集部が取材や分析をもとに作成した独自予想です。
そのため、企業のIR資料や決算説明会の内容とは異なる「予測ベース」の情報であり、状況の変化によっては企業発表と乖離するケースもあります。あくまでひとつのシナリオとして捉える視点が重要です。
最大で数カ月の情報遅れがある
四季報は年4回の発行(春・夏・秋・新春)で、掲載される情報は原稿締切時点のものであり、最大で2カ月程度情報の遅れが生じている可能性があります。
時期によっては、決算発表やIR説明会の内容が最新号に反映されていないこともあるため、注意しておきましょう。
新春号だけで判断しない
特に情報量の多い新春号は多くの投資家が注目しがちですが、この1号だけを読んで投資判断を下すのは危険です。
企業の業績や市場環境は常に変化しており、四季報は年4回を通じて業績予想やコメントがどのように修正されているかを追うことで真価を発揮します。
数字そのものだけでなく、前号からの変化やトーンの違いに注目することで、企業を取り巻く環境の変化や評価の方向性をより深く読み取ることができます。
四季報スクリーニングの使い方と活用事例
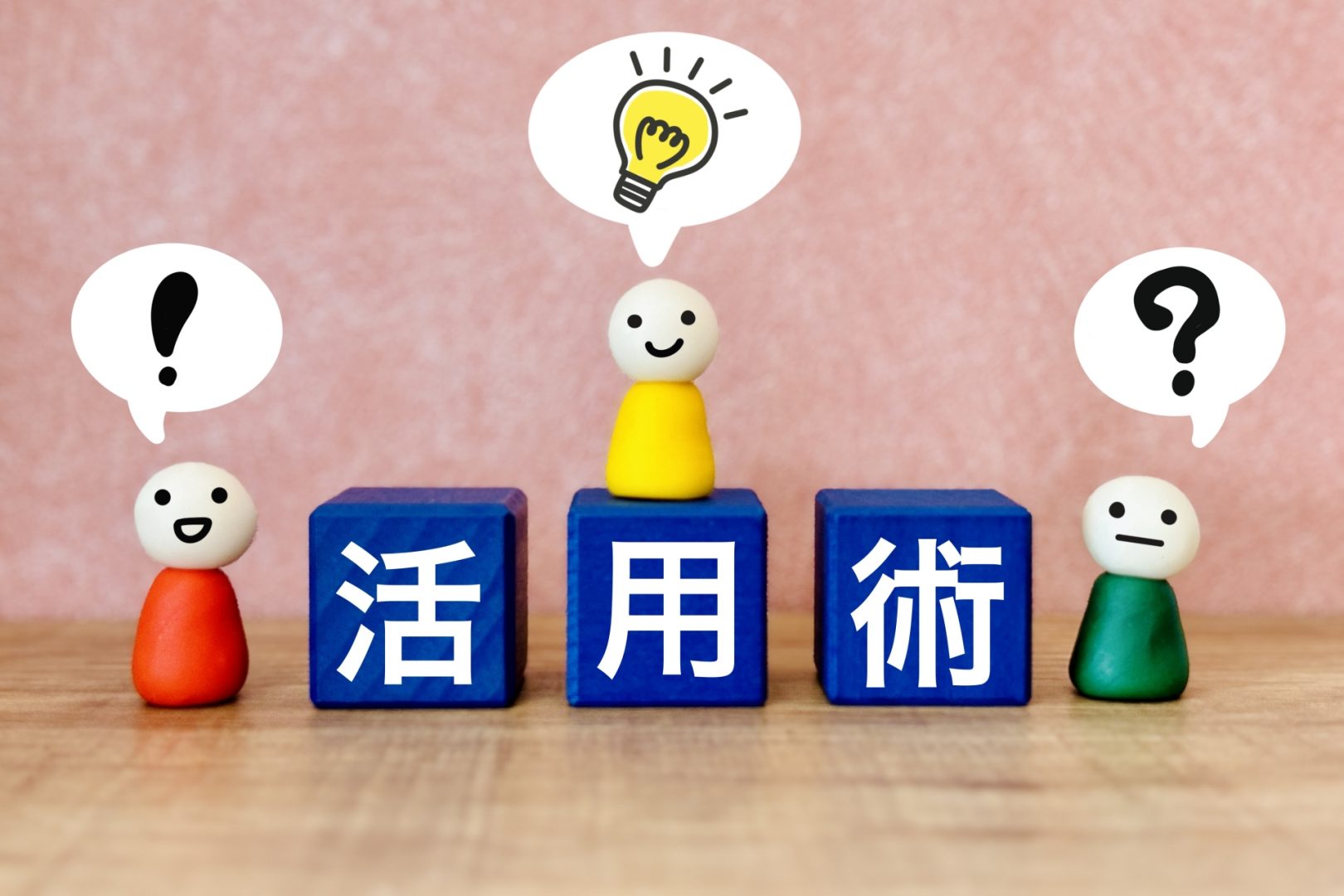
スクリーニングとは一定の条件を設定して、数千社ある上場企業の中から、自分の投資目的に合った企業をふるい分けることです。
会社四季報オンラインなどのWebサービスを使えば、複数の条件を組み合わせて、自分に合った銘柄を効率よく探し出せます。
STEP①:投資目的を決める
まず最初に行うべきは、自分がどんな投資を目指しているのかを明確にすることです。「将来の成長を狙いたいから成長株を探すのか」「割安なタイミングを狙うのか」「安定した配当収入が目的なのか」など、投資スタイルによって探す銘柄の基準は大きく変わります。
また、「話題のテーマに乗りたい」という理由でテーマ株を探すのも有効ですが、その場合も“どのテーマに注目するか”を明確にしておくことが大切です。目的が曖昧なままでは、条件設定にブレが出てしまい、的確な銘柄選定につながりません。
STEP②:条件を2〜4つに絞って設定
スクリーニング機能を使うとき、条件をたくさん入れすぎると絞り込みすぎてしまい、対象となる銘柄がゼロになってしまうこともあります。はじめのうちは「売上高成長率がプラスで、自己資本比率が50%以上」「配当利回りが高く、時価総額が300億円以上」など、2~4個程度のシンプルな条件から始めるのがポイントです。
たとえば、成長性に注目したい場合は「売上高の伸び率」と「営業利益率」、財務の健全性を重視したい場合は「自己資本比率」や「ROE」などの条件を使うと、比較的わかりやすく絞り込めます。
STEP③:結果リストを確認
条件に合致した銘柄が一覧で表示されたら、それぞれの企業についてもう少し詳しく見ていきましょう。会社名だけで判断せず、「どんな事業をしているか」「業績はどう推移しているか」といった基本情報を確認します。
会社四季報のコメント欄には、その企業の最近の動向や注目ポイントが簡潔にまとめられているため、初心者でも理解しやすく、判断材料として非常に役立ちます。できれば売上や利益の推移、チャートの動きなども合わせて見ておくと、より立体的な銘柄評価が可能になります。
STEP④:気になる銘柄はウォッチリストで管理する
リストの中で気になる銘柄が見つかったら、すぐに購入を決めるのではなく、証券口座のマイページや四季報オンラインのウォッチリスト機能に登録して、継続的に情報を追っていくのがおすすめです。
株価の動きや出来高、決算情報などを定期的にチェックしながら、買い時をじっくり見極めていく姿勢が大切です。また、四季報の次号が出たときに同じ企業がどう評価されているかを追うことで、中長期での見通しの変化や業績の進捗を確認できます。
焦らず、客観的な視点で情報を集めながら投資判断を進めましょう。
[関連]証券口座とは?初心者でもわかる仕組み、株取引に必須となる証券口座の開設方法や選び方を解説
具体的な活用事例
これまでお伝えしたことを踏まえて一つ、高収益グロース株を探す場合のスクリーニングをご紹介します。
売上高成長率(前期→今期)で10%以上、営業利益率は10%以上、ROE15%以上、時価総額は500億円未満の中小型株。
中小型で高収益な成長株を探し、見つかった銘柄は、四季報コメントで「新規分野拡大」「海外強化」などの文言を探して将来性を確認しましょう。
四季報秋号に注目ポイントあり

秋号は、10月~11月に控える「中間決算」の直前に発行されるため、企業の最新の業績動向や、下半期(10月以降)の見通しが反映され始めるタイミングになります。そのため、株価にとって重要な“次の材料”を先回りして見つけるヒントが多く含まれているのが特徴です。
業績の上方修正が織り込まれた銘柄や円安・原材料安など外部環境変化を受けた修正企業、来期の変化に含みを持たせる独自コメントなどに注目すると良いでしょう。
成長株・割安株・高配当株…見つけ方の違いとコツ

「なんとなく」で銘柄を選ぶよりも、自分が何を求めているかを明確にし、それに合った指標・コメントを見ることが、四季報活用の本質となります。
銘柄の見つけ方の違いとコツについて、目的別に見るべき指標やチェックポイント、四季報で注目すべき文言や事例を交えて解説します。
成長株(グロース株)を見つけるコツ
| 見るべき四季報項目 | 指標 |
|---|---|
| 売上高の成長率 | ビジネスが拡大しているか?年10%以上の成長性があるか? |
| 営業利益・純利益の成長率 | 利益体質か?理想は右肩上がり。 |
| ROE(自己資本利益率) | 資本効率の良さを確認。15%以上を意識。 |
| 営業利益率 | 高収益の証となり、10%以上は要チェック |
| コメント欄 | 「伸長」、「拡大」、「新規参入」など成長ストーリーの裏付けとなるような文言に注目 |
四季報での見つけ方のコツ
コメント欄に「好調」「受注拡大」「シェア拡大」「需要追い風」などのワードがあれば注目してチェックしましょう。また、過去3年の売上・利益が途切れなく成長している企業や、時価総額が低い(100億円未満など)企業は狙い目となりやすいです。
割安株(バリュー株)を見つけるコツ
| 見るべき四季報項目 | 指標 |
|---|---|
| PER(株価収益率)、PBR(株価純資産倍率) | 利益に対して株価が割安か? |
| 営業利益または経常利益 | 安定黒字かどうか?過去数年黒字維持が理想。 |
| 自己資本比率 | 50%以上あれば倒産リスクを比較的に回避できる。 |
| コメント欄 | 「再評価」「資産活用」「見直し」などは株価上昇余地のサインかも。 |
四季報での見つけ方のコツ
低PER、PBRなのに、収益が安定していて赤字でない企業に注目。コメントに「株価見直し」「再評価余地」「自社株買い」などがあればチェックしましょう。
[関連]グロース株とバリュー株の違いとは?見分け方や投資する際のメリット・デメリットを解説!
高配当株(インカム株)を見つけるコツ
| 見るべき四季報項目 | 指標 |
|---|---|
| 配当利回り | 年間の配当収入の大きさを確認。 |
| 1株配当額 | 実際の配当額であり、継続して増配されているか? |
| 営業キャッシュフロー | 配当の原資になるため、安定黒字であることが重要。 |
| コメント欄 | 「配当維持」「株主還元方針」などは、配当重視の投資において長期的な安心感があります。 |
四季報での見つけ方のコツ
コメントに「高水準配当」「減配なし」「増配続く」などが書かれていれば信頼感があり、安定配当ならなお良し。過去数年の配当推移(増配か減配)も確認するとさらなる安心感につながります。
成長相場では グロース株の勢いが活きる場面が多くなり、調整局面では 割安株や高配当株の安定感が武器になるでしょう。自分の資金規模やリスク許容度に応じて、複数の視点で組み合わせるのも有効です。
読みこなせば武器になる!四季報は投資家の強力な味方
会社四季報は、数ある投資ツールの中でも情報の信頼性と網羅性に優れた存在です。最初は情報量の多さに圧倒されるかもしれませんが、ポイントを絞って少しずつ慣れていけば、自然と読みこなせるようになります。
スクリーニング機能を使って効率よく銘柄を探したり、記者コメントから未来の成長ヒントを見つけたりと、使い方次第で可能性は無限に広がるでしょう。
「なんとなく有名だから」ではなく、「自分の判断で選べる」投資家になるために。四季報というツールを味方にし、自分だけの銘柄選びを始めてみてください。
アナリストが選定した銘柄が知りたい!
今なら急騰期待の“有力3銘柄”を
無料で配信いたします
買いと売りのタイミングから銘柄選びまで全て弊社にお任せください。
投資に精通したアナリストの手腕を惜しげもなくお伝えします。
弊社がご提供する銘柄の良さをまずはご実感ください。
▼プロが選んだ3銘柄を無料でご提案▼
執筆者情報
日本投資機構株式会社 投資戦略部 室長
大学時代に投資家である祖母の影響で日本株のトレーディングを始める。大学時代、アベノミクスの恩恵も受けて資金を増やすことに成功する。卒業後、証券会社、投資顧問会社を経て2019年2月より日本投資機構株式会社の分析者に就任。モメンタム分析を最も得意としており、IPO(新規上場株)やセクター分析にも長けたアナリスト。
![Invest Leaders[インベストリーダーズ]](https://jioinc.jp/investleaders/wp-content/uploads/2025/07/logo_01.png)