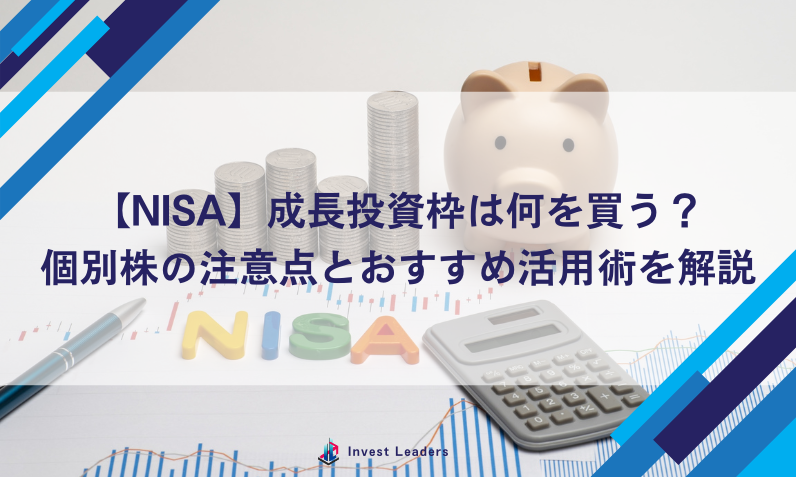2024年から始まった新NISA制度。「非課税で投資ができる」と聞いて興味はあるけれど、実際に何を買えばいいのか迷っていませんか?
この記事では、新NISAの中でも攻めの枠とされる「成長投資枠」に注目し、個別株を買うべきかどうか、そのメリット・注意点、さらに失敗を避けるための実践的な戦略まで解説します。
これから新NISAを始めたい初心者の方にもわかりやすく整理しています。
「NISA」とは利益にかかる税金がゼロになる国の制度

NISAとは利益にかかる税金がゼロになる制度です。通常、投資で得た利益には約20.315%の税金がかかりますが、NISA口座を利用すれば非課税投資枠内での利益は非課税になります。
そのため、運用次第では非常に効率的な資産形成が可能です。
ただし銘柄選びや売買のタイミングを間違えれば、非課税でも損失は出るため「儲かるかどうか」は使い方次第ということは理解しておきましょう。
NISAなら配当金もまるごと非課税

通常、株式取引で10万円の利益を出すと約20%の税金が発生し、手元に残るのは約8万円となります。しかし、NISAならそのまま10万円が手元に残ります。また、配当金も同様に非課税で受け取れます。
運用益が複利で積み上がる長期投資では、税金の差が最終資産に大きく影響します。これが「非課税の威力」です。
2023年までとここが違う!「新NISA」の4つの重要変更点

変更点①:つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能
旧制度では、つみたてNISAと一般NISAのどちらか一方しか利用できず、年間1回しか変更できませんでした。
そのため、長期・分散投資を進めながら成長株にも投資する、といった戦略は取りにくい仕組みでした。
しかし新NISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠を同時に利用できるようになり、資産形成と積極運用を同時に進めることが可能に。
2つの枠を併用することで、リスクを分散しつつ効率的な資産形成を目指すことができるようになりました。
変更点②:従来は最長5年だった非課税期間が「無期限」に
旧制度では最長5年間しか非課税の恩恵を受けられませんでしたが、新NISAでは一度購入すれば非課税のまま保有を続けられるようになりました。
これにより、長期保有を前提とする銘柄選びがしやすくなっています。
変更点③:年間投資枠が拡大
従来の年間投資上限は、一般NISAで120万円、つみたてNISAで40万円の合計160万円でした。しかし、新NISAにより成長投資枠240万円+つみたて投資枠120万円の年間最大360万円まで投資が可能になっています。
従来と比較して投資可能額が大幅に拡大し、資産形成のスピードアップが期待できます。
変更点④:非課税枠の再利用が可能に
旧NISAでは、一度使った非課税枠は売却しても戻りませんでしたが、新NISAでは売却後に空いた枠を再利用可能となりました。NISAで購入した株式を売却しても、その年内に再投資できます。これにより柔軟な売買戦略が組めるようになりました。
旧NISAと新NISAの違いまとめ
旧NISAと新NISAの仕組みや制度の違いは以下の通りです。

参考:金融庁「NISA特設ウェブサイト」
旧NISAから新NISAへと制度が大きく変わったことで、投資の自由度や非課税メリットの範囲が拡大しました。
新NISAの「成長投資枠」と「投資対象」の使い方の基本

2024年からスタートした新NISAでは、「成長投資枠」と呼ばれる自由度の高い非課税枠が用意されています。この成長投資枠では、個別株やETF、REIT、一般の投資信託(※つみたてNISA対象以外のもの)など、さまざまな金融商品に投資することができます。
年間240万円までの投資が非課税対象となり、その枠の中で好きなタイミング・好きな商品に投資できるのが特徴です。とくに、個別株に非課税で投資できる点は、成長投資枠ならではの魅力といえるでしょう。
この枠は、将来の値上がり益(キャピタルゲイン)や配当金などを効率よく受け取りたい人に向いています。たとえば、「これから成長が期待できそうな企業の株を買いたい」「高配当のETFで収入を増やしたい」といった、中長期で資産を増やしたい人向けの“攻めの投資枠”です。
一方で、投資先は自分で選ぶ必要があるため、「何を買えばいいかわからない」という方は、まずは商品ジャンルごとに特徴をつかみ、少額から始めていくのがおすすめです。
新NISAを始める前に準備しておくべき3つのこと

NISA対応の証券口座を開設
NISAを利用するには、金融機関で専用の「NISA口座」を開設する必要があります。
1人1口座のみなので、どの証券で開設するかは慎重に選びましょう。
[関連]証券口座とは?初心者でもわかる仕組み、株取引に必須となる証券口座の開設方法や選び方を解説
証券会社選び
NISAで買える商品は証券会社ごとに異なります。例えば、米国株に強い会社、低コストETFが豊富な会社、初心者向けのUIを持つ会社など様々です。
取扱銘柄数や使いやすさで比較し、自分の投資スタイルに合った証券会社を選ぶことが重要です。
初期設定と入金の確認(枠の利用設定、積立設定など)
NISA口座を開設したら、年間の非課税枠をどう使うかの設定や、毎月の自動積立設定、資金の入金確認を行いましょう。特に「成長投資枠」と「つみたて投資枠」のどちらを使うかを事前に決めておくとスムーズにスタートできます。
初心者がつまずきやすいのは「どこで始めるか」「何を選ぶか」なので、口座と証券会社はしっかり比較しましょう。
新NISAで初心者におすすめの“成長投資枠”商品ジャンル

成長投資枠は、自分で選んだ商品に積極的に投資することができます。
初心者が最初に選ぶにあたっては、「値動きが比較的安定している」「分散効果が期待できる」「長期的に成長が見込まれる」など、中長期目線でのジャンルから選ぶのが安心といえるでしょう。
また、ETF(上場投資信託)の活用も考えておきましょう。
ETF(上場投資信託)は、1つ買うだけで複数銘柄に分散投資できる仕組みの商品です。個別株よりも比較的リスクが低く、初心者にとっては「最初の一歩」となる選択肢です。
初心者の方が最初に選ぶにあたり、まずはジャンル別で大まかに方向性を決めるという方法がいいかと思われます。
新NISAのつみたて投資枠と成長投資枠の戦略的組み合わせ術

新NISAには成長投資枠の他につみたて枠があります。この2つのメリットを考えたうえで投資を行うことでより効率的に資産を増やすことができるでしょう。
つみたて投資枠の活用法(守りの運用)
つみたて枠は、毎月コツコツと積み立てながら、長期的に資産を育てるための枠です。対象となるのは、国が認めた「長期・積立・分散」に適した投資信託で、信頼性の高い商品がそろっています。
例えば、
・「eMAXIS Slim」シリーズ(国内外の株式に連動する低コストのインデックスファンド)
・「S&P500連動型の投資信託」(米国の主要企業に分散投資)
などが代表的です。
毎月同じ金額を積み立てる「ドルコスト平均法」を活用することで、購入価格が平均化され、リスクを抑えながら投資が続けられるのも大きな特徴です。
[関連]赤字でも株価は上がる!?赤字企業の株に投資するメリットやポイントをプロが解説!
成長投資枠の活用法(攻めの運用)
成長投資枠は、自分で自由に投資商品を選んで、将来の値上がりや配当を狙う枠です。
こちらでは個別株やETF(上場投資信託)、アクティブ型の投資信託など、幅広い商品が対象になります。
たとえば、
・日本株の高配当銘柄(例:三菱HCキャピタル、NTTなど)
・米国株ETF(例:VOO、VYMなど)
・成長性の高い企業が組み込まれたアクティブファンド
といった商品が人気です。
「配当金で収入を得たい」「将来伸びそうな企業に投資したい」という人には、この成長枠がぴったりです。
組み合わせのポイントはポートフォリオ全体のうち6〜8割は安定的に育てるコア資産「つみたて枠」に配分し、残り2〜4割を「成長投資枠」に振り分けるなど、資産配分を意識しましょう。
まずは安定を重視した資産バランスにすることで値上がり益を狙いつつ、中長期で資産増加を目指すことを目標として、つみたて枠の比率を多めに設定するのが最初の一歩です。
全体のリスクバランスを見ながら「つみたて+成長投資」という考え方で組み合わせると資産増減も安定しやすくなります。
新NISAの売却タイミングと“再利用”ルールの活かし方

新NISAでは、成長投資枠を売却しても、その年の枠内であれば再投資が可能です。
例えば年初に100万円分の株式を購入し、途中で50万円分を利益確定すると、その50万円分の非課税枠が空きます。その空いた枠を同じ年内であれば再利用できるため、新しい銘柄やETFに投資できます。
この仕組みにより、保有銘柄の見直しや相場状況に応じた戦略的な売買が可能になり、柔軟な資産運用ができるようになりました。
重要ポイント
1.売却した分の枠は翌年には繰り越せないため、その年内に使い切る必要があります。
2.含み損の状態で売却すると枠が戻るものの、損失が確定してしまうためタイミングが重要です。
利益確定のための売却と、ポートフォリオの入れ替えを組み合わせると効率的に枠を活用できます。
【活用例】
年初に成長投資枠で米国ETFを100万円分購入
↓
半年後に株価が20%上昇したため50万円分を利益確定
↓
空いた50万円の枠で高配当株に再投資。
↓
相場が悪化して含み損が出た個別株を一部損切り。
↓
同じ年内に安定性のあるインデックスETFに資金をシフトする。
このような活用をすると、利益確定や資産入れ替えの際に「非課税枠を取り戻せる」点を活かすことができ、資産をより効率的に増やすことができます。
過去人気を集めた新NISA対象銘柄と投資傾向

NISAを活用して投資する人たちは、どのような銘柄を選んでいるのでしょうか?
実際に人気を集めた企業やETFを見てみると、投資家がどんな基準で商品を選んでいるか、また、今どんなテーマに注目が集まっているのかがわかります。
特に2024年前半は、以下のようなジャンルの銘柄が人気となりました。
日本株(高配当株が人気)
三井物産やENEOS、NTTなど、安定した配当金が期待できる企業が多く選ばれました。「配当金を毎年もらいながら、資産を増やしていきたい」という投資スタイルの人にとって、こうした高配当株は魅力的な選択肢です。
米国ETF(成長企業にまとめて投資)
VOO(S&P500)、QQQ(ナスダック100)といった米国ETFも注目を集めました。
これらは、アメリカの有名な企業がたくさん含まれており、一つ買うだけで分散投資できるのがポイントです。長期的な成長を期待する人にとって人気が高い選択肢となっています。
テーマ株(将来の成長を期待)
AI(人工知能)や再生可能エネルギー、電池材料といった将来性のある分野の企業も注目されました。
「これからの時代を変える技術に投資したい」という人には、テーマ株が支持されています。
2024年は、「配当金を安定的に受け取る高配当株」と「将来の成長を期待するグロース株」のバランスを重視する動きが見られました。初心者の方も、自分の目的や投資スタイルに合わせて、こうした人気のジャンルを参考にしてみると良いでしょう。
[関連]AI関連銘柄がアツい!過去の急騰銘柄と今注目の有望企業を紹介
[関連]再生可能エネルギー関連株を徹底解説|投資初心者が押さえるべき注目企業
新NISAを賢く使うための3つの注意点と落とし穴
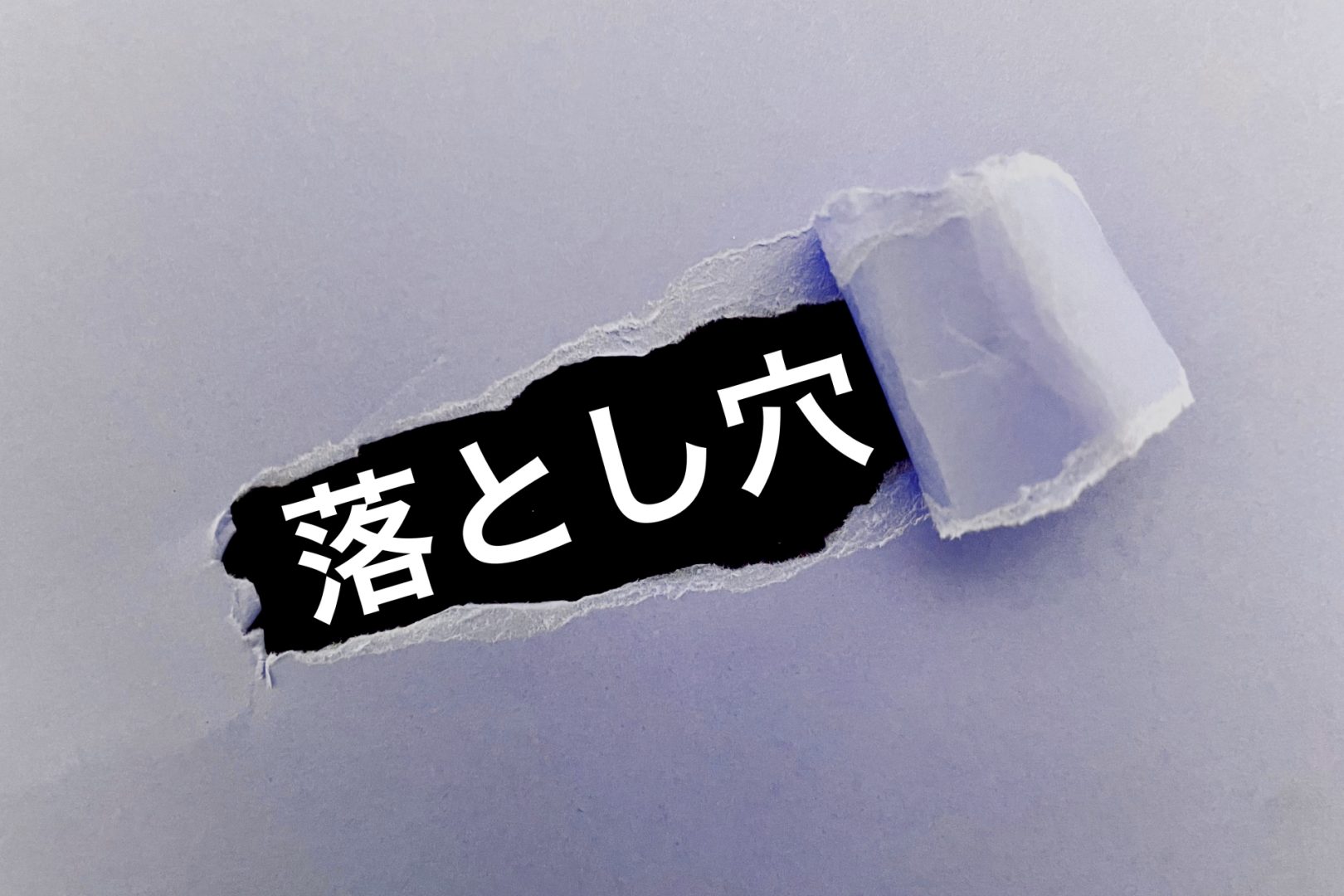
短期売買の繰り返しは逆効果になることも
新NISAでは、売却した分の枠を再利用できる仕組みがありますが、だからといって頻繁に売買を繰り返すのはおすすめできません。短期的な値動きに振り回されてしまうと、投資の方向性がぶれてしまい、結果として損失を出すリスクが高まります。
NISAは本来、中長期の資産形成を目指す制度です。焦らず、腰を据えて運用することが成功のコツです。
NISA口座では「損失を他と相殺できない」ルールに注意
NISA口座で投資して損失が出た場合、他の利益と相殺(損益通算)することができません。たとえば、特定口座で20万円の利益、NISAで10万円の損失が出た場合でも、その損は他で取り返すことができません。
このため、一つの銘柄に大きく投資するのではなく、複数に分散して投資するなど、リスク管理が大切になります。
人気銘柄は割高になっているリスクも高い
NISAでよく買われている銘柄は、多くの人が注目しているため、実際の価値以上に株価が上がってしまっていることもあります。こうした銘柄は、「なんとなく人気だから」という理由だけで買うのではなく、本当に今の価格が適正なのかをチェックすることが大切です。
PER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率)といった「割安かどうかを見る指標」を使って判断するのがポイントです。
NISAは非課税でお得な制度ですが、「何に投資するか」「どのように運用するか」をしっかり考えないと損をすることもあります。初心者の方は、分散投資・長期保有・過信しないという3つの姿勢を意識して、じっくり資産を育てていきましょう。
[関連]PER(株価収益率)とは?意味や日本株と米国株における目安、活用方法を徹底解説
[関連]PBR(株価純資産倍率)とは?業種別の目安や計算式、投資での活用術をプロが解説!
まとめ|“コアはつみたて、攻めは成長枠”で長期最適化
新NISAの成長投資枠は、個別株やETFを使って積極的に資産を増やすための有効な制度です。
ただし、自由度が高い=リスクも自己責任という点を忘れずに、しっかりとした目標設定と資産配分を決めて使うことが大切です。
つみたて枠で長期安定運用の土台を作り、成長枠ではテーマ株や高配当株などでチャンスを狙う「ハイブリッド型運用」を意識しましょう。
また、再利用ルールや非課税のメリットを活かし、利益確定や入れ替えの戦略も取り入れると、より効率的に資産形成が進みます。
アナリストが選定した銘柄が知りたい!
今なら急騰期待の“有力3銘柄”を
無料で配信いたします
買いと売りのタイミングから銘柄選びまで全て弊社にお任せください。
投資に精通したアナリストの手腕を惜しげもなくお伝えします。
弊社がご提供する銘柄の良さをまずはご実感ください。
▼プロが選んだ3銘柄を無料でご提案▼
執筆者情報
日本投資機構株式会社 アナリスト
大学時代に投資家である祖母の影響で日本株のトレーディングを始める。大学時代、アベノミクスの恩恵も受けて資金を増やすことに成功する。卒業後、証券会社、投資顧問会社を経て2019年2月より日本投資機構株式会社の分析者に就任。モメンタム分析を最も得意としており、IPO(新規上場株)やセクター分析にも長けたアナリスト。

![Invest Leaders[インベストリーダーズ]](https://jioinc.jp/investleaders/wp-content/uploads/2025/07/logo_01.png)