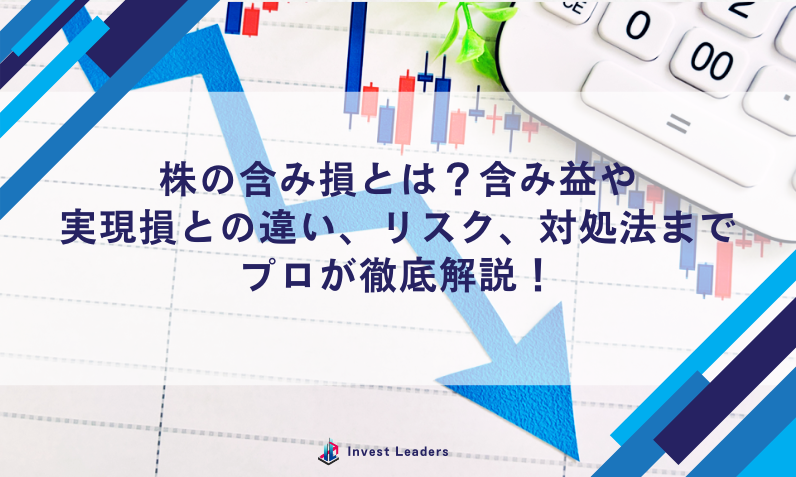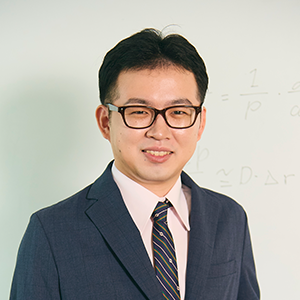「買い付けた銘柄が大きく下がったけれど、売らなければ損失は確定していないから、まだ損ではない」と永遠に含み損の銘柄を持っている投資家の話をよく聞きます。
勿論、将来的に上昇の期待がある、配当や優待を目的として保有している、応援している企業だから、etc…などの理由があって持っているなら良いと思います。
しかし、上昇の目途もなくただ単に売りたくないという人もいると思います。
実はその行動は既に損に繋がっています。
今回は含み損の株式は売らなくても損に繋がることについて解説しています。
株の含み損(ふくみぞん)とは購入時より価値が下がっている状態のこと

株の含み損とは、保有している株の現在の時価が購入時より下回っている状態を指します。
例えば1株1,000円で購入した株が、現在900円になっていれば、1株あたり100円の含み損ということです。
この段階では株を売却していないため、損失はまだ確定しておらず、「見かけ上の損失」となります。
株の含み損の計算式と算出方法
含み損の計算式は以下の通りです。
含み損は現在の資産の評価額から、その資産の取得価格を差し引いた金額で表されます。
では実際の計算例を見てみましょう。
例えばある企業の株を1株1,000円で100株購入し、現在の株価が900円に下落した場合は以下の通りです。
取得価格の合計:1,000円 × 100株 = 10万円
現在の評価額:900円 × 100株 = 9万円
この場合の含み損は
9万円 - 10万円 =-1万円
つまり「現在保有している株の含み損は1万円」ということになります。
株の含み損からわかること
含み損は単に「損をしている」と捉えるだけでなく、自分の投資判断の適切さやリスク許容度を再評価する重要な指標でもあります。
保有する特定の株価だけが下落している場合、購入時の判断に改善の余地があったかもしれません。
一方、株価の下落が市場全体の動きに連動している場合、景気後退や金利の変動などのマクロ要因が影響している可能性が高いと考えられます。
含み損が発生した時はこうした背景を分析し、「買い時は適切だったか」「銘柄選びは正しかったか」を振り返ることで、次の投資判断に活かすことができるのです。
株の含み益は購入時より価値が上がっている状態のこと
含み益とは購入時より株価が上昇し、保有中の株式に「未確定の利益」が出ている状態を指します。
例えば1株1,000円で買った株が現在1,500円になっていれば、1株あたり500円の含み益ということ。
ただ売却するまでは利益は確定しておらず、相場が変動すればすぐに含み損に転じる可能性もあります。
株の含み損益と実現損益の違いは「確定済み」かどうか

保有している株の損益は、「含み損益」と「実現損益」に分けられます。
含み損益は株を保有している間の評価額であり、売却しない限り未確定の状態。
実現損益は株式を売却して現金化することで確定した最終的な損益を指します。実現損益が確定すると、その後の株価変動による影響は受けません。
保有中 → 含み損益(未確定)
売却後 → 実現損益(確定)
つまり株式投資において「売却」という行動が、含み損益を実現損益に変える重要な境界点となります。
株の含み損への対応は、投資スタイルによって考え方が異なる
含み損が発生した時に取るべき対応は、「短期投資なのか」「中長期投資なのか」といった投資スタイルによって大きく変わります。
同じ含み損であっても、投資目的や保有期間が異なれば、適切な判断も当然異なるからです。
短期的な値動きを狙っている場合、含み損は想定と異なる方向に相場が動いたサインと捉えるべきケースが多く、損失拡大を防ぐために早めの判断が求められます。
一方、中長期を前提に投資している場合は、一時的な株価下落が必ずしも投資判断の失敗を意味するとは限りません。
そのため、まずは自分がどの時間軸で投資しているのかを整理することが重要になります。
株の含み損を放置すると危険?知らないと怖い4つのリスク

含み損となった株式を売却しないと、以下のような様々なリスクを抱えることになります。
こうしたリスクを加味しても、売らないという選択肢を取るのか十分に考える必要があります。
①機会損失リスク
株を売らなければ、勿論その株を買った分の資金は動かせなくなってしまいます。
上昇期待のある銘柄を見つけたとしても、そちらに向けられる投資金の量が少なくなってしまいます。
少なくなるどころか、投資金が全て拘束されていた場合は、チャンスを逃すことになります。
株式市場に入れている投資金に対して、得られる利益が少なくなるため、運用パフォーマンスが大きく低下してしまうでしょう。
②継続下落リスク
株式を持っているということは、それだけで価格変動リスクがあります。
つまり、含み損がどんどんと増加していく可能性があります。
勿論、上昇する可能性もあるわけですが、含み損になっているということは、チャートも下落トレンドになっている可能性が高いです。
上昇転換の期待が出来るなら話は別ですが、転換する目途もないとなると長期の下落となり、仮に上昇したとしても買値にすら戻らないなんてこともあり得ます。
③心理的ストレス
含み損の銘柄を持っているとそれだけで、ストレスになります。
証券口座にログインしてみたら大きな額の含み損が表示されるのは嫌ですよね。
さらに下落したらどうしようとか、市場が悪化したら…などを考えていると当然不安になります。
このような状態が続くと、株式投資を継続することも難しくなってしまう可能性があります。
④そもそも損している
株式の価値が減っている時点で、保有している資産という観点から価値は減少しています。
買値に戻ってから売れば…とかそういう話ではなく、含み損を抱えている時点で、株式を買った時から比較して、資産の価値が減少しています。
お金を株式に換えた時点で、資産としては株式の価値が資産の価値になります。
その株式の価値が減少しているという時点で、保有資産という観点から損をしています。
例えば、胡椒を1キロ持っている人が「胡椒は昔、金銀と同じ価値があった。まだ売ってないから、このコショウを持っている私は金銀を1キロもっているのと同じだ」と言っていても、現代での価値としては胡椒1キロです。
金銀と同じ価値を持っていると言っても、納得できる人は少ないのではないでしょうか。
株の含み損と税金の関係性について

株式投資では含み損や含み益が税金にどう影響するかを正しく理解しておくことが大切です。
ここからは含み損と税金の関係について解説していきます。
含み損は未確定の損失なので課税対象ではない
株を保有している間の含み損はあくまで評価上の損失で、実際には損失が確定していません。
そのため、売却して損失が確定しない限り、税務上は「損していない」と見なされます。
つまり、含み損の状態で損失を確定させるかどうかは、投資判断次第です。
保有する株価が回復する可能性を考慮できる場合は、税金を意識して慌てて売却する必要はありません。
含み損が確定(売却)したタイミングで損益通算が可能
含み損は株を売却した瞬間に実現損となりますが、同じ年に売却益が出ている株がある場合、確定申告をすれば「損益通算」が可能です。
損益通算とは同一年度内に発生した利益と損失を差し引き、課税対象額を減らせる制度のことです。
例えばA株で20万円の含み損を確定させ、B株で40万円の売却益がある場合で考えてみましょう。
通常40万円の売却益に対して約8万円の税金がかかりますが、損益通算を行えば課税対象となる利益は、40万円-20万円=20万円となります。
この仕組みを活用することで、約4万円の節税ができるのです。
確定申告をすれば3年間の繰越控除も使える
株の売却で損失が出た年に、確定申告を行うことで「損失の繰越控除」を利用できます。これは、損失を翌年以降3年間にわたり、株の売却益や配当所得と相殺できる制度です。
例えば、ある年に50万円の損失が出て、その年に利益が出ていない場合でも、翌年に30万円の売却益が出れば、その利益を全額相殺し、課税をゼロにできます。さらに残りの20万円分は、翌々年まで繰り越して活用できます。
ただし繰越控除を適用するには、損失が発生した年から繰り越す期間(最長3年間)まで、連続して毎年確定申告を行う必要があります。
1度でも申告を忘れると、その時点で繰越控除の権利は失われてしまうため、含み損を確定させた年は必ず申告しておきましょう。
株で含み損を抱えた際に取るべき行動

株式投資において含み損を抱えることは珍しいことではありません。
ここからは実際に含み損を抱えてしまった場合、取るべき行動について解説していきます。
事前に定めた損切りルールに基づき売却
含み損が一定の水準を超えた場合には、事前に決めた損切りルールに従って売却することが重要です。
例えば「この株が5%下落したら売る」といった損切りラインを決めておくことで損失の拡大を防ぎ、かつ冷静な判断を維持できます。
また損切りは単なる損失確定ではなく、新たな投資機会に資金を充てられるというメリットもあります。
損切りラインを決める際には、自身のリスク許容度や投資スタイルに応じて、明確な数値や%で設定すると効果的です。
投資対象の成長性や将来性を見極めて長期保有を検討
株の基本的な価値や成長性が高いと判断できる場合、含み損を抱えていても長期保有を検討することも有効です。
安定した収益を上げている企業や、将来的に事業拡大が見込まれる企業であれば、株価が一時的に下落しても、時間をかけて回復する可能性があります。
ただし、企業の財務状況や競合環境の変化を定期的にチェックし、状況に応じて保有を継続するか再評価することが大切。安易に「いつか戻るだろう」と放置してしまうと塩漬け株となり、資金の有効活用が難しくなるため注意が必要です。
[関連]貸借対照表(バランスシート)とは?投資家初心者が企業価値とリスクを見抜く読み方を解説
[関連]損益計算書(P/L)とは?投資初心者が押さえておきたい決算書の見方をアナリストが解説
投資対象の成長性や将来性を見極めてナンピン買い
株価が下落しているタイミングでは、ナンピン買いを検討する方法もあります。
ナンピン買いとは保有する株式の価格が下落した際、追加で同じ銘柄を購入して平均取得価格を下げる投資戦略です。
ただし、ナンピン買いは資金拘束やさらなる下落のリスクも伴います。
そのため企業の成長性や業績、業界動向を分析し、長期的に株価が回復する見込みがある場合に限定することが重要です。
[関連]ナンピン買いは良くない?ルールやいつすべきかの目安、リスクを徹底解説!
含み損を一度売却して他の売却益と損益通算する
同じ年に売却益が出ている場合には、確定申告を通じて損益を相殺できる「損益通算」が有効です。
損益通算を活用すれば余分に支払う税金を抑え、その分を新たな投資に回すことができるので、運用資金を効率よく循環させることも可能です。
特に複数の銘柄を保有していたり投資資金を積極的に活用したい場合には、戦略的に利用する価値の高い方法です。
株の含み損に怯えずに投資を続けるコツ

株式投資で含み損があると不安になりがちですが、損失に過剰反応せず冷静に投資を続けることが重要です。
ここからは感情に左右されず、安定して資産運用を行うためのポイントを解説していきます。
感情に左右されない投資ルールを持つ
投資を続ける上で最も大切なのは、あらかじめ自分で決めた投資ルールを守ることです。
損切りラインや利確ライン、投資金額の上限などを事前に決めておくことで、短期的な株の変動に一喜一憂せず冷静に判断できます。
またルール通りに行動することにより感情的な判断を防ぎ、長期的に安定した資産運用を行いやすくなります。
投資対象の成長性と財務の健全性を評価する
株式投資で銘柄を選ぶ時は単に株価の動きだけでなく、その企業自体の本質的な価値を見極めることが不可欠です。
業績の安定性や財務の健全性、競争力のある事業モデルなどを確認し、長期的に成長が期待できる企業に投資することで、含み損の期間も心配が少なくなります。
またこうした分析をもとに投資判断を行うことで、感情に流されず計画的に資産形成を進めることが可能になりますよ。
分散投資を心がける
分散投資は含み損のリスクを低減する有効な手段です。
例えばIT株だけでポートフォリオを組む場合、業界全体が下落すると損失が拡大しますが、異なる業種に分散していれば下落リスクを緩和できます。
分散投資はリスク管理の基本であり含み損に対する心理的ストレスも軽減できるため、長期投資の安定性が向上します。
定期的にポートフォリオを見直す
投資環境や企業の状況は常に変化するため、定期的にポートフォリオを確認して調整することが重要です。
株価が上昇した銘柄を一部利益確定したり、成長性が低下した銘柄を見直したりすることで資産効率を高められます。
また市場全体の変動や経済状況に応じて、保有比率を調整することでリスク管理も可能。
ポートフォリオを定期的にチェックする習慣をつけることで含み損に過度に怯えることなく、計画的な資産運用を継続できます。
リスクとは何かを理解した上で投資を行おう!

そもそも、買う時にどこまで下がろうと持続しようと考えて買う人は少数です。
そして出来る限りリスクを低い取引をしようと考える人が多いのではないでしょうか。
しかし、実際に損に直面した時に損を取り戻そうとする時、人は通常よりもリスクを取ることが多い、という研究結果もあります。
このような状況にならないように、常にポートフォリオの見直しや、買い付け前に損切りルールを決めることなどが必要です。
損が出ていると、デメリットに向き合わずに放置してしまうことがあると思いますが、資金を増やすためには常にメリット・デメリットに向き合って運用していくことが大事です。
運用がうまくいってない時ほど、冷静に判断して運用を行っていきましょう。
アナリストが選定した銘柄が知りたい!
今なら急騰期待の“有力3銘柄”を
無料で配信いたします
買いと売りのタイミングから銘柄選びまで全て弊社にお任せください。
投資に精通したアナリストの手腕を惜しげもなくお伝えします。
弊社がご提供する銘柄の良さをまずはご実感ください。
▼プロが選んだ3銘柄を無料でご提案▼
執筆者情報
日本投資機構株式会社 証券アナリスト(CMA) テクニカルアナリスト(CMTA®)
総合鉄鋼メーカーに勤務していた経験を活かした、鉄鋼・自動車市場の分析及び情報収集を得意とし、データの集計・分析に基づいた統計学により銘柄の選定を行う希少なデータアナリスト。AIに関する資格も有しておりデータサイエンティストとしても活躍の場を拡げている。

![Invest Leaders[インベストリーダーズ]](https://jioinc.jp/investleaders/wp-content/uploads/2025/07/logo_01.png)