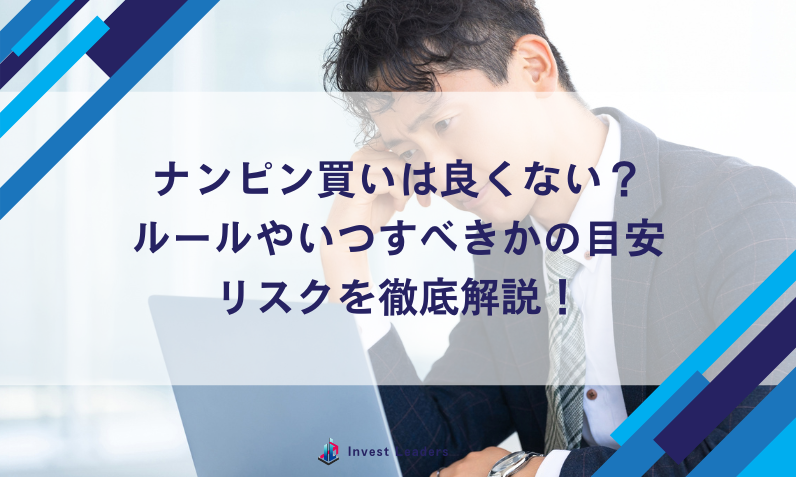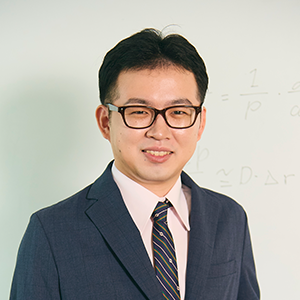株価が下がったとき、あなたはどうしますか?
多くの投資家が悩む局面で選択肢の一つとなるのが「ナンピン買い」です。これは下落した銘柄を追加で買い増しし、平均取得単価を下げて損益分岐点を引き下げる手法。
しかし「危険」「やめた方がいい」とも言われます。本記事では、ナンピン買いの仕組みやメリット・デメリット、失敗しやすいケース、成功させるための条件まで具体例を交えて徹底解説します。
ナンピン(難平)買いは買い増し手法のひとつ

ナンピン(難平)買いとは、保有している株式の株価が購入時よりも下落した際に、その銘柄を追加で買い増しする投資手法です。
買い増しによって、1株あたりの平均取得単価を引き下げることを目的に行われます。
例えば、1株1,000円で買った株が800円に値下がりした時、同じ株数を800円で買い増すと、平均取得単価は900円になります。
これにより、株価が元の1,000円まで回復しなくても、901円以上に値上がりした時点で利益が出る状態になり、損益分岐点を有利にできるのが基本的な考え方です。
ナンピン買いの由来
ナンピン買いの「ナンピン」は、「難平」と書き、「難(なん)を平(たい)らにする」という言葉が語源とされています。
ここでの「難」とは、購入時より株価が下落し、評価損を抱えた含み損の状態を指します。
そして「平らにする」とは、追加の買い入れによって平均取得単価を下げ、損失をならすという意味合いです。
江戸時代の米相場といった古くからの取引で使われていたと言われています。
価格が下がった商品を買い増すことで、相場が回復した時に利益を出しやすくするという、投資戦略のひとつです。
ナンピン買いの計算方法|平均取得単価をわかりやすく解説
ナンピン買い後の平均取得単価は、簡単な計算で求められます。
計算式は「合計の購入金額 ÷ 合計の保有株数」です。
具体例で見てみましょう。
ある銘柄を1株1,000円で100株(購入金額10万円)で購入したとします。
その後、株価が1株800円に下落したため、
ナンピン買いとして100株を追加購入(追加購入金額8万円)しました。
この場合、合計の購入金額は10万円+8万円=18万円、
合計の保有株数は100株+100株=200株となります。
したがって、平均取得単価は【18万円 ÷ 200株 = 900円】となります。
これにより、損益分岐点は1,000円から900円に引き下がり、より少ない株価の回復で利益を狙えるようになります。
ナンピン買いの逆は「売り増し」や「ピラミッティング」
ナンピン買いが「含み損が出ている銘柄を買い増す」行為であるのに対し、逆の戦略は「含み益が出ている銘柄を買い増す」ことです。
この代表的な手法がピラミッティングです。これは、株価が予測通りに上昇し、利益が出ている状況でさらに買い増しを行い、利益の最大化を狙う攻めの手法です。
買い増し額を徐々に減らしていく形がピラミッドに似ていることから名付けられました。
また、「売り」の世界でのナンピンは売り増しと呼ばれます。
これは空売りした銘柄の価格が予想に反して上昇した場合に、さらに高い価格で空売りを追加し、平均売建単価を引き上げる行為です。
ナンピン買いとドルコスト平均法、押し目買の違い

ナンピン買いとドルコスト平均法の違い
ナンピン買いは、保有中の株が下落し含み損を抱えた際に、平均取得単価を下げることを目的として追加購入する手法です。
一方、ドルコスト平均法は株価の上下に関係なく「一定の金額を定期的に買い続ける」手法で、そもそもの目的が資産形成や長期積立にあります。
つまり、ナンピン買いは「含み損を抱えた際の防御的な行動」、ドルコスト平均法は「価格変動リスクを平準化する長期戦略」という点が明確に異なります。
[関連]ドルコスト平均法とは?メリット・デメリットやシュミレーション結果を解説
ナンピン買いと押し目買いの違い
押し目買いは、上昇トレンドにある銘柄が一時的に調整で下落したタイミングを狙い、将来的な上昇を見込んで追加投資する手法です。
これに対し、ナンピン買いはすでに保有している株が下落し、含み損を抱えた状況でに買い増しを行う手法であり、目的は平均取得価格を引き下げることにあります。
押し目買いは「上昇を予測して買う」のに対し、ナンピン買いは「下落への対処として買う」という点で大きく異なります。
[関連]押し目買いとは?失敗しない判断基準・ポイントをテクニカルアナリストが徹底解説
ナンピン買いのメリット

ナンピン買いの最大の魅力は平均取得単価を引き下げ、その後の投資展開を有利にできる点にあります。
株価の下落は通常ピンチですが、ナンピン買いが成功すれば、それをチャンスに変えることができます。下落が一時的で、その後株価が力強く反発する局面では、ナンピン買いは非常に強力な武器となります。
結果的に、下落局面で安く多くの株を仕込めたことになり、株価が少し回復しただけでも利益に転じやすくなるのです。
ただし、これはあくまで「株価が回復する」という前提が成功した場合の話です。
下落が止まらず、損失を拡大させてしまうリスクも常に念頭に置く必要がありますが、上手くいけば大きなリターンを狙えるのがナンピン買いのメリットと言えるでしょう。
平均取得単価を下げ、損益分岐点を引き下げられる

ナンピン買いの最も基本的かつ最大のメリットです。
最初に1株1,000円で購入した株が800円に下落した場合、損益が±0ゼロになるには株価が1,000円に戻るのを待たなければなりません。
しかし、800円で同数のナンピン買いを行えば平均取得単価は900円に下がります。
この結果、株価が901円以上に回復すれば利益に転換するため、当初の買値まで回復を待つ必要がなくなります。
損益分岐点が下がれば、投資家にとって大きな精神的な安心感にも繋がります。
ただし、あくまで損益分岐点となる価格が下がるだけであり、含み損の金額自体が少なくなる訳ではありません。
株価回復時に大きな利益を狙える

ナンピン買いは、守りの手法と見られがちですが、成功すれば攻めの効果も発揮します。
なぜなら、結果的に「株価が安い時に多くの株数を仕込めた」ことになるからです。
もし予測通りに株価が反発し、最初の購入価格以上に上昇した場合、ナンピン買いで追加購入した分の株式が大きな利益を生み出します。
例えば、1,000円で買った株を800円でナンピンした後、株価が1,200円まで上昇したとします。
この時、ナンピンしなかった場合に比べて保有株数が多いため、得られる利益の総額はより大きくなります。
高配当株投資、長期投資との相性が良い

ナンピン買いは、特に高配当株投資や、長期的な成長が期待される銘柄への投資と相性が良いとされています。
高配当株の場合、たとえ株価が下落して含み損を抱えても、定期的に配当金を受け取れるため、精神的な支えになります。
さらに、利益に対する配当の割合を示す「配当性向」が健全な水準にあれば、配当が無理なく維持される可能性が高く、下落局面でも安心して保有しやすい点も魅力です。
ナンピン買いで保有株数を増やせば、受け取る配当金の総額も増加するため、株価が回復するまでの期間を耐えやすくなります。
また、長期的に成長すると期待できる優良企業であれば、一時的な市場の動揺による株価下落は、むしろ「優良株を安く買い増せる絶好の機会」と捉えることができます。
ナンピン買いが「ダメ」「良くない」とされる理由と失敗例

便利なようで危険も多いナンピン買い。その甘い響きの裏には、損失を無限に拡大させかねない大きなリスクが潜んでいます。
計画性のない感情的なナンピンは、投資家を再起不能な状況に追い込む「最悪の手」とさえ言われます。
下落トレンドが続く銘柄において損失を致命的に拡大させる

株価の下落には必ず理由があり、その根本的な原因(業績悪化や市場構造の変化など)が解決されない限り、株価は回復しません。「安くなったから」というだけの理由での買い増しは、底なし沼に自ら足を踏み入れるようなものです。
実際に、コロナ禍後の巣ごもり需要で急騰したあるIT系グロース株に高値で投資し、その後の金融引き締めで株価が下落し始めたお客様の例を挙げると、彼は「あの時の勢いはいずれ戻るはず」と信じ、株価が半値、さらにその半値になるまでナンピンを続けました。
しかし企業の成長鈍化は明らかで株価は一向に回復せず、最終的に投資資金の8割を失った状態でご相談に来られました。まさに地獄でした。
貴重な投資資金を長期間塩漬けにし、機会損失を生む

ナンピンを繰り返すことで特定の銘柄への投資額が膨れ上がり、その資金が拘束され、その結果、他に現れた有望な投資機会をみすみす逃すことになります。含み損を抱えた銘柄は心理的にも売却しづらく、ポートフォリオ全体が機能不全に陥ります。
こちらも例を挙げると、かつての花形企業だった大手電機メーカーの株を、構造改革への期待から購入したお客様がいました。株価が低迷するたびに「日本の技術力はこんなものではない」とナンピンを繰り返し、10年近くも保有し続けました。
その間、他の成長企業が次々と現れましたが、資金の大部分がその銘柄に固定されていたため、新たな投資ができませんでした。「あの資金があれば…」という後悔の言葉が今も忘れられません。
[関連]株の塩漬けは悪くない?個人投資家が塩漬けをして復活&損失拡大した実例を紹介
投資家の正常な判断力を奪い、精神を極度に疲弊させる
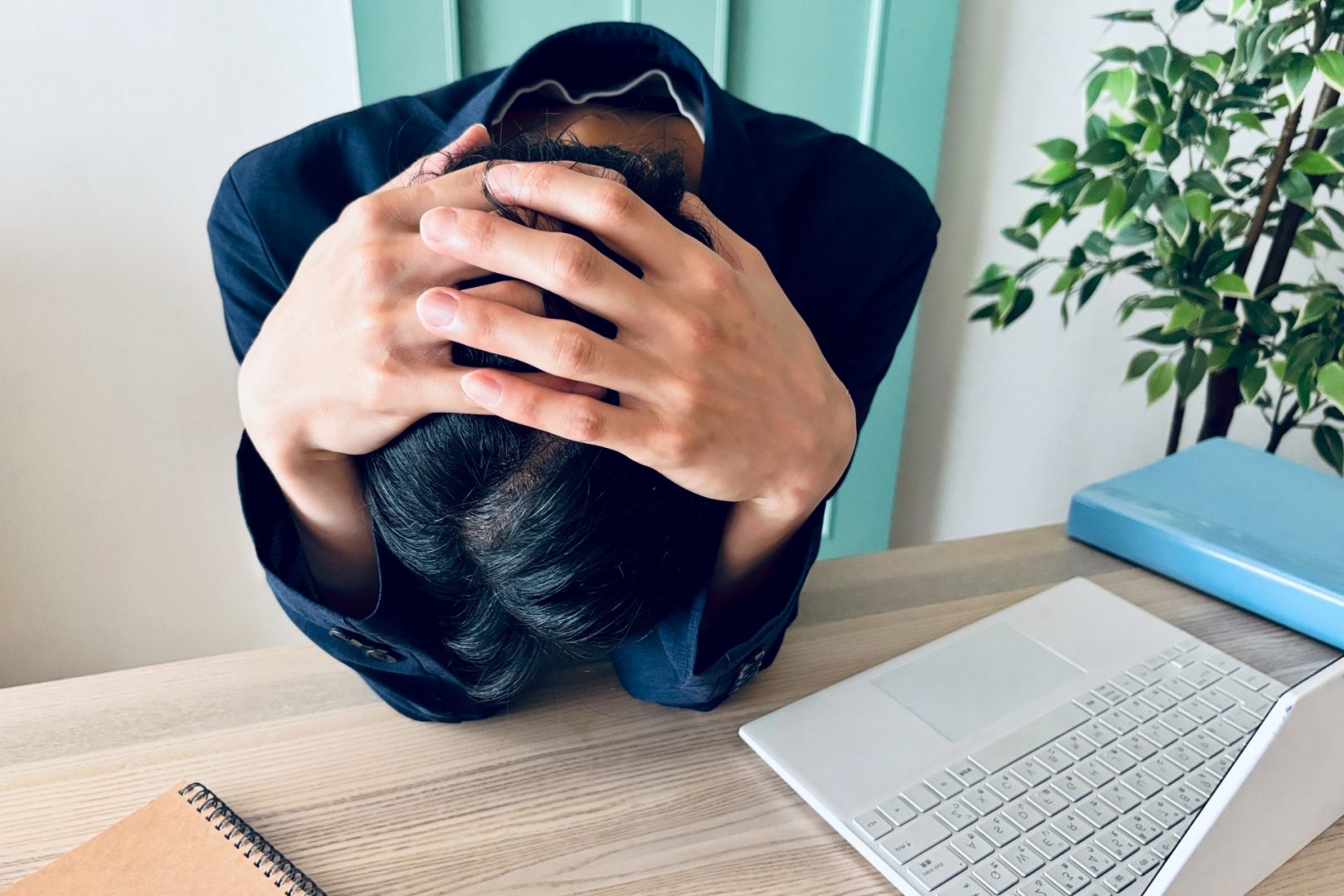
含み損が日々拡大していく状況は、冷静な判断を著しく困難にします。「損を取り返したい」という焦りや、「ここまで投資したのだから今さら引けない」という固執(コンコルド効果)が、さらなるナンピンという非合理的な行動を誘発します。
あるお客様は、新興バイオ企業の将来性に賭けて投資しましたが、臨床試験の失敗で株価が暴落しました。
彼は「IRに電話しても『頑張ります』と言っていたから」と希望を捨てきれず、下がるたびに貯金を切り崩してナンピンを続けました。
毎日株価に一喜一憂し、夜も眠れず、仕事にも集中できなくなったそうです。
お金だけでなく、大切な時間と精神的な平穏まで失ってしまった痛ましいケースでした。
私たちが個人投資家の方からよく相談を受ける失敗例で最も多いのが、「下がるたびに買い続け、気づけば投資資金の大部分を一つの銘柄に注ぎ込んで身動きが取れなくなった」というケースです。
これは、株価はいずれ回復するという希望的観測にすがり、損切りという重要な決断を先延ばしにした結果です。
企業の業績悪化など、下落に明確な理由がある場合、ナンピンは傷口に塩を塗る行為に他なりません。
ナンピン買いが成功しやすい人・失敗しやすい人の特徴

ナンピン買いは、その効果とリスクの大きさから、すべての投資家に適した手法ではありません。
これから解説する特徴を参考に、自分がナンピン買いを武器にできるタイプなのか、それとも避けるべきタイプなのかを見極めましょう。
戦略的にナンピンを活用できる人の特徴

戦略的にナンピンを成功させられる人には、以下の4つの特徴があります。
資金管理能力が徹底している
ナンピンは、追加投資を前提とした手法であるため、資金配分を明確に設計できる人ほど成功しやすい傾向があります。
「この銘柄に投じる総額は資産の○%まで」「ナンピンは最大〇回まで」「1回あたりの追加投資額は初回の○%」など、事前に上限を決めておくことで、予期せぬ価格変動が起こっても冷静な対応が可能。
徹底した資金管理ができる人ほど、ナンピン買いは有効な戦略となるでしょう。
客観的な分析力と事前ルールがある
株価が下落した理由を感情ではなく、データに基づいて判断できる人は、ナンピン買いを成功させる可能性が大きく高まります。
「決算内容の悪化なのか」「市場全体の下落なのか」「一時的な過剰反応なのか」を冷静に見極め、企業価値に問題がないと判断できたときのみナンピン買いに踏み切れるからです。
さらに「株価が○%下落したら1回目」「業績に変化があったらナンピンしない」など、明確なルールを設定できる人ほど、感情的なナンピン買いの罠にはまりません。
強靭な精神力を持っている
ナンピン買いを行う局面は、多くの場合、含み損が増えて心理的に追い込まれやすいタイミングです。
株価の下落が続くと、「このままさらに落ちるのでは?」「判断を誤ったのでは?」と不安が募り、冷静さを失いがちになります。
しかし、ナンピン買いを成功させる投資家はこうした場面でも動揺せず、事前に定めたルールや分析を信じて落ち着いて行動できます。
短期的な値動きに振り回されず、自分の戦略を一貫して実行できるメンタルの強さがあるからです。ナンピン買いを使いこなすには、まさにこの「強靭な精神力」が欠かせない要素と言えるでしょう。
自分なりの取引方法を確立している
経験豊富で、自分の得意な投資スタイルや判断基準を把握している投資家ほど、ナンピン買いを「戦略の一部」として取り入れやすくなります。
逆に明確な基準がないまま感覚で売買していると、ナンピン買いは「損失を追いかけるだけの危険な行動」になりかねません。
自分なりのスタイルを確立していることは、ナンピン買いを成功させるうえで欠かせない条件です。
感情に流されやすく資金管理が苦手な人にナンピンは逆効果
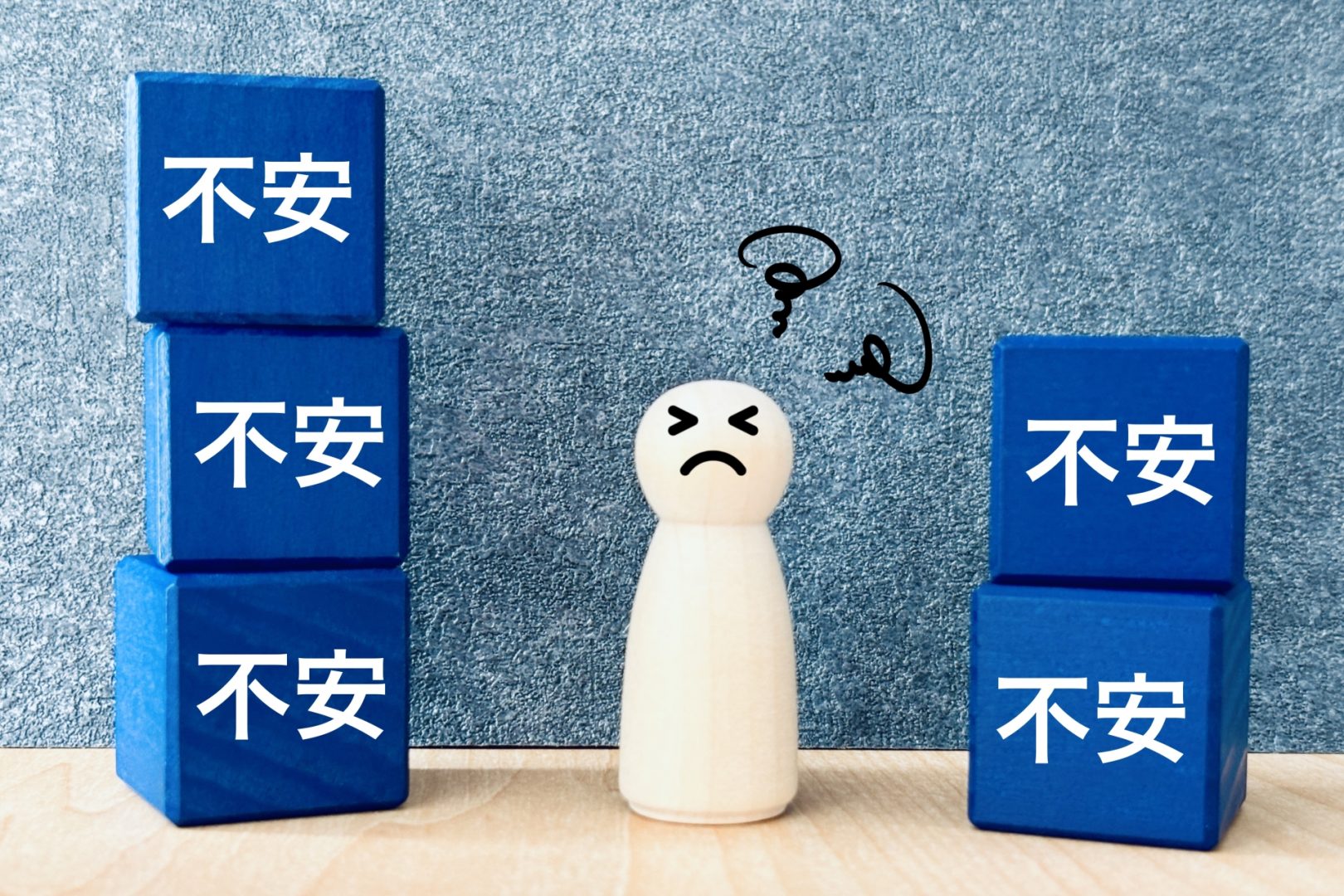
ナンピン買いが大きな失敗に繋がりやすいのは、メンタルが弱く資金管理が苦手な人です。
こうしたタイプの人は、株価が下落すると「早く損失を取り戻さなくては」という焦りから、衝動的にナンピンに手を出してしまいます。
さらに下落が続くと冷静さを失い、投げやりになって、許容範囲を超えた資金を投じてしまう危険があります。
「損失を取り返すためのナンピン」という考えになってしまう時点で、ナンピン買いには向いていません。
ナンピン買いは「上昇するシナリオが崩れていない」という前提で行うものです。
「上昇するシナリオが崩れていない」のであれば「損失を取り返す」ではなく「利益を増やすため」のナンピンと考えるはず。
また、「損失を取り戻す」という考え方で投資をしてしまうと、損切を行うことができなくなる可能性が高くなってしまいます。
そうなると、ただ単に傷口を広げただけという結果になってしまうため、想定シナリオから外れた売却をするようにしましょう。
ナンピン買いをすべきタイミングの目安やコツを解説

ナンピン買いの成否は、そのタイミングに大きく左右されます。単に「株価が下がったから買う」という安易な考えでは、失敗する確率が非常に高くなります。
ナンピンはいつでも使える万能薬ではありません。
適切なタイミングを見極めることが最も重要なコツです。それでは実際にどのような時に行うことが効果的かを解説していきます。
市場全体の暴落による「連れ安」のとき
個別の企業に悪材料が出たわけではなく、リーマンショックやコロナショックのような経済危機、地政学リスクの高まりなどで株式市場全体が暴落する場面があります。
このような時、優良企業の株価も本質的な価値とは無関係に、パニック売りによって大きく下落することがあります。
こうした「連れ安」は、長期的に成長が見込める優良株を安く買い増す絶好の機会であると言えるでしょう。
下落の原因がその企業自身にないため、市場が落ち着きを取り戻せば、株価も回復する可能性が高いと考えられるからです。
企業の貸借対照表や損益計算書などを確認し、ファンダメンタルズに問題がないことをしっかり見極めた上で実行するのが大前提です。
[関連]貸借対照表(バランスシート)とは?投資家初心者が企業価値とリスクを見抜く読み方を解説
[関連]損益計算書(P/L)とは?投資初心者が押さえておきたい決算書の見方をアナリストが解説
長期的な成長ストーリーに変化がないとき
短期的な需給の悪化や、決算の数字が市場予想にわずかに届かなかった等の理由で株価が下落する場合があります。
この時、企業の長期的な成長シナリオを揺るがすような変化がない場合は、「買い場」と捉えることができます。
企業の成長シナリオを信じられるのであれば、ナンピン買いによって平均取得単価を下げることで、大きなリターンを狙えます。
ナンピン買いを入れる目安となる株価の下落率
「株価が何%下がったらナンピンすべきか」の答えは投資家個々人によって異なります。
なぜなら、投資家の資金量、リスク許容度、投資対象の銘柄の性質などの様々なことが影響するからです。
目安として「最初の買値から15%下落したら1回目、さらにそこから20%下落したら2回目」といったルールを設ける投資家もいますが、これはあくまで一例です。
自分の総投資額と照らし合わせ、「最大で何回、どの株価水準で買うか」というシナリオを事前に決めておきましょう。
新NISAでナンピン買いをする際の注意点

非課税メリットを活かした長期的な資産形成を目的とする新NISAは、原則としてナンピン買いと相性が良いと言えます。
特に、長期的な成長が期待できる銘柄やインデックスファンドが下落した際に買い増しをすれば、非課税の恩恵を受けながら将来のリターンを高める効果が期待できます。
しかし、重大な注意点があります。NISA口座は損益通算や繰越控除ができません。
もしナンピン買いに失敗して最終的に損失が確定した場合、その損失を他の課税口座の利益と相殺することができず、自己負担となります。
課税口座以上に慎重な銘柄選定と、計画的な資金管理が求められます。
投資信託やインデックスをナンピン買いをする場合
S&P500や全世界株式などのインデックスファンド、あるいは広く分散された投資信託へのナンピン買いは、個別株に比べてリスクが低いとされています。
市場全体に投資しているため、倒産などで価値がゼロになるリスクが極めて低いからです。
これらは長期的に右肩上がりの成長を遂げてきた歴史があるため、市場全体が下落した局面での買い増しは、将来の資産を増やすための有効な戦略と言えます。
これは実質的にドルコスト平均法と似た考え方ですが、暴落時などにスポットで多めに買い増すことで、より効率的に平均取得価額を下げることが期待できます。
あくまで短期的な回復を狙うのではなく、長期目線で実行することが重要です。
新NISAの成長投資枠でナンピン買いする場合
年間240万円という大きな非課税枠を持つ成長投資枠では、個別株へのナンピン買いを検討する機会も増えるでしょう。
非課税のメリットを最大限に活かすため、下落時に安く買い増し、株価回復時の利益をまるごと非課税にしたいと考えるのは自然なことです。
しかし、ここでも「損益通算ができない」というNISAのデメリットが重くのしかかります。
ナンピンした銘柄の株価が回復せず、最終的に損切りした場合、その損失は他の利益と相殺できず、非課税投資枠の一部を失ってしまいます。
成長投資枠でナンピンを行う際は、最悪の場合でも損失が許容範囲内に収まるように資金管理を徹底することが必要です。
[関連]新NISAの成長投資枠は何を買う?個別株の注意点とおすすめ活用術を解説
よくあるQ&A|ナンピン買いの疑問を解決
ナンピン買いは「資金」「心理」「タイミング」を徹底したうえで行おう!
ナンピン買いは、使いどころを誤らなければ、下落相場をチャンスに変え、将来の利益を増やすことできます。
しかし、その一方で、損失を拡大させてしまう可能性のある「諸刃の剣」です。
「資金」「心理」「タイミング」の3要素を冷静に管理できるかにかかっています。
下落の原因を客観的に分析し、ルールに従って取引ができる投資家にとっては有効な戦略となります。
自分の投資スタイルと性格を深く理解し、この手法と冷静に向き合うことが何よりも重要です。
アナリストが選定した銘柄が知りたい!
今なら急騰期待の“有力3銘柄”を
無料で配信いたします
買いと売りのタイミングから銘柄選びまで全て弊社にお任せください。
投資に精通したアナリストの手腕を惜しげもなくお伝えします。
弊社がご提供する銘柄の良さをまずはご実感ください。
▼プロが選んだ3銘柄を無料でご提案▼
執筆者情報
日本投資機構株式会社 証券アナリスト(CMA) テクニカルアナリスト(CMTA®)
総合鉄鋼メーカーに勤務していた経験を活かした、鉄鋼・自動車市場の分析及び情報収集を得意とし、データの集計・分析に基づいた統計学により銘柄の選定を行う希少なデータアナリスト。AIに関する資格も有しておりデータサイエンティストとしても活躍の場を拡げている。

![Invest Leaders[インベストリーダーズ]](https://jioinc.jp/investleaders/wp-content/uploads/2025/07/logo_01.png)