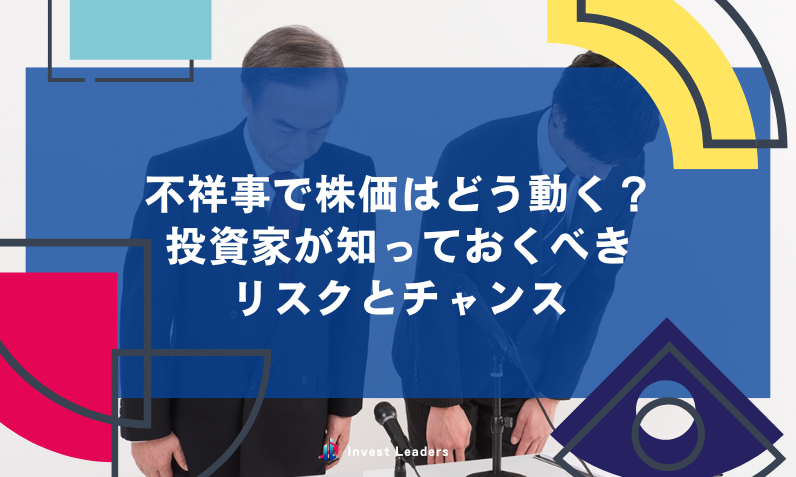企業の不祥事は、株価を大きく動かす重要な要因のひとつです。
粉飾決算や製品トラブル、情報漏えいなど不祥事が発覚した場合、売りが殺到し株価が急落するケースも少なくありません。
しかし、その後の企業対応や事業構造によっては、株価が回復に向かうケースもあります。
本記事では不祥事が株価へ与える影響や、実際の事例から投資家が知っておくべきリスクとチャンスを解説します。
企業の不祥事とは

企業の不祥事とは、法令違反や社会的規範に反する行為、あるいは企業倫理を欠いた行動によって、社会的信用を失う事態のことです。
不祥事を起こすと株主や顧客、取引先からの信頼が失われ、業績やブランドなどに様々な悪影響を及ぼします。
また近年では、情報管理の甘さやガバナンス不備など、表面的な問題だけでなく組織体質そのものの問題が問われるケースも増加しています。
企業が起こす主な不祥事の種類
企業が引き起こす不祥事には、さまざまな形があります。
以下のようなケースはいずれも、株価下落や経営悪化につながる重大なリスク要因となります。
・横領
・情報漏えい
・不適切な会計処理
・品質データ偽装
・ハラスメント など
こうした不祥事は一見すると個別の問題に見えますが、内部統制の甘さや経営陣のチェック体制の不備など、構造的かつ根本的な原因を抱えているケースも少なくありません。
不祥事が株価へ与える影響

企業が不祥事を起こすと、株式市場や業績、さらにはブランド価値にまでさまざまな影響が及びます。
ここからは、その主な影響と株価への影響を解説していきます。
信用失墜による売り圧力の増加
企業が不祥事を起こすと市場の信頼が急速に失われ、投資家の間で売りが先行します。
株式市場において「信用」は企業の評価や株価に直結する重要な要素なので、信用の崩壊は即座に株価下落につながります。
特に発表直後は不安心理が広がり、損失回避を目的に保有株を手放す動きが加速。業績への影響が明確でなくても、「リスクを織り込む」形で売り圧力が強まるのが一般的です。
投資家・顧客離れによる業績悪化懸念
企業の不祥事は株主だけでなく、顧客や取引先の信頼にも影響を及ぼします。
企業の信用が揺らぐと顧客が商品やサービスの利用を控え、取引先が新規契約を見送るなど、売上減少のリスクが高まります。
場合によっては取引停止や契約解除が発生し、短期的な損失が膨らむケースも。
その結果、業績の先行きが不透明になり、投資家の間で「業績悪化懸念」が広がることで、株価下落に拍車がかかる可能性があります。
経営陣の退任・改革による一時的な不透明感
不祥事後は責任を取る形で経営陣が退任し、企業体制が大きく変わることが多いです。
これは信頼回復への重要なステップですが、短期的には「誰が次の舵を取るのか」「方針はどう変わるのか」といった不透明感を市場に与えてしまいます。
投資家は改革の実効性を慎重に見極めようとするため、株価は一時的に停滞、あるいは軟調に推移する可能性が高いです。
長期的なブランド価値への打撃
不祥事は単なる一時的トラブルではなく、長期的なブランド価値の毀損という形で企業に影響を残します。
その影響は多岐にわたり、顧客離れや市場シェアの低下など、様々な形で企業の競争力を弱める可能性も。
ブランドの回復には数年を要する場合も多く、その間は株価が割安に放置されやすい傾向があります。
不祥事を起こした企業の株価事例

実際に不祥事を起こした企業の株価は、その内容や対応によって大きく異なる動きを見せます。
ここからは、過去の具体的な事例をもとに、不祥事発覚後に株価がどのように変化したのかを見ていきましょう。
フジ・メディア・ホールディングス(4676)

フジ・メディア・ホールディングスは2024年12月20日に芸能関連トラブルが報道されて以降、1,848円だった株価が急落し、2025年1月16日には約1,616円まで下落。
しかしその後、米国投資ファンドであるダルトン・インベストメンツが株式を保有し、経営改革を求める書簡を提出したことで、ガバナンス改善への期待が急速に高まりました。
さらに、同社が保有する不動産や株式などの含み資産に注目が集まり、「改革が進めば企業価値が大きく見直される」との見方が広がりました。
こうした動きを背景に投資家の買いが強まり、2025年4月には株価が約3,433円台まで大きく上昇。
この事例は不祥事発覚による株価下落から、外部の圧力や経営改革への思惑が株価回復の起点となりうるという典型的なストーリーを示しています。
[関連]【株価急上昇とトラブルの裏側】 フジ・メディアホールディングスの未来を探る
オルツ(260A)
AI開発企業のオルツは、2025年8月31日付で東京証券取引所グロース市場から上場廃止となりました。
原因は、2021年12月期から2024年12月期までの間に、実態のないライセンス契約を通じて売上を過大計上していたことが発覚したため。
調査の結果、売上高の最大9割が架空計上だったとされ、経営陣による組織的な不正会計が明らかになりました。
不正発覚後の株価は急落。2025年7月30日から整理銘柄に指定されたことで、個人投資家の投げ売りが加速しました。
さらに再上場や事業継続の見通しも立たず、株式は最終的に無価値化。まさに「事件は売り」を象徴する事例と言えるでしょう。
不祥事発覚後の株価の動き方

ここからは不祥事発覚後の株価の動き方について解説します。
不祥事発覚後に株価が回復しにくいケース
不祥事の内容が企業の根幹を揺るがすような「事件」であった場合、株価が回復せず長期低迷に陥るケースが多々あります。
特に、組織ぐるみでの粉飾や隠蔽が明らかになると、投資家の信頼回復には時間を要し、回復見込みが立たないと判断されると株価は急落。
また事後対応が遅い、または責任所在が不明確な企業は、市場が「次に何が出てくるか分からない」と警戒を強め、株価は値を戻せず低迷が長期化しがちです。
さらに、ネガティブな情報が断続的に出ると投資家心理はさらに悪化し、「見切り売り」対象となることがあります。
不祥事発覚後に株価が回復しやすいケース
不祥事発覚後に株価が回復しやすいのは、発覚した問題の深刻度が比較的軽く、企業本来の事業や競争力への影響が少ない「事故型」のケースです。
また、企業が迅速かつ誠実に謝罪・対応を行い、再発防止策を明確に打ち出した場合、投資家の信頼を早期に回復できる可能性があります。
このような状況では、株価も下落後短期的に下げ止まり、数か月〜1年程度で反発することも見られます。
不祥事が発覚した銘柄は「買い」か「見送り」か

投資の世界には「事故は買い、事件は売り」という格言があります。
突発的なトラブルなどの事故であれば、一時的に株価が下落しても、信頼回復によって再び上昇が見込めるため、中長期的には「買い」のチャンス。
一方、組織ぐるみの粉飾や不正といった事件の場合は、業績やブランドに長期的な悪影響を及ぼし、「見送り」または「売り」と判断されることが多いです。
もっとも、この格言は株式市場における経験則のひとつであり、この格言が必ずしも当てはまるわけではありません。
たとえ「事件」に分類されるような不祥事でも、経営陣の迅速な対応や再発防止策の実効性、事業自体の競争力によっては、株価が再び上昇基調に転じることもあります。
不祥事銘柄への投資を検討する際は、短期的な感情やニュースの衝撃に流されず、その出来事が業績に与える影響の大きさと、企業の回復力を冷静に見極めることが大切です。
不祥事銘柄への投資を検討する際の注意点

不祥事を起こした企業への投資は、リスクとチャンスが表裏一体です。ここでは、投資判断を下すうえで押さえておきたい注意点を紹介します。
集中投資は避ける
不祥事が明らかになった直後は株価の変動が激しく、情報の不確実性が高い局面と言えます。
このような場面で集中投資をすることは非常にリスクが高く、評価が固まらないうちに想定外の悪材料が出た場合には短期間で大きな損失を被る可能性があります。
したがって、段階的に買い進める「分散投資」が望ましいです。株価の動きを見ながら少しずつ買い進め、企業の対応や業績の回復状況を確認して追加投資を判断することで、リスクを抑えながら投資ポジションを整えていくのが良いでしょう。
長期的な視点を持つ
不祥事をきっかけにした株価の変動は、短期的な下落だけでなく、その後の「信頼回復までの時間」に大きく左右されます。
目先の値上がりを狙うのではなく、数年単位で企業の再建やブランドの立て直し、業績の回復を見守る姿勢が大切です。
実際、株価が下げ止まり、回復に転じるまでには半年から1年以上かかることも少なくありません。
そのため「短期の急騰狙い」ではなく、「回復の流れに乗る」という長期的な視点を持つことが重要です。
企業の動向を注視する
企業の動きを注意深く観察することも、不祥事後の投資判断では重要です。
発覚後の対応スピードや説明の丁寧さ、再発防止策の実効性、さらには次の事業展開の進み具合などが、企業の信頼回復の鍵を握ります。
そのためIR情報や決算資料などを通じて、経営陣の入れ替えや内部管理体制の改善、主要取引先や顧客の動向を継続的に確認しましょう。
また状況が変わるたびに投資方針を柔軟に見直す姿勢が、リスクを抑えながら利益を狙ううえで大切です。
銘柄の不祥事リスクを見抜くためのポイント

不祥事リスクを見抜くには、「なんとなく怪しい」という直感に頼るだけでは不十分です。
実際には、財務内容・経営体制・企業文化・過去の履歴などといった複数の観点から、客観的に分析することが重要。
ここからは、不祥事リスクを事前に察知するために注目すべきポイントを見ていきましょう。
財務諸表の分析
不祥事リスクを事前に察知するためには、貸借対照表や損益計算書、キャッシュ・フロー計算書などの財務諸表で、異常値や不整合がないかをチェックする必要があります。
例えば、売上が急増しているのにキャッシュフローが伴わない、在庫が急増している、販管費が不自然に増加しているといった兆候は、将来の不正や経営トラブルの前触れとなる可能性があります。
数字の裏に隠れた「無理な成長」や「見せかけの売上」を疑う視点がリスク軽減に大きく寄与します。
ガバナンス体制・内部統制の確認
企業が不祥事を防ぐには、取締役会や監査役、社外取締役が適切に機能していることが大切です。
特に、経営陣が責任を取る姿勢を持っているか、社外取締役が経営から独立した客観的な意見を言えるか、監査法人の頻繁な変更はないかなどをチェックしましょう。
ガバナンス(企業統治)が弱い企業は、不祥事が起きやすく、投資家からリスクの高い銘柄として見られやすい傾向があります。
企業文化と外部情報の確認
企業内の文化や風土も、不祥事リスクを見抜く上で重要なヒントです。
たとえば過度な成長志向や不適切な情報開示、トップの異様なメディア露出など、内部統制が効いていない可能性を示す「雰囲気」があります。
またSNSや業界ニュース、社内関係者の発信をチェックすることで、表面的なIR資料だけでは把握できない情報を掴むことができます。
過去のトラブル履歴の確認
企業が過去にどんなトラブルを抱えてきたかは、将来のリスクを見抜くうえで重要な判断材料です。
たとえば、品質問題や労働問題、会計の不正疑惑などを起こした企業が、根本的な原因を解決できていない場合、再発のリスクを抱えている可能性があります。
過去の不祥事を踏まえて、どの程度改善が進み、再発防止策が機能しているかを確認することが、将来的な株価下落リスクを抑えるポイントになります。
まとめ
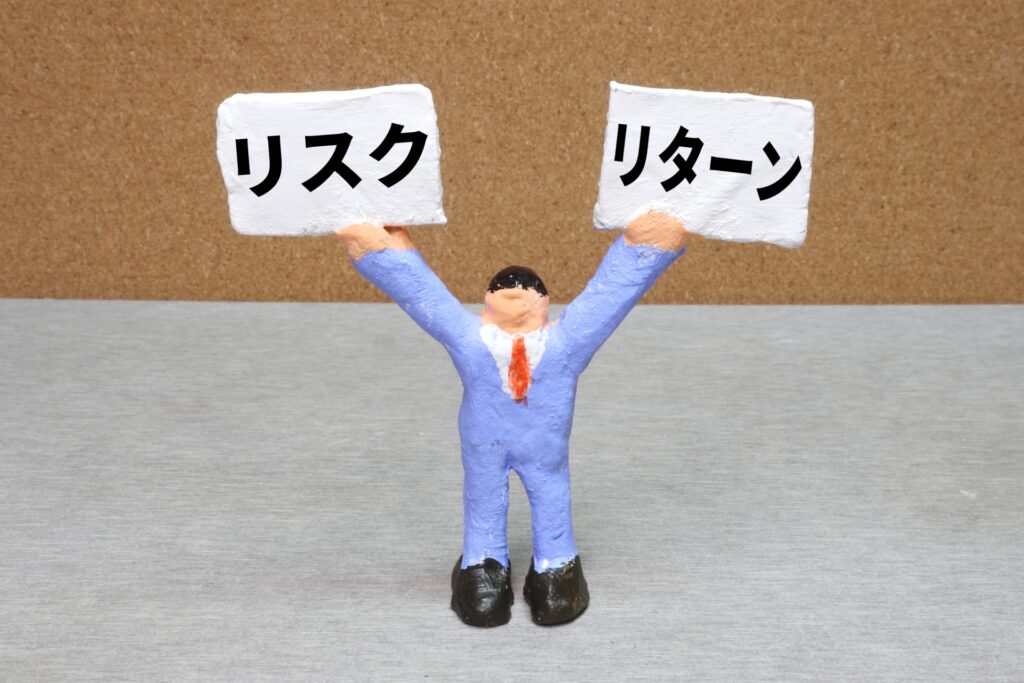
不祥事が発覚した企業の株に投資することは、他の銘柄に比べてリスクが高く、一筋縄ではいかないものです。
業績への影響や問題の深刻さを正しく見極め、致命的なものでないと判断できる場合に限り、押し目買いのチャンスを逃さずに捉えることが重要です。実際、過去の事例の中には株価が10倍に上昇した(テンバガー)銘柄も存在します。
株式投資とは企業の本来の実力を見極め、現在の株価が割安か割高かを判断するものです。不祥事によって市場の期待と不安が一気に剥がれ落ちることで、企業の本質がより鮮明に見えることがあります。
これ以上に下がりにくい水準まで売り込まれた株や、実力に対して過剰に下落した銘柄を仕込むのは、株式投資における有効な戦略のひとつ。もちろん「絶対に下がらない株」は存在しませんが、それに近い銘柄を見極めることは可能です。
投資家として事の真相を見極める力を養い、未来の可能性を見極めるための手段として活用してみてはいかがでしょうか。
アナリストが選定した銘柄が知りたい!
今なら急騰期待の“有力3銘柄”を
無料で配信いたします
買いと売りのタイミングから銘柄選びまで全て弊社にお任せください。
投資に精通したアナリストの手腕を惜しげもなくお伝えします。
弊社がご提供する銘柄の良さをまずはご実感ください。
▼プロが選んだ3銘柄を無料でご提案▼
執筆者情報
日本投資機構株式会社 テクニカルアナリスト(CMTA®)
著名な元機関投資家や経験豊富なアナリスト・ファンドマネージャーより培った知識と経験を基に、数多くの市場動向の予測や個別銘柄の動向をピンポイントで分析。銘柄の推奨実績において社内の月間最高勝率記録を持つテクニカルアナリスト。

![Invest Leaders[インベストリーダーズ]](https://jioinc.jp/investleaders/wp-content/uploads/2025/07/logo_01.png)