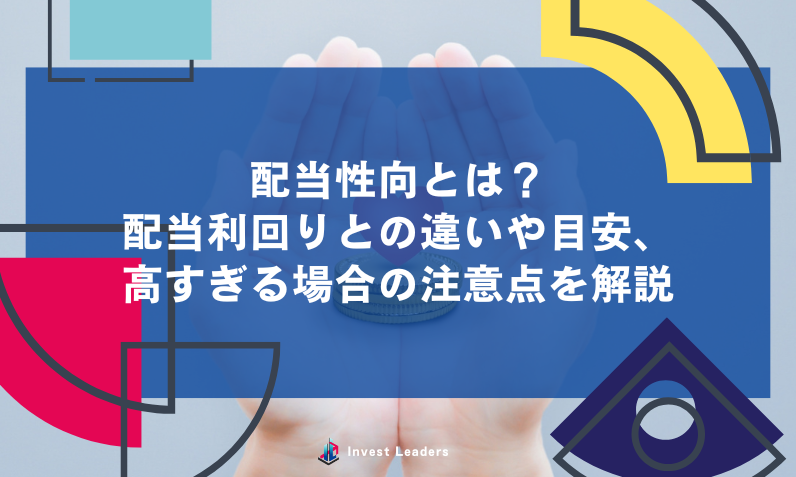配当の健全性や安定性を分析する際に、必ず知っておきたい指標が「配当性向(はいとうせいこう)」です。
配当性向は、企業が稼いだ利益のうち、どれくらいの割合を配当にあてているかを示します。
この記事では、配当性向の基本や具体的な計算式、投資で役立つ目安、高すぎる場合の注意点などを初心者の方にもわかりやすく徹底的に解説します。
配当性向とは?意味や重要性をわかりやすく解説

配当性向とは、企業が当期純利益(税金などを引いた後に最終的に残った利益)の中から、どれだけの割合を配当金として株主に支払ったかを示す指標です。
英語表記ではDividend Payout Ratio (DPR)と呼ばれます。
企業が稼いだ利益は、主に「配当金として株主に還元する」か「企業内部に留保し、将来の事業拡大や財務基盤強化に使う」かのどちらかに振り分けられます。
配当性向は、このうち「株主還元」の割合を表しています。
例えば、配当性向が30%であれば、「企業が稼いだ利益の30%を配当金として支払い、残りの70%は社内に留保している」ことを意味します。
配当性向はなぜ投資家にとって重要なのか
配当性向を見ると、その企業の株主還元や経営に関する考え方が分かります。
配当性向が高い企業は、株主への利益還元に積極的であると判断できます。
一方で、配当性向が低い(利益の多くを内部留保している)企業が良くないとは言い切れません。
なぜなら、その資金を設備投資やM&Aなどの成長投資に回していて、将来的な成長が期待できるケースがあるからです。
配当性向は、配当の安定性・持続可能性を判断する材料にもなります。
利益に対して配当性向が高すぎると、少し業績が悪化しただけで配当を維持できなくなる減配リスクが高いと考えられます。
配当性向の計算式と具体例

配当性向の計算方法は2通りありますが、どちらも結果は同じです。
会社全体で見た場合|配当金総額 ÷ 当期純利益
配当性向を、会社全体の利益と配当金総額から計算する場合には、以下の式を用います。
配当金総額とは、企業が株主全体に支払う配当金の合計額であり、当期純利益とは最終的に企業に残った利益です。
例えば、当期純利益が500億円、配当金総額が150億円の企業の場合、配当性向は以下のようになります。
1株当たりの数値を用いる場合
配当性向を、1株当たりの利益や配当金額から計算する場合、以下の式を用います。
投資家がより頻繁に目にするのは、こちらの1株当たりの数字を使った計算式かと思います。
例えば、1株当たり配当金が30円、1株当たり当期純利益(EPS)が100円の企業の場合、配当性向は以下のように計算します。
配当性向がマイナスになるケースとは?
配当性向がマイナスになるのは、分母である当期純利益がマイナス(赤字)の場合です。
例えば、当期純利益がマイナス100億円(赤字)で配当金総額が50億円の場合、配当性向は以下のようになります。
企業は業績が赤字に転落した際に、すぐに無配にするのではなく、過去の利益剰余金(内部留保)を取り崩して配当を維持する場合があります。
この場合に配当性向がマイナスになるのです。
一時的な要因による赤字計上であれば、大きな問題はありませんが、黒字浮上の見込みがないと、いずれは無配に転落する可能性が高いため注意が必要です。
[関連]赤字でも株価は上がる!?赤字企業の株に投資するメリットやポイントをプロが解説!
配当性向の計算式と配当利回りとの違い

配当性向と並んでよく用いられるのが配当利回りです。
配当性向が「企業の利益に対する配当の割合」を示すのに対し、配当利回りは「株価に対する配当の割合」を示します。
配当性向は、企業の利益から見て配当が妥当な水準かを判断する指標です。
一方、配当利回りは投資した金額(株価)に対してどれくらいの配当金が得られるか(リターン)を判断する指標です。
両者は役割が異なるため、投資をする際にはセットで確認しましょう。
配当性向は何%が目安?水準の考え方

配当性向は、高ければ高いほど良いわけではありません。
適正な水準は、企業の状況や属する業種によって異なります。
一般的な配当性向の適正水準・目安は30%程度
配当性向は、30%程度が適正水準・目安として語られる場合が多いです。
利益を株主に還元しながらも、事業投資を行い成長を目指す企業は、配当性向30%程度を掲げているケースが多いのです。
利益の3割を株主に還元し、残りの7割を成長投資や内部留保に回すバランス型の経営と言えます。
市場でも、配当性向が30%を超えていれば、株主還元に前向きだと評価されやすいです。
企業のタイプによっても目安は異なる
ただし、企業の成長ステージによって、適正な配当性向は大きく異なります。
成長企業は、利益を先行投資に回す段階にあるため、低め(0%〜30%)の配当性向が望ましいとされます。
これに対して、電力や通信など安定した収益を上げているものの大きな成長投資の機会が少ない成熟企業には、積極的な株主還元が求められます。
そのため、高め(40%〜60%)の配当性向が目安となります。
また、景気変動で利益が大きくブレる景気敏感業種は、業績悪化に備えて内部留保を厚くする傾向があるため、配当性向は比較的低めに設定されやすいです。
[関連]グロース株とバリュー株の違いとは?見分け方や投資する際のメリット・デメリットを解説!
配当性向が高すぎる・低すぎる場合のリスク

配当性向が極端に高い、または低い場合は、それぞれ注意すべきリスクが存在します。
配当性向が高すぎる場合のリスク
配当性向が80%以上など、極端に高い企業は、業績が悪化している可能性があります。
配当性向の分母である当期純利益が減少しているのにも関わらず、分子である配当金総額を減らさなければ、配当性向は高くなるからです。
高すぎる配当性向が続いている企業は、業績が早期に改善しなければ、配当を出せなくなってしまう可能性が高いため注意が必要です。
配当性向が低い企業が必ずしも悪くない理由
配当性向が10%や20%といった低い水準の企業が、必ずしも株主還元に消極的な企業とは限りません。
たとえば、企業が高成長期にあり、利益を全て成長投資に回した方が良いと判断しているケースがあります。
今は配当を出さずに利益の拡大に全力を注いだ方が、業績の拡大を通じて株主に還元できると経営者が判断しているわけです。
また、景気変動の激しい業種で、将来の減配に備えるために意図的に内部留保を厚くしている場合もあります。
さらに、配当ではなく、自社株買いによる株主還元を積極化している可能性もあります。
特に日本企業では、近年、配当金と自社株買いを合わせた「総還元性向」を重視する傾向が強まっています。
配当性向を投資判断に活かす方法

ここからは、投資候補としている銘柄の配当性向を実際に見る上での注意点や、具体的な見方を解説していきます。
配当性向の「推移」を見る重要性
配当性向を確認する際には、単年度の数字だけではなく、推移を見るようにしましょう。
配当性向が乱高下している企業は、業績が不安定か、配当方針が定まっていない可能性があります。
一方で、配当性向が安定している企業は、配当方針が一貫しており、不況に強い安定配当株である可能性が高いと言えます。
一時的な損益の計上に注意
配当性向の分母である「当期純利益」には、特別損益(一過性の大きな利益や損失)が含まれるため、数字が一時的に歪む場合があります。
例えば、土地・資産売却益などの特別利益が計上された時は、当期純利益が一時的に膨らみ、配当性向が低くなってしまいます。
逆に、リストラ費用・減損損失などの特別損失が計上された時は、当期純利益が大きく落ち込み、配当性向が高く(あるいはマイナスに)なってしまいます。
この場合には、一時的な要因を取り除いた経常利益や営業利益に基づき、配当性向を計算し直すと良いでしょう。
もしくは、過去の配当性向や純利益を確認し、一過性の損益計上が無くなった場合に、どの程度の配当性向に落ち着くかを確認する方法も有効です。
[関連]損益計算書(P/L)とは?投資初心者が押さえておきたい決算書の見方をアナリストが解説
配当方針を明示している場合の確認方法
企業によっては、株主還元の方針として具体的な配当性向の目標値を公的に明示している場合があります。
決算発表時にあわせて開示される決算説明資料や中期経営計画、企業のIRサイト内の「株主還元方針」といったページに記載されている場合が多いため、是非確認してみましょう。
この目標値は、企業が株主に約束する水準ですので、企業が目標を達成できているかのチェックによって、投資判断の確度を上げられます。
目標値が公表されているにもかかわらず、実際の配当性向がそれを大きく下回っている場合は、企業側の説明を注意深く聞く必要があります。
また、目標値が引き上げられた場合、株主還元により注力する方針であると考えられ、注目に値します。
減配・無配リスクを見抜くポイント
減配・無配リスクを見抜く上では、配当性向の他にも、いくつかの指標をチェックしておきたいです。
まず、当期純利益が減少傾向にある場合、配当の維持が困難になる可能性があります。
次に、利益は黒字でも、本業での現金の流れを示すフリーキャッシュフロー(自由に使えるお金)がマイナスの場合、いずれ配当の原資が尽きるリスクがあります。
さらに、有利子負債が増加している場合も、借金が増え続け、利息の支払いに収益が圧迫されるリスクがあるため、注意が必要です。
[関連]貸借対照表(バランスシート)とは?投資家初心者が企業価値とリスクを見抜く読み方を解説
配当性向の調べ方・確認方法

配当性向は、企業の公式情報や金融情報サイトで簡単に確認できます。
決算短信・有価証券報告書での確認方法
配当性向は、企業の業績の概況をまとめた速報資料である決算短信の数字から計算できます。
決算短信の「連結損益計算書(当期純利益)」と「配当の状況」の項目から当期純利益と配当金総額の数字を拾って計算できます。
もう1つは、企業が年に一度、金融庁に提出する詳細な報告書である有価証券報告書です。
ここでは、過去の業績推移や配当方針がより詳しく記載されています。
証券会社サイト・金融情報サイトでの調べ方
投資家が日常的に利用する証券会社や金融情報サイトに、配当性向が計算済みの指標として掲載されている場合があります。
例えば、Yahoo!ファイナンスの各銘柄の情報ページで、「配当」という欄を選ぶと、配当性向が表示されています。

よくあるQ&A|配当性向の疑問を解決
まとめ|配当性向を味方につけて、安定配当銘柄を見極めよう

配当性向は、企業の株主還元への姿勢と配当の安定性を測る重要指標の1つです。
特に高配当株に投資を行う場合には、配当利回りだけではなく配当性向も確認し、配当の安定性を見極めるようにしましょう。
ただ数字を見るだけにとどまらず、その理由や過去の配当性向の推移まで踏み込んで確認すれば、その企業をより深く理解できるはずです。
弊社では、アナリストが厳選した注目銘柄情報を無料配信しています。
アナリストがどのような視点でその銘柄に注目しているのかも記載しており、銘柄選びの参考になると思いますので、是非あわせてご確認ください。
銘柄情報は、以下のフォームより無料でお受け取りいただけます。
アナリストが選定した銘柄が知りたい!
今なら急騰期待の“有力3銘柄”を
無料で配信いたします
買いと売りのタイミングから銘柄選びまで全て弊社にお任せください。
投資に精通したアナリストの手腕を惜しげもなくお伝えします。
弊社がご提供する銘柄の良さをまずはご実感ください。
▼プロが選んだ3銘柄を無料でご提案▼
執筆者情報
日本投資機構株式会社 証券アナリスト(CMA) テクニカルアナリスト(CMTA®)
国内株式、海外株式、外国為替の領域で経験豊富なアナリスト・ファンドマネージャーのもと、金融市場の基礎・特徴、マクロ経済の捉え方、個別株式の分析、チャート分析、流動性分析などを学びながら、日本投資機構株式会社では唯一の女性アナリストとして登録。自身が専任するLINE公式など各コンテンツに累計7000名以上が参加。Twitterのフォロワー数も3万人を超える人気アナリスト。

![Invest Leaders[インベストリーダーズ]](https://jioinc.jp/investleaders/wp-content/uploads/2025/07/logo_01.png)