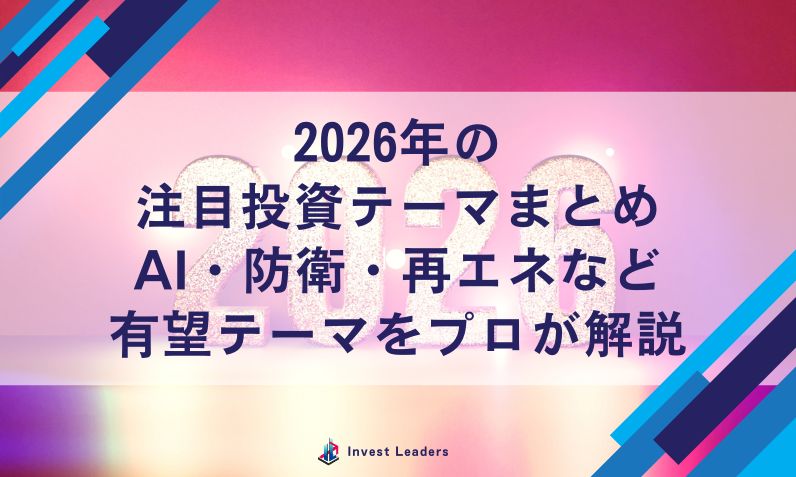2026年はどのような銘柄に買いが向くでしょうか?
この記事では、2026年の投資戦略を考えている方に向けて、2026年の注目すべきマクロトレンドと、成長が見込まれる注目テーマをまとめます。
2026年の株式市場見通し

2026年は、多くの企業にとって事業の先行きが見通しやすい環境が続くと考えられます。
為替の変動は抑制される期待が高く、米国の関税政策も軟化しているからです。
詳しく確認しておきましょう。
日米金利差は縮小も財政拡張で円高進行は限定的に
米国の中央銀行(FRB)は、インフレ率の落ち着きを確認しながら、2026年末までに政策金利を3.4%前後へとゆっくり下げるシナリオを描いています。
また、パウエル米FRB議長の任期が2026年5月で満了し、より積極的な利下げを求めるトランプ米大統領の意向に沿った人物が後任となる可能性が想定されています。
利下げが進展し、金利の低下を通じて、株式市場は追い風を受けそうです。
一方、日本銀行は、金融政策の正常化を続ける見通しです。
米FRBが利下げを、日銀が利上げを進めた場合、日米の金利差は縮小するため、通常為替は円高方向に動きやすくなります。
ただし、高市政権が拡張的な財政政策を進めて財政が緩むとの思惑から、円が売られやすくなっている面もあります。
2026年12月に日銀が利上げを行った場面でも為替はむしろ円安方向に動いており、輸出企業の業績を圧迫するような過度の円高進行は起こりづらくなっています。
トランプ関税への警戒感は後退か
2025年4月5日に米国は全輸入に対する10%のベースライン関税の徴収を開始し、国別の相互関税を上乗せする枠組みを打ち出しました。
当初市場は大きく動揺しましたが、その後の展開で過度な悲観は後退しています。
難航が懸念された米中の協議も進展し、米国は関税のさらなる引き上げを少なくとも2026年11月10日まで停止する方針を示しています。
中国側はレアアースなど戦略鉱物の輸出管理を緩め、報復関税や非関税措置の停止、農産物購入の再開などを約束しています。
これにより、企業は価格転嫁やサプライチェーン再設計のための時間的な猶予を得ています。
世界経済の先行きに関する不透明感が払しょくされ、投資家心理は大きく改善しました。
当面はこうした状況が続くとみられますが、11月の米中間選挙の時期が近づくと再び政治的な不透明感が強まる可能性には注意を払いたいです。
[関連]中国の対日輸出規制で急浮上したレアアース関連銘柄に注目!4つの恩恵パターンと厳選9銘柄
2026年に注目すべき4大マクロトレンド

注目の投資テーマを考える上では、長期的なマクロトレンドを押さえておきたいです。
短期的なニュースに惑わされず、長期的な変化を捉えたテーマに投資することが、成功の鍵となります。
世界的な地政学リスクの高まり
ウクライナ紛争の長期化、中東の不安定化、そして台湾海峡を巡る米中間の緊張など、世界的な地政学リスクは2026年も主要な懸念材料であり続けます。
直近では、高市首相の台湾をめぐる発言を受けて、日中の関係も悪化しています。
2026年も重要物資の供給網や技術覇権を巡る対立が市場のボラティリティ(変動幅)を高める要因となるでしょう。
エネルギー安全保障と脱炭素転換2.0
地政学リスクの高まりを受けて、エネルギー安全保障が重要テーマとなっています。
これまでの脱炭素一辺倒ではなく、安定供給と脱炭素の両立を目指す「脱炭素転換2.0」への投資が加速するでしょう。
具体的には、再生可能エネルギーだけでなく、原子力の再評価、水素・アンモニア等の次世代燃料、そしてLNG基地など既存インフラの強化が焦点となります。
サプライチェーンの再構築、国内回帰
地政学リスクと経済安全保障の観点から、主要国は重要戦略物資(半導体、電池、医薬品など)のサプライチェーンを、友好国や国内へと回帰させる動きを強めています。
これにより、国内の工場建設、設備投資、そして物流・インフラ関連企業への恩恵が見込まれます。
資本効率改善・株主還元強化
東京証券取引所による「PBR1倍割れ」企業への改善要請は、2026年も日本株市場の構造変化を促す最も強力なドライバーであり続けます。
企業は今後も自社株買いや増配といった株主還元策を強化し、経営資源の再配分を進めるでしょう。
これは日本株の持続的な評価向上に繋がる中長期テーマです。
[関連]PBR(株価純資産倍率)とは?業種別の目安や計算式、投資での活用術をプロが解説!
2026年に成長が見込まれる9大テーマ

2026年も、AI関連銘柄への注目は続き、前述したようなマクロトレンドも追い風に多くの企業が成長を続けそうです。
構造変化を背景に、特に成長が期待される9つの具体的なテーマを解説します。
①AI|フィジカルAIなどに裾野が広がる
AI関連銘柄については、2025年に日本株のけん引役となったアドバンテストやソフトバンクグループなどの上昇が一服する一方、物色の裾野が広がっています。
特に注目されているのがフィジカルAIの分野で、2025年12月にはエヌビディアとの協業を推進すると発表したファナックが急伸する場面が見られました。
フィジカルAIの社会実装や需要の拡大はまだ先になるとみられますが、もし実装が進んだ場合の業績へのインパクトが大きくなるとの期待から2026年も関連銘柄への物色が続きそうです。
また、Googleの手掛けるAI「Gemini」が高い性能評価を受けたため、AI開発競争の激化も意識されています。
AI開発競争の勝者になり得るとして、OpenAIだけではなく、Googleの周辺企業にも注目しておきたいです。
[関連]フィジカルAI関連銘柄まとめ!次のAIテーマとしてプロが注目する理由も解説
[関連]Gemini関連銘柄をピックアップ!Gemini3発表でGoogle関連企業に注目集まる
②半導体|メモリや先端パッケージが主戦場に
半導体市場は引き続き力強い成長が続きますが、特に注目すべきは「AIチップの性能を極限まで高める技術」です。
AIに不可欠な高性能メモリ(HBM)や、複数のチップを立体的に重ねて一体化する先端パッケージ技術が市場をけん引します。
引き続き、製造工程の「最も難しく、進化が求められる部分」に特化した企業が有利です。
例えば、先端パッケージに必要な高性能な基板(ABF基板)や、超微細な回路を描くEUV周辺技術、そしてその製造に欠かせない特殊な薬液や材料などの高付加価値領域が挙げられます。
[関連]半導体が大躍進!脱中国・AI新時代の覇権を握る関連テーマ株を徹底解説!
③宇宙開発|衛星通信・防災・測位が民間化へ
これまでは国が主導してきた宇宙開発が、民間ビジネスとして本格化します。
小型衛星の大量打ち上げで、衛星通信や地球観測(気象・環境データ)の商用サービスが加速します。
日本では、正確な位置情報を提供する準天頂衛星(QZSS)の整備が進展中です。
自動運転車へのデータ提供、ドローンを活用した物流、そして災害時の状況把握(防災)といった分野での宇宙データ活用が期待されます。
投資機会は、衛星データ解析サービスや、衛星と通信するための地上局など、宇宙技術を地上サービスに繋げる企業に広がります。
[関連]【宇宙関連銘柄】政策・商業・防災…広がる成長期待と注目株とは?
④再エネ2.0|急増する電力需要への対応が急務に
AIやEV(電気自動車)の普及による電力需要の急増に対し、太陽光発電などの再生可能エネルギーだけを増やすだけでは限界があります。
そこで、再エネを軸にしつつも安定供給を重視する「再エネ2.0」への転換が急務です。
具体的には、系統増強(電力を運ぶ送電網の強化)、系統用蓄電(大型バッテリーでの電気の貯蔵)、そして家庭や工場での電気の使い方を最適化する省エネや調整力(DR)などの強化が進む見通しです。
送電設備、大型蓄電池、そして電力と電気を使う側を繋ぐ制御技術(PPAなど)に注目が集まります。
[関連]再生可能エネルギー関連株を徹底解説|投資初心者が押さえるべき注目企業
[関連]太陽光発電関連銘柄は脱炭素の本命!注目理由と投資視点を解説
⑤防衛・安全保障|スマート防衛領域への投資加速
防衛費の増加に伴い、スマート防衛領域への予算配分も加速しそうです。
これは、従来の戦車や戦闘機だけでなく、サイバーセキュリティ、宇宙、無人兵器(ドローン・UAV)といった情報戦に勝つための技術です。
ここで注目されるのが、デュアルユース技術、つまり民間と軍事の両方で利用可能な技術です。
高性能なAIソフトウェア、センサー、通信技術を持つ一般の民間企業が防衛のサプライチェーンに参入する機会が増加するでしょう。
[関連]防衛関連銘柄で急騰を掴む!投資家が注目する有望企業を解説
⑥バイオハッキング|ウェアラブル端末や再生医療に注目
バイオハッキングとは、テクノロジーを駆使して自らの身体と脳のパフォーマンスを意図的に最適化・拡張する取り組みを指します。
関連銘柄としては、生体情報を可視化するスマートウォッチや、体内の変化をリアルタイムで追跡する血糖値測定器などを開発する精密機器業種が挙げられます。
また、老化抑制の研究やゲノム編集を行うバイオテクノロジー企業、さらには再生医療のプラットフォームを提供する化学・製薬企業も、市場を支える重要なプレイヤーです。
AIによる個別最適化やウェルネスツーリズムの普及に伴い、テクノロジーと医療が融合した巨大な成長産業として期待を集めています。
⑦内需・サービス|物価高対策やインバウンド2.0で活況に
訪日外国人(インバウンド)は増加ペースを維持していますが、消費の質が変化しています。
単にモノを買うだけでなく、地方観光や日本の文化体験を重視するコト消費の好調さが続いています。
これにより、高級旅館や体験型ツアーを提供する事業者が優位に立つと考えられます。
AIを使った最適な価格設定や予約・在庫の管理など、オペレーションを高度化する事業者がこの恩恵を大きく受けるでしょう。
また、高市新政権が急務としている物価高対策によって、国内消費も堅調に推移する期待ができます。
[関連]インバウンドが日本経済を動かす!注目の関連銘柄と今後の展望
[関連]高市銘柄に再注目!宇宙・半導体・サイバーセキュリティなど注目銘柄を紹介
⑧サイバーセキュリティ|高市政権も注力
サイバー攻撃が巧妙化・多発しているため、国としてアクティブ・サイバーディフェンス法の整備など、防御体制の制度強化が進んでいます。
特に、SOC(セキュリティ運用)、人材育成、そして「ゼロトラスト」(何も信用しないという前提の防御思想)といった分野を国が後押ししています。
工場設備や自動車向けセキュリティといった新しい分野でも需要が拡大し、専門企業から大手まで、運用・監査・教育といった幅広い分野で安定した需要が見込まれます。
[関連]サイバーセキュリティ関連株の本命は?|初心者でも狙いやすい注目銘柄を厳選紹介
⑨エンタメ・IP|推し活と海外進出で成長続く
アニメやゲームといった日本のコンテンツ(IP)は、海外での売上が大きく伸びています。
政府も経済効果の拡大を目標に掲げています。
重要なのは、「多層収益化」、つまり1つのIPから映像配信、音楽、ライブイベント、グッズ販売といった複数の収益を生み出すエコシステムです。
この多角展開を支える配信プラットフォーム、越境EC、決済システムの整備が進み、関連企業の成長を後押しします。
[関連]推し活の市場規模は3.5兆円!Z世代の「推し消費」を投資対象として徹底解説
2026年イベントカレンダーと月別投資戦略

2026年の投資計画を立てる上では、注目テーマだけではなく、イベントや月別の傾向(アノマリー)も考慮しておきたいです。
あらかじめ株価が軟調に推移しやすい時期や市場の変動が大きくなりそうな時期を把握しておけば、戦略的なエントリーや利益確定が可能となります。
2026年の経済イベント・スケジュールや各月のアノマリーは以下の記事にまとめています。
[関連]2026年の経済イベントカレンダー|株式投資に使える主要スケジュールや季節性まとめ
成功するテーマ投資のためのポイント

人気のテーマ株は魅力的に映りますが、投資で成功するにはテーマ性だけで飛びつかずに、業績や株価の位置もきちんと確認する必要があります。
ここでは、買いが続く銘柄を選別し、高値づかみを避けるための具体的なポイントを解説します。
KPI(重要業績評価指標)を深堀り
テーマ株へ投資する際には、そのテーマが企業の売上や利益に具体的に結びついているかを確認しておきたいです。
テーマ性と業績の拡大が重なることで、息の長い株価上昇が実現するからです。
売上高や各利益の伸びを確認するのは勿論のこと、その裏付けとなるKPI(重要業績評価指標)もチェックしたいです。
例えば、半導体関連企業の場合、単に「受注が増えた」というニュースに惑わされず、実際に製品の「出荷数量」が増えているか、そして「平均販売価格(ASP:単価)」が上昇しているかという両面で成長を確認することが重要です。
ASPが上がる企業は、高い技術力やブランド力を持ち、価格競争に巻き込まれにくい高付加価値型の成長をしている証拠と言えます。
株価に期待感が織り込まれているかをチェック
どれほど素晴らしい成長テーマでも、株価が期待を上回り過ぎていれば、高値づかみになってしまう可能性が高いです。
株価評価指標(バリュエーション)を使って、冷静に判断する規律が必要です。
テーマ株はPER(株価収益率)が高くなりがちですが、同業他社や過去のレンジと比べて「異常に高い水準」にないかを確認し、無理な水準で買わないことが重要です。
次に、PBR(株価純資産倍率)とROE(自己資本利益率)の組み合わせも重要で、特に日本市場では、低PBRを改善する姿勢と高いROEを両立している企業が構造的な資金流入の恩恵を受けやすい傾向があります。
人気=割高?高値づかみを避けるポイント
イベントやニュースで人気が沸騰している時に投資をすると、高値づかみになるリスクが高いです。
企業の決算発表や大型展示会といったイベント前は、期待が先行して株価が急騰しがちですが、イベントが終了したり、期待通りのニュースが出なかったりすると、利益確定売りが出て株価が急落する傾向があります。
株価が短期間で上昇しすぎていないかは、銘柄を買い付ける際にチェックするようにしましょう。
チャートも確認して、移動平均線などを頼りに、下落局面での買い(押し目買い)を狙うと高値づかみを避けられます。
[関連]好決算なのに株価が下がる理由は?下落時に知っておきたい売買の考え方を解説!
意図しない集中投資にならないように注意
期待できるテーマに絞って銘柄を買い付けていくと、知らず知らずのうちに同じ景気動向に強く左右される「同一テーマ」の集中投資になっている場合があります。
例えば、AI、半導体、データセンター関連の恩恵を受けている銘柄は、AIへの期待が萎んだタイミングで一気に急落してしまうリスクがあります。
自身のリスク許容度に応じて、ポートフォリオが偏りすぎていないか、意識的に見直すと良いでしょう。
その上で、AI・半導体関連の銘柄に偏り過ぎている場合には、景気変動の影響を受けにくい内需・サービス系の銘柄や、政府からの受注が主軸になっている防衛関連の銘柄を組み合わせるといった戦略を取りたいです。
またデータセンター向けでも、半導体の製造ではなく、電設工事、空調、配電といった土木・建設系の領域は、半導体チップの価格変動の影響を直接受けにくいため、有効な分散先となり得ます。
まとめ|マクロトレンドを追い風に成長を続ける銘柄を掴め

2026年は、AIの実用化がさらに進み、幅広い企業の追い風となりそうです。
また、地政学リスクの高まり、サプライチェーンの再構築というマクロトレンドも継続します。
これらが売上や利益の伸びに直結し、大きく上昇する銘柄が数多く誕生するでしょう。
しかし、人気のテーマ株には高値づかみや集中投資のリスクが伴います。
本記事で解説したKPI分析やバリュエーションの確認を徹底し、「成長性」と「割安感」を兼ね備えた銘柄を選別することが重要です。
また、どの企業が本当に成長するのか、個別銘柄の選定は難しいという方には、私たちアナリストチームが厳選した急騰期待銘柄をご覧いただきたいです。
以下のフォームから無料で受け取っていただけますので、今すぐご確認ください。
アナリストが選定した銘柄が知りたい!
今なら急騰期待の“有力3銘柄”を
無料で配信いたします
買いと売りのタイミングから銘柄選びまで全て弊社にお任せください。
投資に精通したアナリストの手腕を惜しげもなくお伝えします。
弊社がご提供する銘柄の良さをまずはご実感ください。
▼プロが選んだ3銘柄を無料でご提案▼
執筆者情報
日本投資機構株式会社 アナリスト
準大手の証券会社にて資産運用のアドバイザーを務めた後、日本株主力の投資顧問会社の支店長となる。現在は日本投資機構株式会社の筆頭アナリストとして多くのお客様に株式投資の助言を行いつつ、YouTubeチャンネルにも積極的に出演しており、資産運用の重要さを発信している。

![Invest Leaders[インベストリーダーズ]](https://jioinc.jp/investleaders/wp-content/uploads/2025/07/logo_01.png)